運用ノウハウ

Googleタグマネージャー(GTM)手順完・・・
2020.12.23
TRASPコラム
運用ノウハウ
更新日:2023.04.02
公開日:2020.09.26
ホームページ制作においては、制作後に分析を行いよいホームページへと内容を変更し続ける作業が重要です。立ち上げ当初は効果が出ていても時代の変化で効果が薄れる可能性もあるので、ユーザビリティを意識しながら改善を柔軟に行うとホームページが有効な集客コンテンツとして長期間機能するようになるでしょう。
ホームページ制作を行う際事前に改善のよくあるパターンを把握しながら、基本的な改善の流れを覚えておくと安心です。
今回はホームページの改善方法を知りたい方向けによくある改善パターン、そして失敗事例や成功させるための基本的な改善の流れなどを解説していきます。
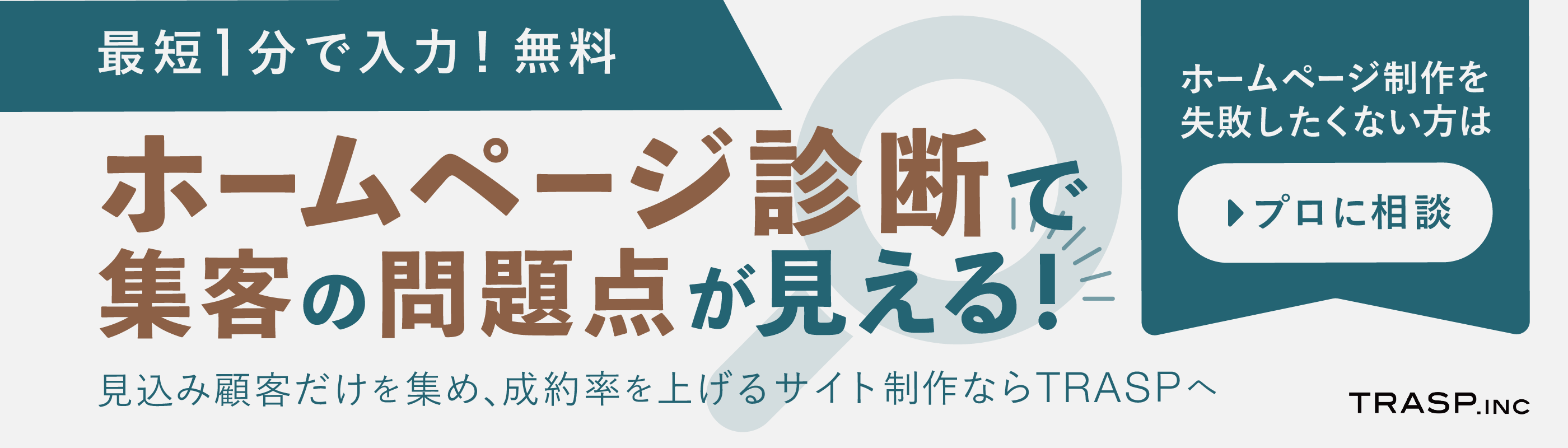
目次

ホームページのパフォーマンスを落として費用対効果を悪化させている要因としては、次のようなものが挙げられます。対応策も提示するので理解を深めてみてください。
ホームページを公開する際は、必ずターゲットユーザーに対して情報が伝わるような構成にする必要があります。ユーザーの悩みに合わせて、コンテンツを閲覧すると得られるメリットをユーザー目線で伝達できるようにしておくのがポイントです。
たとえば
といった手法が考えられます。
「他社よりお得」といったプッシュしたい情報よりも、「ターゲットユーザーがどんな情報を求めているのか」に沿ってピックアップしたい情報をまとめましょう。プッシュの強いホームページよりもターゲットユーザーに絞ったメリットを提示する内容にしたほうが、ユーザーが自分ごと化しやすく効果が出やすいのは基本です。
ホームページを読むユーザーは時間がない場合も多いですから、スムーズに欲しい情報を閲覧できるようにしておく必要があります。しかし閲覧したい情報の場所が分かりにくいとストレスの原因になり、離脱が発生してしまうので注意が必要です。
たとえば料金プランはユーザーがサービスを比較検討する際必要な項目ですが、トップメニューにないと探す必要が出てくるので「検討をやめよう」という気持ちにもなってしまいます。コンテンツを読んだユーザーへスムーズに契約を促したい場合は、トップメニューに「料金プランのご説明」といった項目を分かりやすいデザインで設置しておく必要があるでしょう。
また「導入事例」のメニューの下に「飲食」、「アパレル」といったサブメニューを用意するといったように情報を整理、階層化してユーザーに分かりやすく提示する視点も重要です。
さらに各ページに関連のあるページ情報を最後にリンク掲載するといった、導線上の工夫も必要です。
ホームページに自社の伝えたい情報をただ過剰に掲載し過ぎると、情報過多で提示されている情報が返って見えにくくなるというデメリットがあります。ホームページ制作初心者だとついやってしまう、典型的なミスの一つです。
余計な情報を削りながらユーザーへメリットを伝えられるコンテンツを制作するのがポイントです。ユーザーへ情報を伝えやすくするためには、
といった工夫が有効です。
専門語は基本使わないほうがよいでしょう。自社と同じ業種の企業に情報を伝えるBtoBのサービスサイトならば専門語を多用する場合もあるかもしれませんが、一般消費者まで相手にした商品やサービスの宣伝の場合、専門語は相手の理解を阻害してしまう要因の一つになっていしまいます。「自社では当たり前に使っている」という言葉であればあるほど気軽に使ってしまうので、注意が必要です。
改善方法の例としては、
といった方法が挙げられます。
またカタカナ語も相手によっては伝わらない場合があるので、同じように噛み砕いたり補足を付けたりといった補足が必要なケースがあります。ただし世間一般に知れ渡っており説明の必要がないという単語の場合はそのまま使っても大丈夫です。ターゲットユーザーにもよるので注意してコンテンツを制作しましょう。
商品やサービスに関しては、必ずデメリットや注意点もあるはずです。ユーザーはそういったネガティブな情報も敏感に感じ取って疑問を感じてしまうので、どこかでネガティブな情報もあえて説明して安心させるというテクニックも必要となります。
不安を解消するには、
といった方法が有効です。
ただしデメリットや注意点ばかりを挙げると悪い印象が増えてしまう恐れがあるので、カバーする情報を入れたりといった手法でイメージをよい方向へ自然に持って行けるようにしてみてください。
ホームページにおけるコンバージョン(商品やサービスの成約や資料請求など)を獲得するためには、スムーズにユーザーが取りたいアクションを実行できるようにレイアウトを工夫しておく必要があります。
たとえば単に「問い合わせする」というフレーズだと、何が起きるか分かりません。「問い合わせして資料をもらう」といったように何が起こるかを含めて記載しておくと、コンバージョンが増加する可能性もあります。
また単に「商品やサービスを契約する」といったCtoAだけでなく、「資料請求を行う」や「無料プランを試す」といった下位のコンバージョンに関係するCtoAボタンの設置も検討してみてください。ハードルが低ければ自社の収益に直結はしにくい分、コンバージョン率を高めてその後の施策へつなげられます。

ここではホームページ制作において改善を失敗する事例をご紹介していきます。自社が該当していないかチェックして、事例と同じような行動をしている場合は対応を改めましょう。
ホームページ改善を行う際に、
といったケースに遭遇することもあります。関係者と連携が取れていないと改善施策が上手く回らず、情報不足なままアクセス解析をしてしまい失敗を招く恐れがあります。
ホームページ改善を行う際は営業部門や広報部門など関連の部署と連携を行い、ホームページに関してどのような行動を改善の対象になる期間中取ったか確認しておきましょう。また外部業者には改善に必要な情報を定期的に渡して、良好な関係を継続させられるよう努力するのもポイントです。
アクセス解析を行う際は、仮説が必要です。仮説によりどこに改善の原因があるのかを見つけ出して、対応する施策を行うことでホームページの改善につながります。
しかしデータの根拠なしに仮説を立てようとするのは避けてください。
といったように感覚的に仮説を立ててしまうと、ユーザーのニーズとずれが生じてしまう可能性が高まります。仮説を立てる際は必ず分析を行い、根拠となるデータの異変を見つけておきましょう。
また逆にアクセス解析が目的になって、仮説を立てないのもNGです。アクセス解析で分かるのはあくまでデータの根拠だけであり、そこから仮説を立てて検証を行わないと調べただけで終わってしまいます。せっかく分析したデータを無駄にしないためにも、アクセス解析と仮説の提案はセットで行ってみてください。
アクセス解析で分析に必要な項目が抜けていると、施策にずれが起きる原因になります。たとえば現在ではスマホでホームページにアクセスするユーザーが多いのが一般的ですが、パソコンからのアクセス流入だけを調べると現実と大きな乖離が起こって分析の精度が下がってしまいます。
またアクセス解析ツール側が新しいニーズに対応して、機能を追加している場合もあるので注意が必要です。定期的にアクセス解析ツールの変化を確認しながら、必要なデータを適宜追加して解析の精度を上げていく必要があるでしょう。

ここからは、ホームページ制作の際に改善を行う基本的な流れを解説していきます。基本的な流れを知っておけば改善を失敗するリスクも防げるので、ぜひチェックしてみましょう。
まずは自社サイトのデータを分析して、現状を把握していきます。
データには2種類あります。
どちらか片方に偏らず両方のデータを集めることが、ホームページ改善において一つポイントです。
定量的なデータとは、
といった数値化がしやすいデータです。アクセス解析ツールで数値を把握しながら課題を分析していきましょう。
対して定性的なデータとは、
といった数値化がしにくい人の感情に伴うデータです。定性的なデータはアンケートでコメントをもらったり、オンライン座談会で自社のファンとなってくれているユーザーに質問したりすると収集できます。
定量的なデータだけでは分からない改善データが見つかるかもしれないので、こちらも積極的に集めましょう。
次にデータを基に、自社のホームページのどんな点に問題があるのかを細かく深堀していきます。
たとえば、
といったケースが考えられます。
なるべく数値も併せながら問題を分析していくのがポイントです。目標に対してどのくらい数値を改善すればよいのか判断する基準になるからです。
そして目標に合わせて問題に優先順位を付けるのもポイントになってきます。限られた時間の中で同じタイミングで複数改善を行うのは難しく、まずは効果の最も出る問題解決から行うのが重要だからです。
次に問題を解決できるような仮説を立てて、施策を実行する段階に移行します。
たとえば
といった改善施策が考えられます。
データを基に立案できる改善施策は一つだけではありません。複数の改善施策を同じ条件で試してみる「A/Bテスト」を実行するのも重要です。A/Bテストにより同じ条件の下で各施策を分析して、どの施策が一番効果があるのかを確認できます。
改善の施策を実行したら、再び得られたデータを分析していきます。そこで数値も確認しながら、目標通り改善効果が得られたかを確認していきましょう。
施策が成功した場合は他の問題の仮説立てと検証を行います。また失敗した場合は他の改善施策を考えて実行して、効果が出るか確認していきます。
ホームページ改善は一朝一夕でできるものではなく、今まで見てきたような「PDCAサイクル」を意識して長い目で改善を行うのがポイントです。一つの施策で効果が出なくても落ち込む必要はなく、また別の施策を考えて検証を行い効果が出るまで粘り強く改善を行う姿勢が重要になってきます。
改善を何度も行っていくとノウハウとして蓄積されていきます。ノウハウが貯まれば他の施策の改善に活かし、効率よく改善を行えるようになるでしょう。ただし改善に掛ける時間もないという方は、ぜひ外注して作業効率化することも検討してみてください。

今回はホームページ改善におけるよくある改善パターン、そして失敗事例や基本的な改善の流れなどを解説していきます。
ホームページにおいては、プッシュし過ぎて嫌がられたり情報が不足したりといった問題が起こります。データを基にどんな課題があるかを判断して、次の施策へ活用していくのが重要です。