建設業
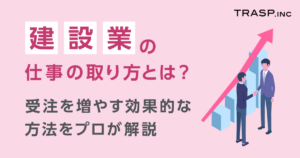
建設業の仕事の取り方とは?受注を増やす効果的・・・
2022.06.01
TRASPコラム
建設業
更新日:2023.04.03
公開日:2023.03.06
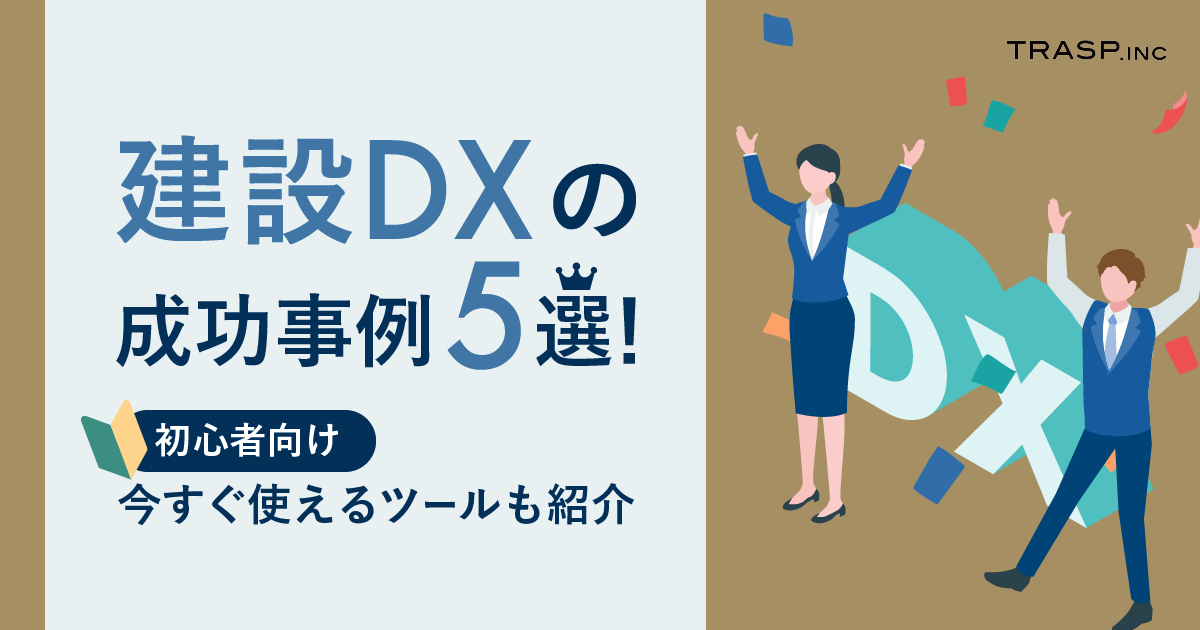
人材不足に加え、高齢化による後継者不足が深刻な問題になっている建設業界。この状況を解決すべく、IT技術を活用した「建設DX」への取り組みを行う企業が増えています。
そのようななかで、「建設DXを導入するメリットとは?」「成功事例を詳しく知りたい」と悩まれている担当者さまもいらっしゃるでしょう。
建設DXを実践し、成功させるためには押さえるべきコツが複数あります。また「具体的にどのような事例があるのか」を把握し、自社に必要な施策を実行することも欠かせません。
そこで、この記事では建設DXの成功事例5選を徹底解説!建設業界で多くのサイト制作・Web集客を支援してきたTRASPが、DXを実践するメリットを詳しくまとめました。初心者向けにおすすめしたいツールもあわせて紹介しますので、ぜひご一読ください。
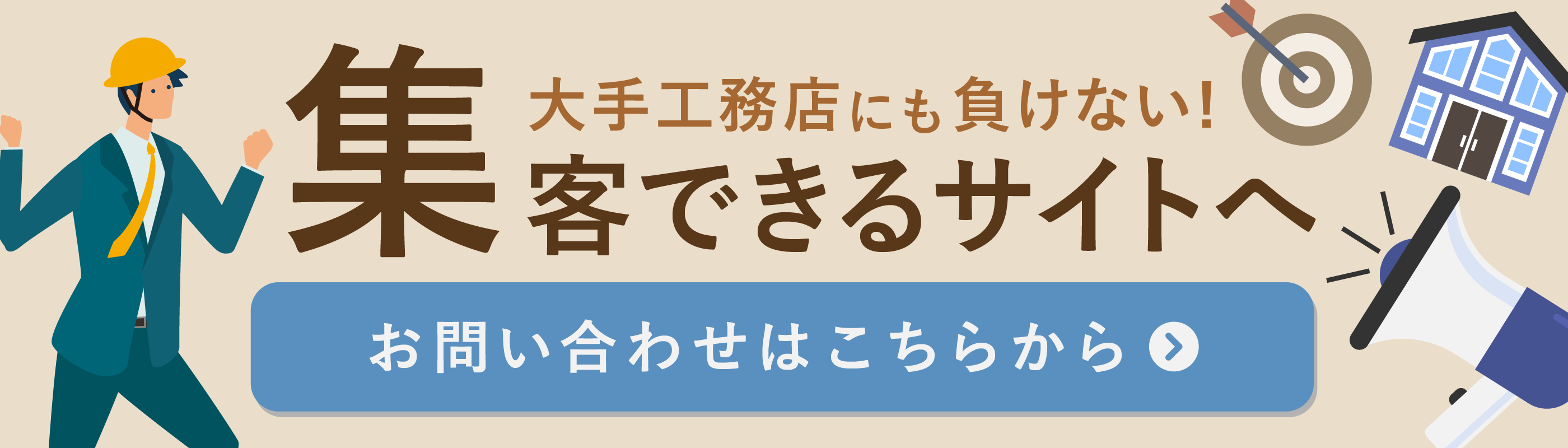
目次

建設業がDXを実践するにあたり、「どのような効果があるの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。この項目では、代表的なメリット3つをわかりやすく解説します。
1つ目のメリットは、業務の生産性向上です。
例えば、建設DXの一環である「施工管理アプリ」を導入すれば、工事関係者との段取りの行き違いなどが生じにくくなるでしょう。
さらに遠隔臨場などを活用すれば、現場に行かなくても立ち合いができるようになり、移動時間を減らせます。このようにさまざまな工程・時間を大幅に削減できるため、現場運営の生産性が大きく高まるでしょう。
2つ目のメリットは、人手不足の解消です。
DXによって効率化を図れば「長時間労働が改善される」「ドローンや自動制御の導入により、現場の負担が軽減される」といった効果が見込めます。
その結果、労働環境が良くなっていき、建設業界特有である“3K(きつい・汚い・危険)”といった状況を改善しやすくなります。そうなると、若年層に関心を寄せてもらえる機会が増え、最終的には人材不足の解消につながっていくでしょう。
3つ目のメリットは、ノウハウの継承です。
建設業は高齢化問題を抱えており、熟練した技術を持った職人が年齢により引退せざるを得ません。そのため「継承先となる中間層・若手が十分に揃っていない」という事態が進み、技術の継承が困難になっている企業も少なくありません。
そこで建設DXを導入すれば、上記のようなアクションを実行できるようになります。“若手でも短期間で技術を習得できる”という流れを作り出せるため、熟練技術者のノウハウ継承に大きく役立つでしょう。
建設業の経営・集客・営業ノウハウを詳しくまとめた記事があります。
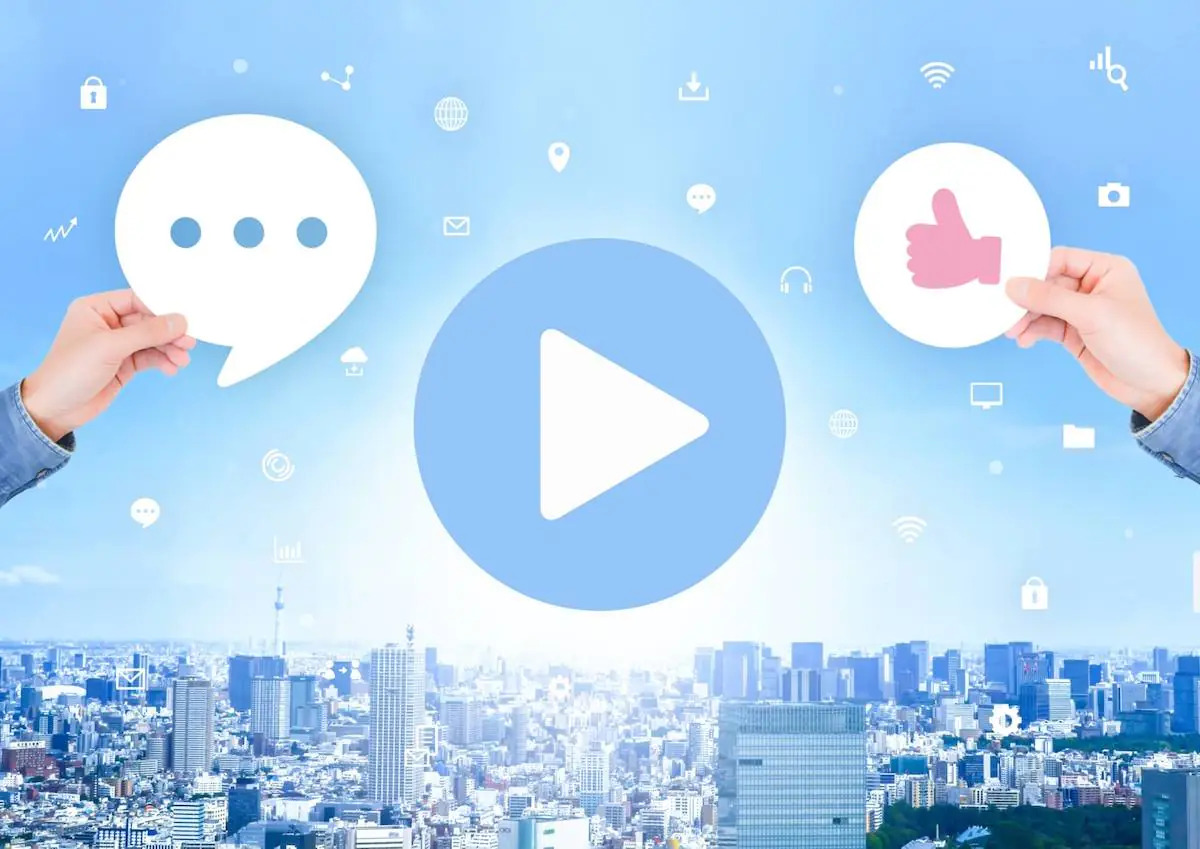
ここからは、建設業のDX成功事例5選をそれぞれ紹介します。自社でDXを実践するにあたり、参考になる取り組みを厳選いたしました。ぜひ参考にしてください。
清水建設はゼネコンの中で唯一、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「DX銘柄2022」に選出。2021年に次いで、2年連続での受賞となりました。
同社は下記3つのコンセプトを、デジタル戦略の柱としています。
これらを実現する建設会社を「デジタルゼネコン」と定義し、目標に掲げています。またこの「デジタルゼネコン」という経営戦略を元に、組織づくり・人材育成・社内のデジタル化を促進している点が、DX銘柄選定にあたって高く評価されました。
さらに建物運用のDXをサポートする建物OS「DX-Core」の商品化も推進。当商品は“建築設備・IoT機器・各種アプリケーション同士の相互連携や制御をスムーズに行う”ソフトウェアです。「DX-Core」はすでに同社の自社施設である大規模賃貸オフィスビル「メブクス豊洲」をはじめ、東北支店新社屋・北陸支店新社屋へ実装されています。
今後は外部企業との協業により、さらに広い建物設備システムと連携できるハードウェア・アプリケーションを開発していく予定です。
2020年の「DX銘柄」に選定された実績を持つ、鹿島建設株式会社。大手ゼネコンの一つである同社は、AI・IoTといったデジタル技術を活用した「鹿島スマート生産ビジョン」を打ち出しています。
上記のコンセプトに基づき、このような取り組みを行っています。
作業の半分はロボットと
高度な判断や調整が生じる作業は、これまでと変わらず「人」が行う。対して、運搬をはじめとする付帯作業・連続作業は、鉄骨溶接ロボットなどの「ロボット」が担当。人・ロボットが持つ力をフルに引き出し、それぞれの得意分野を活かして稼働するビジョン。
管理の半分は遠隔で
人と人とのコミュニケーションは大切にしながらも、「現地での確認」×「遠隔での確認」を組み合わせることで、さらにスマートな現場管理を実現。また現場確認をする際は、「センシング技術(=センサーによる計測)」を用いて、人為的なミスを防いでいく。
全てのプロセスをデジタルに
設計・施工・維持管理の全工程をデジタル情報に落とし込み、管理。3次元モデル活用技術であるBIM・工程表・コストといった、さまざまなデータと連携を実施する。さらにVR技術も取り入れ、疑似的に体験しながら仕様決めを行うこともあるとのこと。
同社では「鹿島スマート生産ビジョン」によりDXを推進したことで、工期短縮・作業者の熱中症予防・施工時の手戻り防止といった効果を得られたそうです。今後も「課題である人手不足の解消」「より魅力的な建築生産プロセスの実現」に大きく貢献していくでしょう。
電気設備工事業を展開するダイダンは、経済産業省の「DX認定取得事業者」に選定されています。同社はこれまでにi-Constructionの促進に力を入れ、建設現場におけるデジタル技術の活用を目指してきました。
特に評価されている取り組みとして、下記の2つが挙げられます。
現場支援リモートチーム
全国各地の現場に対し、本社・支店から効率的にサポートできるよう編成されたチーム。「Web会議ツール」「クラウド上のファイルサーバー」「共通CADソフト」を活用し、図面作成・工程管理などを遠隔からサポートする。経験年数が短い若手社員や時短勤務を希望する技術者など、多彩な人材が活躍できる点がメリットといえる。
REMOVIS(リモビス)
設備の稼働状況・エネルギー消費状況などを、遠隔で監視できるシステム。クラウド上で制御・監視機能が稼働しているため、幅広いIoTデバイスとも連携OK。さらに遠隔監視のため、エンジニアが現地へ出向く機会を減らせる。移動時間の短縮につながり、生産性向上に非常に役立っている。
また同システムは社内での活用だけに留まらず、他社へもサブスクリプションサービスとして提供されているとのこと。さまざまな現場で活躍しており、設備管理の悩みを解決するツールとして認知度が高まってきています。
戸田建設では「有用なデータを収集・蓄積し、サービス提供のためのプラットフォームを構築すること」「ほかのエコシステムと連携し、事業領域を拡大・深化させること」の実現を目指し、積極的に事業革新に取り組んでいます。
またDXの実現に向け、“導入→展開→創造→常態”の4ステップのアクションに分け、上記のロードマップを作成しているそうです。
株式会社奥村組は、メガネ型のデバイスにさまざまな機能を搭載した「スマートグラス」を活用し、遠隔臨場(=遠隔での現場立ち合い)の取り組みを実施しています。
同社が導入したのは、「V-CUBEコラボレーション」というもの。音声認識型のスマートグラス・会議システムが一体化した、遠隔臨場ツールとなります。
現場での使用に関しては、現場・事務所・発注者の監督官を会議システムでつなぎ、現場のスマートグラスの映像を共有していく流れとなります。さらに会議の進行に支障が出ないよう、ノイズキャンセリング機能も搭載。多くの重機が動く現場においても、クリアに音声が聞き取れるようになっている点が特徴です。
また遠隔で確認箇所等を書き込むと、スマートグラス上に表示されるため、現場に担当者がいなくても円滑に作業を行えるようになります。
結果的に、同社は「スマートグラス」を取り入れたことで、移動時間などのコスト削減に成功しています。今後は熟練した職員による技術指導等への活用も進んでいく見通しです。
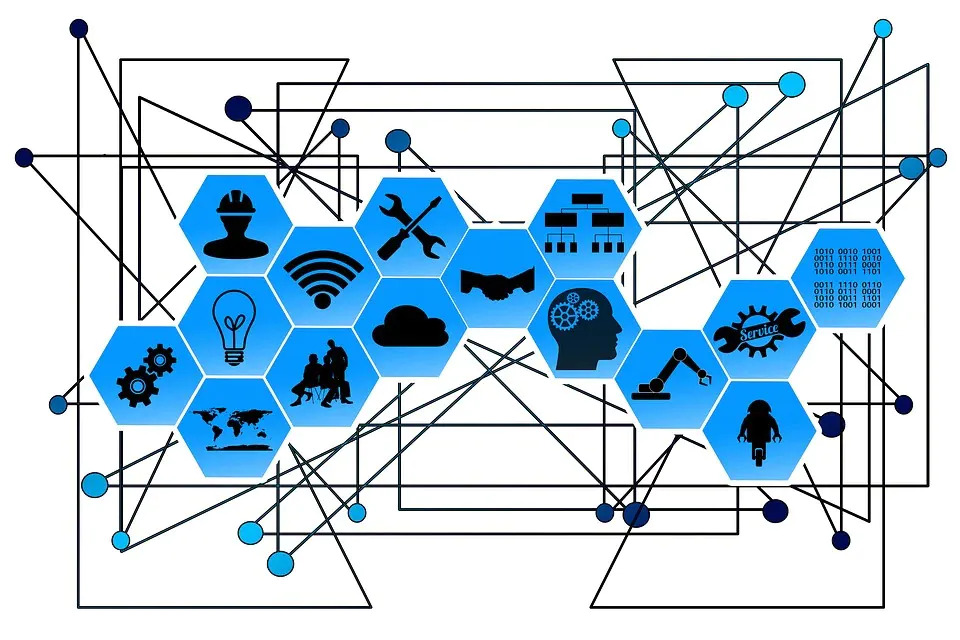
自社でDXに取り組むうえで、欠かせないものが「ITツール」です。
ITツールには“現場と管理部門との連携がスムーズになる・専門技術や煩雑な仕事を効率化できる”といったメリットがあり、自社のDX推進に役立つ可能性が高いです。
この項目では、建設業におすすめの業務効率化ツール・管理アプリなどを紹介します。
https://www.any-one.jp/it_hojyo?_ebx=4m6jwdfdq.1628218508.7p4jj8d
業務一元化のためのオールインワン基幹システムである、「AnyONE」。2021年までの実績で6年連続支援事業者に選ばれており、採択率は92.2%と非常に人気があります。
当ツールは建設業の中小企業・小規模事業者に必要な業務をほとんど網羅しており、基本機能が非常に充実している点が特徴です。
また「AnyONE」で行えることとして、下記のようなものがあります。
このように、対応している業務は多岐にわたります。「集客業務」「営業業務」「経理・粗利」といったさまざまな課題を解決し、企業全体の効率化を支援してくれるでしょう。
「ダンドリワーク」は工務店・リフォーム会社に特化した、コミュニケーション一元化システムです。
当ツールは“建築現場の効率と品質は段取りで8割決まる”という考えのもと、建築業界の業務改善に役立つ機能が数多く搭載されています。また建築現場経験者により開発されたこともあり、きめ細やかな運用・サポートが多くの企業から好評を得ているそうです。
「ダンドリワーク」の特徴として、下記のようなものが挙げられます。
また基本的な機能として、次のようなものが搭載されています。
さらに「工程表」「入出金・発注・請求」などの複数機能については、オプションにて追加可能。自社の状況に応じて、機能を自在にカスタマイズできる点が魅力です。
「現場管理をより円滑に行いたい」という建設会社は、こちらのツールをぜひチェックしてみてください。
建設DXを促進させるには、ホームページが欠かせません。なぜなら、自社のホームページを運用することで、集客面・採用面において生産性が大きく向上するため。
その具体的な理由として、下記の2つが挙げられます。
集客の自動化を実現できる
ホームページ運用によって、集客の自動化が可能です。なぜなら、ホームページは自社メディアとして、サービスの紹介や申し込みフォームを設置することで、“24時間365日”見込み客に自社を宣伝する営業ツールになるため。
自社サイトをGoogle・Yahoo!JAPANなどで検索された際に上位表示させたり、SNSで露出を増やしたりすれば、多くのユーザーに認知してもらえる機会を増やせます。結果的に自動的に多くのお客さまを集客できるでしょう。
人材確保にも効果的
ホームページ運用は、自社の人材確保にも適しているでしょう。
現在多くの求人活動は、インターネットを通じて行われています。そのため「自分に合う会社を探している」「業界に興味がある」求職者が企業の情報を知り、応募するかどうかを判断する一番の材料がホームページといえるでしょう。
したがって求職者が求める情報をしっかり掲載することで、他社よりも優位に立てるため、優秀な人材の獲得につながります。
このようにホームページを運用すれば、集客面・採用面ともに大きなメリットがあります。
自社のDX化を促進させ、より働きやすい環境をつくりあげるためにも、ホームページ運用をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
建設業の経営でWebを活用すべき理由を説明します。ぜひご覧ください。
当社は建設業界のホームページ制作を数多く手がけてきました。これまでの実績はこちらから。

建設DXに取り組み、成果を出すためには押さえるべきコツがあります。続いて、建設業のDXを成功させるポイント3つを詳しく見ていきましょう。
建設DXを導入するにあたり、まずは経営陣・現場との認識を擦り合わせ、ギャップをなくせるよう努めましょう。
最新のデジタル技術を建設現場が受け入れるためには、何らかの課題が生じる可能性が高いです。なぜなら、アナログ文化が強く根付いている業界ということもあり、「DX導入は絶対に受け入れられない」と職人から強い反発が起きるケースも非常に多いため。
そのため、経営陣は「なぜ導入するのか」「どのような方法で使うのか」などを、根気強く現場スタッフに説明しましょう。
いくら利便性が高いとは言え、現場スタッフが「課題を解決するのは難しい」「うまく使いこなせない」と感じるようであれば、DX化は一向に進みません。
したがって「生産性向上に貢献できる」「スピーディーにノウハウを継承できる」などの、“アナログにはない強み”を伝え、全員にしっかりと納得してもらうことが大切です。
働き方改革の実現に向けて、アクションを起こすことも重要でしょう。なぜなら、2024年4月から、改正労働基準法第36条の5項である「時間外労働の上限」が建設業界にも適用されるためです。
これまで建設業の特殊な業務内容から期間に猶予が与えられていたものの、将来的には労働時間の上限を厳密に管理しなくてはならなくなります。そして、もし当法律を守れない場合は、社名の公表や刑事罰の対象になるとのことです。
そのため建設DXを導入し、2024年4月までに働き方改革の実現を目指すと良いでしょう。
建設DXは1つの技術を導入しただけでは、決して成功できるものではありません。最先端の技術・手法を複数取り入れ、それらをコラボレーションさせることで、最大限の効果を引き出すことができます。
また、建設DXには「ICT」「AI」などの多彩な技術が用いられますが、それぞれが持つ特性や得られる効果は大きく異なります。
そのため“どのような場面で、どの技術を取り入れるべきなのか”という知識・ノウハウを習得し、自社の状況に応じて臨機応変に実践していくことが重要です。
建設DXに用いられる技術などを詳しく解説した記事があります。ぜひご覧ください。

前項目にて「建設DXの技術によって、特性・効果が異なること」「専門的な知識・ノウハウの習得が必須であること」などをお伝えしました。
ですが、“最先端のデジタル技術を駆使したうえで、DXを導入できる人材がいる”という企業は、非常に限られているかと思います。
そのため「DXに取り組みたい」と考えている場合は、プロへの依頼がおすすめです。建設業の支援実績のあるWeb会社であれば、自社が解決すべき課題を見つけ、ベストな方法を提案してくれます。
TRASPは建設業界でのサイト制作・Web集客の実績を多数保有しています。また、ターゲットユーザーを細かく分析した“集客につながるホームページ”が強みです。専門知識・ノウハウを培ったプロが、お客さまに適したプランニングをご提案いたしますので「IT・DXに関するスキルに自信がない」という方でも丁寧にサポートいたします!詳細はこちらをご覧ください。
この記事では、建設DXの成功事例5選をピックアップしました。初心者向けにおすすめのツールも紹介しましたが、いかがでしたか?
建設DXによって、業務の生産性向上・人手不足の解消・ノウハウの継承といったメリットが得られます。紹介した事例を参考に「現場とのギャップをなくす」「複数の手法を活用する」などを意識し、自社に合うDXを実践しましょう。
DXの第一歩としてWeb集客がおすすめ。気になる方はホームページ制作会社をはじめ、専門のプロへ相談すると良いでしょう。
TRASPではホームページ制作をとおした集客支援によって、業務のデジタル化や採用の強化など、複数の成果を出した事例もあります。利益に直結する最重要項目のため、Web集客のプロにお任せください。