解体業

富山県の解体業のホームページデザイン15選!・・・
2023.02.06
TRASPコラム
解体業
更新日:2023.03.25
公開日:2022.05.18
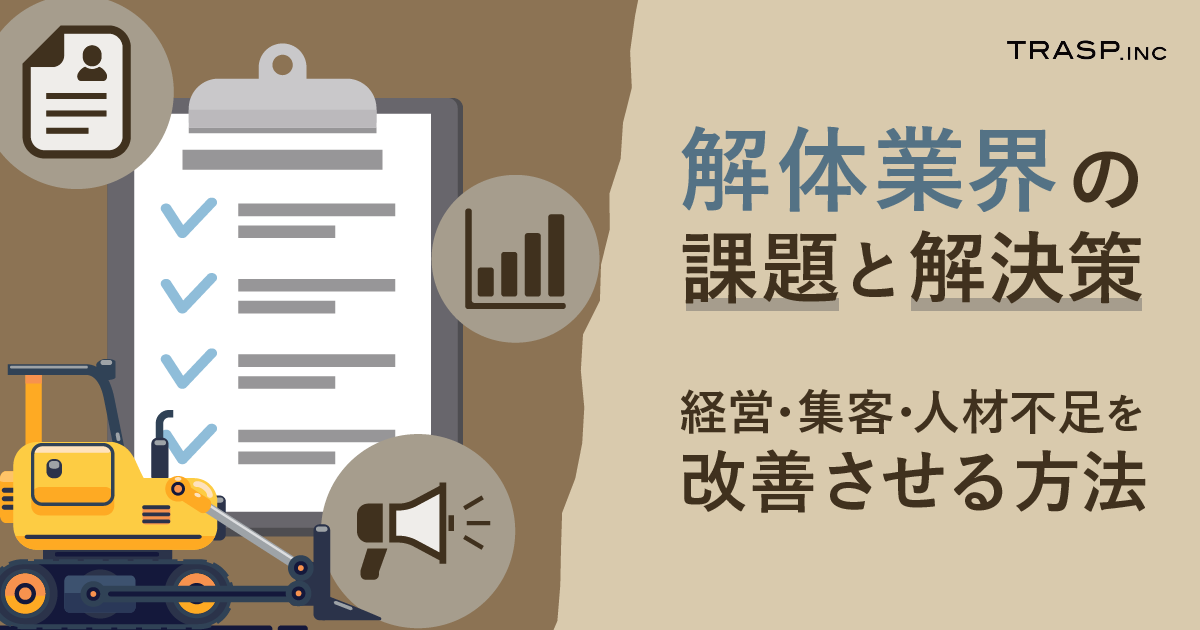
解体業に携わっている方は、コロナ禍やアスベスト対応の影響で
「人が足りなくて業務がまわせない…」
「問い合わせがパッタリとなくなってしまった」
といった悩みを感じている方も多いのではないでしょうか?
解体業界は実にさまざまな面で課題を抱えています。自社に複数の問題が重なると、どれから手をつければ良いのかわからない状態になってしまいますね。
そこで本記事では解体業界の課題4つと具体的な解決方法をまとめてみました。
さらに、多くの解体業者をWebで支援してきたTRASPが、個々の企業の課題についても「経営」「集客」「採用」「業務」の観点から考察し、解決案を提案いたします。

目次

まずは解体業界で考えられる4つの課題と、解決方法について解説していきます。
産廃処理とは、廃油やゴムくずなど事業によって排出されたゴミの処分を指し、日本では廃棄物処理法によって関わる事業者の責務が細かく規定されています。
従来は海外へ輸出することもできましたが、2017年末に中国で廃プラスチックの輸入制限が始まったことで、日本国内で処理を行う必要性が高まりました。
しかし近年の災害の影響によって廃処理場が不足し、最終処分場の残余年数は約20年と土地の確保が問題視されています。また最終処分場は環境汚染が心配され、簡単には増やせないのが現状です。
解決方法
解体・建設業はリーマンショックによって需要が激減し、それ以降「職人離れ」が加速しています。
特に近年では若年層の建設業在職者が減少傾向となり、現場職人や後継者不足が大きな課題といえるでしょう。
実際に解体業者を対象にした調査を確認すると、
引用:株式会社クラッソーネ
産業処理不足に次いで、人材不足を問題視している企業の多さがわかります。
労働力を確保できなければ安定した経営から遠ざかるため、人材不足は早急な対応が求められます。
解決方法
具体的には後述の「解体業界の課題解決に必要なこと【採用】」で解説します。
令和4年4月1日以降は以下の解体工事を行う際、元請業者等がアスベスト調査結果を都道府県等へ報告することが義務付けられました。
しかしアスベスト調査にかかるコストや対応が遅い業者が多いなど、解体業界ではさまざまな面で課題となっています。アスベストは人体への有害性が問題視されているため、適切な方法で対処しなければ重大な問題につながってしまうでしょう。
解決方法
解体業界ではコロナウイルスの影響によって工事の依頼が減少し、従来より集客が難しい状態となっています。
そのため取引先に頼るのではなく、自社の力で集客をすすめていくことが重要です。
またオンライン化が加速したことで解体業でもインターネットの活用が必須となり、日々の業務や営業活動でデジタル化を考えなければいけません。
解決方法
TRASPではお客さまの事業内容やターゲットを把握したうえで、集客につながる戦略的なホームページを制作しています。実際に「以前よりも問い合わせ件数が増えた」という声も多数いただいています。まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら

ここからは、個々の企業課題について解説していきます。
まず解体業の経営課題として挙げられることは、「元請け構造」や「顧客のニーズに合致していないこと」です。そのため以下の点を意識し、課題解決に取り組みましょう。
解体業が経営の安定化を目指す際は、まず自社が元請けとなる仕事を獲得しましょう。
建設業全体をとおして下請けのみで成り立っている企業はたくさんあります。
しかし下請けの状態ではコロナ禍などの不景気になると、元請けの経営状況に左右されやすく、仕事が急に打ち切られてしまうといったリスクがつきものです。
また元請けとの契約を一度結べば、あとから自社で取引条件を変更できません。
そのため工事の遅れが生じれば時間外や休日に作業を行う場合もあり、発生した追加費用は自社で負担する必要があります。
このように下請けはさまざまなデメリットがあるため、早急に改善し経営課題を解決していきましょう。
解体業の営業方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
根本的な経営課題の解決には、自社の強みを明確化し現状をしっかりと把握することが求められます。
なぜなら経営で失敗する例として、顧客のニーズに沿った訴求を行えていないケースが挙げられるからです。
現在のようにインターネットが一般化した時代では、世の中には数え切れないほどのサービス・商品であふれています。そのため顧客のニーズも多様化し、マッチしないサービス・商品では選んでもらえません。
しかし裏を返せば、ニーズを深く考えることで競合よりも魅力的なサービスを提供でき、自社で独占することも可能です。したがって顧客のニーズに当てはめるためにも、まずは自社について丁寧に分析することが重要になります。
マーケティングの分析方法や解体業の経営課題についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

解体業の集客では、オンライン集客を実施できていないことや、適切な方法で取り組めていないことが課題といえるでしょう。そのため以下の3ステップを意識し、課題解決に取り組みましょう。
集客に取り組む際は、3C分析を用いて「顧客・競合・自社」の分析から行いましょう。
具体的には、各項目で以下の内容を分析していきます。
顧客(Customer)
競合(Competitor)
自社(Company)
普段からセールスポイントやマーケティング施策を考えている方もいらっしゃいますが、どうしても表面上の分析になりがちです。そのため上記のように客観的に分析することで、具体的な課題定義と戦略立案が可能になります。
3C分析についてわかりやすく解説した記事がありますので参考にしてください。
現状分析を行ったあとは、顧客のニーズを判断したうえでWebサイトの運用を行いましょう。
Webサイトは「企業の顔」であり、自社を知ってもらうには欠かせないツールです。
例えば戸建て住宅の解体工事を行う場合、顧客は依頼前に以下の要素を知りたいと考えています。
特に現代では大半の顧客がGoogleやYahoo! JAPANの検索エンジンでリサーチするため、Webサイトがなければ企業情報を知れず選択肢から外れてしまうでしょう。
またWebサイトであれば自社の専門性や強みをアピールでき、競合との差別化を図れます。
したがってWebサイトを活用する際は、「顧客が求めている情報」と「競合との差別ポイント」を意識することが集客成功につながるポイントです。
Webサイトの集客効果を最大化するためには、継続してコンテンツを更新し、アクセス数を増やす必要があります。
ただし更新するコンテンツは、自社の見込み顧客に向けた記事であることが重要です。
仮に戸建て住宅の解体工事をメインで扱っているのであれば、ビルやマンションの解体工事を目的として顧客にアプローチしても意味がありません。
そのため、
など、自社の明確なターゲットがいるキーワードを対策しましょう。
解体業のホームページ集客、ブログについてまとめた記事があります。

解体業の人材不足課題では、求職者が魅力を感じていないことや、そもそも解体業を認知されていないことが挙げられます。そのため以下の点を意識し、課題解決に取り組みましょう。
まずは多くの求人募集を集めるために、働きやすい環境を整えることが重要です。
例えば解体・建設業界では災害対応やインフラ整備など重要な役割となり、ほかの業界と比べて長時間労働を強いられるケースが多いといえるでしょう。
そのため他業界と比べて残業時間も多く、週休2日制を採用できていない状況になります。
また長時間労働の割に給与面でも決して高いわけではありません。
このような待遇では応募者を獲得できないため、労働環境でメリットを感じさせるように改善していきましょう。
人材不足を解消するためには、日本人だけでなく外国人労働者への対応も視野に入れましょう。
なぜなら日本国内では少子化の影響もあり、将来的にも採用難の状態が続くと考えられるからです。
また外国人労働者であれば海外展開などにもつながるため、企業として事業の幅を広げる際も役立ちます。
しかし外国人労働者を雇用する際は日本人とは異なる法律が適用されるため、新たに労働環境を整える点には注意をしましょう。
解体業で言われている3K(きつい・汚い・危険)を改善するには、いままでにはない「働きたい」と感じるようなイメージアップを行う必要があります。
例えば、Webサイトにプロモーション動画や働いている先輩スタッフのスケジュールを掲載するなど、具体的な仕事の様子を発信することが効果的な方法です。
また施工現場の見学会を開催することで、目に見えて解体業の良さを感じるきっかけにもなるでしょう。
特に若年層は「解体業を知らない…」という人が大半のため、積極的に「働く良さ」や「やりがい」をアピールすることが重要です。

解体業界はもともとデジタル化が遅れており、昔ながらのアナログ的な考えが一般化しています。
しかし人材不足といった問題を抱えるなかでは早急にデジタル化を行い、業務や現場作業での効率化を図ることが重要です。
「連絡はすべて電話で行う」や「紙媒体で請求書を管理する」など、昔ながらの方法は業務効率を悪化させている原因かもしれません。特に人材不足に悩んでいる場合は効率性を意識する必要があるため、いまある業務を少しずつデジタル化することが重要です。
例えば顧客管理を行う場合、担当の営業スタッフが状況を逐一把握していたのが従来の方法です。
しかしデジタル化をすればオンライン上でデータを共有でき、担当者でなくても状況を把握できます。
また現状では大半の解体業者がデジタル化を行っていないため、他社との差別化を図るうえでも有効です。
業務効率化ツールを紹介した記事がありますので、参考にしてください。
工事現場では常に事故や怪我のリスクを抱えているため、AIやドローンを活用することで従業員への危険を未然に防ぐことが可能になります。
企業としても現場職人は簡単に替えがきかず、不慮の事故によって人員が減る事態はなんとしても避けるべき要素です。
またAIなどのテクノロジー技術は人間よりも精度や速度の向上につながり、作業全体の効率化が図れます。
顧客へのアピールポイントにもなるため、新しい自社の強みとしても導入をおすすめします。
本記事では解体業界の課題を4つピックアップし、具体的な解決方法を解説してきました。
一見、人材不足や受注件数の減少など複数の課題に頭を悩ませてしまいますが、根本的な解決案はインターネットの活用やオンライン化など、同様の対策であることが多いです。
特に経営と集客面は「自社の集客力」に集約されるため、まずは自社のWebサイトを運用し、積極的に情報発信を行っていきましょう。
TRASPではホームページ制作からマーケティングの支援まで一貫して行っております。
お客さまごとに現状の課題をヒアリングし最適な戦略を提案しておりますので、集客面はぜひプロへお任せください!
