工務店
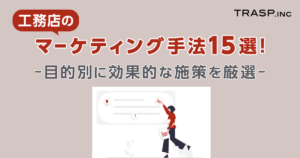
工務店のマーケティング手法15選!具体的な戦・・・
2022.04.14
TRASPコラム
工務店
更新日:2023.03.26
公開日:2022.04.21
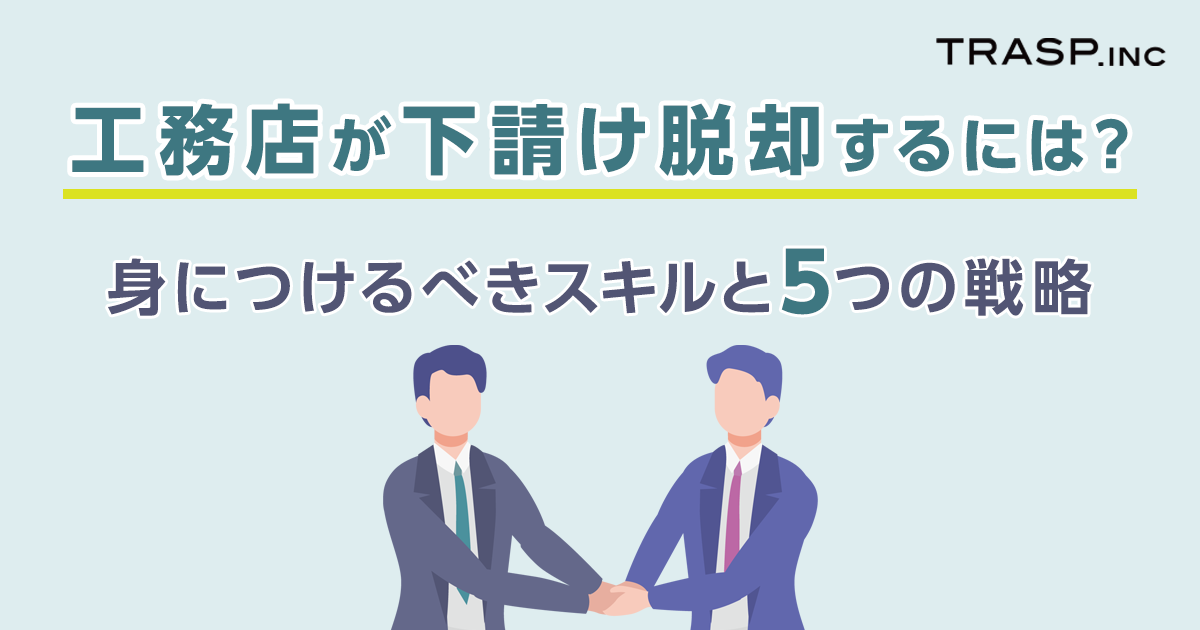
工務店や建設業界では、元請けから下請けへと発注する「重層下請構造」が一般的です。
しかし下請けのままで利益の高い仕事が少なく、「いつまで経っても売上が増えない…」と悩まれている工務店も多いのではないでしょうか?
このような下請けの状態を脱却し安定した経営を行うためには、元請けになって仕事を受注することが重要です。
そこで本記事では、工務店が下請けに依存することの問題点をピックアップし、「脱却するための5つの戦略」や「身につけるべきスキル」を考えてみました。
Webマーケティングによって工務店の集客課題を解決してきたTRASPが、下請けの脱却に欠かせない集客方法についても紹介していきます。
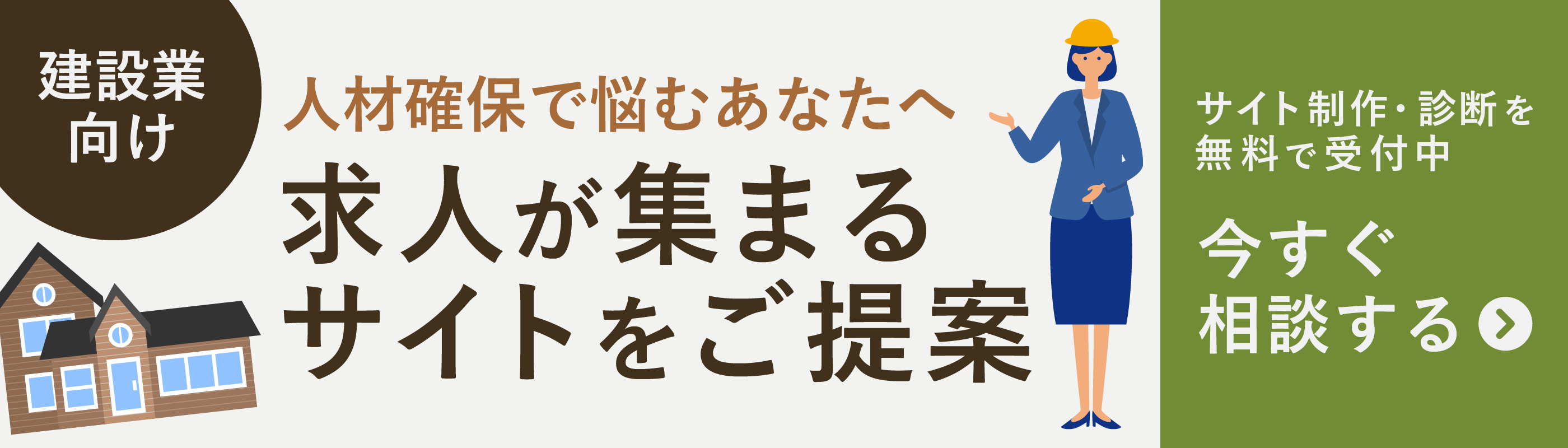
目次

工務店や建設業界は請負契約が一般的化しており、元請け業者が下請け業者に依頼する「重層下請構造」となっています。具体的な階層はこちら。
ゼネコンと呼ばれる企業が国や民間企業から工事を受注し、契約を結んだ下請け業者に仕事を発注する流れです。
基本的には二次下請け、三次下請けと下層になるにつれ、得られる利益は少なくなります。
このような構造は古くから続いており、施工の責任や品質の不明確さなど、さまざまな点が問題視されてはいるものの明確な改善には至っていません。
また工務店にとっても重層下請構造は元請けに依存した状態となり、最悪共倒れをしてしまうといったリスクがあります。そのため安定した経営を行うには、徐々に下請け状態を脱却することが重要です。

下請け状態は、元請け業者次第で仕事の受注件数が決まります。
そのため元請け業者の業績が悪くなった場合には、仕事量が減少することや、最悪仕事がなくなってしまうリスクを考えなければいけません。
また仕事を受注できている場合でも、取引条件が変更できないことによる追加費用の支払いなど、下請けの負担となる要素もデメリットです。
ここでは、工務店が下請けを脱却すべき3つの理由について解説していきます。
下請けは元請けと契約を結ぶことによって仕事を受注します。
そのため契約内容は元請けが定めたものとなり、取引条件を簡単には変更できないことが大きなデメリットです。
例えば作業の追加費用が発生した場合は、元請け側が自社で負担しなければいけません。
特に工務店の場合は雨天などで作業日程が変更になることもあり、休日作業の賃金や機械のレンタル費用は大きな負担となるでしょう。
見積もりと大きく異なる場合でも取引条件が変更されることはないため、当初予定していた以上に費用が発生することを考えておく必要があります。
下請け状態での仕事量は元請け業者によって決まるため、仮に元請け業者の業績が悪くなれば、自社で受ける仕事量も減少してしまいます。そのため自社で仕事量の調整ができない点が下請けのデメリットです。
たしかに下請けであれば、自社で営業活動を行わなくても一定量の仕事を確保できるでしょう。
しかし裏を返せば元請け頼みの状態となり、急な仕事量の変動を常に考えておかなければいけません。
このような状態では安定した経営とはいえないため、仮に仕事量が減少したときでも対応できるような営業力が必須になります。
下請け状態の最大のデメリットは、突然仕事がなくなるリスクです。
前述のように仕事が減少する程度であれば良いですが、なかには急な打ち切りなどによって、仕事の発注が一切なくなってしまう可能性もあります。
ビジネスとして考える以上しかたがないことですが、どんなに自社の技術力が高い場合であっても、元請け側の都合によって否応なしに左右されるのはもったいないですよね。
もし仕事がなくなった場合、いままで自社で営業をおこなう機会がなかった企業であっても、一から新たな取引先を見つけるために営業活動を行う必要があります。そのため現状が自社で集客するノウハウをもっていない企業は、非常にハイリスクな状態であるといえるでしょう。

下請けを脱却するためには、まずは自社が仕事を依頼されしっかりとこなせるだけの技量が必要です。具体的には以下の要素となります。
まず1つ目の要素は、顧客をしっかりと満足させられる技術力です。
下請けから脱却するには、直接仕事を受注する必要があります。
工務店であれば消費者を相手にすることも多く、他社よりも優れた要素やしっかりと仕事を任せてもらえるだけの技術力を伝えなければいけません。
もちろん全体的な技術力の底上げは必要ですが、一般の消費者に職人の専門技術の高さを伝えることは容易ではありません。そこで自社の技術力をアピールするためには「自社ならではの強み」を持つことを意識しましょう。
例えば、
など自社が「ほかには負けない」というわかりやすい強みや魅力をもつことで、直接仕事を受注できる可能性が広がるでしょう。
2つ目の要素は、競合にはない自社独自の開発力です。
開発力とは良い商品を生み出すための能力となり、以下のような要素を指します。
自社で商品やサービスを開発する能力があれば、他社の下請けとして取り組む必要がなく、自社で直接仕事を提案できるようになります。また魅力的な商品は自社独自のブランドイメージを生み出せ、価格競争を回避できることも強みです。
開発力を磨くには時間がかかりますが自社の明確な強みにもなるため、長期スパンで考えながら注力していきましょう。
3つ目の要素は、自社で新規顧客を獲得できる集客力です。
どんなに技術力や開発力があっても、集客力がなければ仕事の獲得はできません。そのため下請けの脱却を図るうえではもっとも重要な要素といえるでしょう。
また集客の中でも重要視すべき施策は、ホームページの活用です。
なぜなら下請けではなく顧客と直接契約を行う場合、一般のお客さまは住宅を依頼する前に「信頼できる企業なのか」をかならず確認しようとします。このとき多くの人はまずインターネットを使って企業情報をチェックするでしょう。もし自社のホームページがなかったり、まったく更新されていなければ、お客さまの信頼は得られません。
工務店のホームページ成功事例をまとめた記事や、工務店におすすめのブログを活用した集客について解説した記事もありますので参考にしてください。

ここでは工務店が下請けを脱却するための戦略について、以下の5つから解説していきます。
根本的な部分となりますが、まずは社長や経営者層が下請けの脱却意識を持つことが重要です。
例えば、経営者が次のような考え方をしている場合は、新たな戦略や集客に挑戦する機会は生まれにくいといえます。
もちろん上記の考えを否定するわけではありませんが、下請けを脱却するには以下のように考えることが大切です。
社長や経営層の考え方次第で企業は大きく成長するため、現状維持ではなく新たなことに進んで取り組む意識を持ちましょう。
下請けでしか仕事を獲得できていない原因として、そもそも元請け業者を軸としたビジネスモデルであることが挙げられます。
根本的なビジネスモデルがズレていれば、どんなに仕事を獲得できても利益率を高められません。
そのためビジネスモデル全体を見直し、自社が元請けとなって経営できるような仕組みづくりを行ないましょう。
例えば新規住宅の建設からリフォーム業に変更するなど、いまある技術力を活かす方法はたくさんあります。
特に近年は新設住宅着工戸数が減少しており、新規住宅市場は厳しい状況下といえるでしょう。
そのためリフォーム業は需要が高く、今後工務店が生き抜いていく戦略としても効果的です。
リフォーム業界についてはこちらの記事をご覧ください。
いままで企業相手のBtoBであれば、消費者をターゲットにしたBtoCに変更するなど、ターゲットを変えることも下請け脱出のきっかけになります。
ただし異なるターゲットの場合は新たな商品が必要なこともあり、開発力が求められるケースもあるでしょう。
またターゲットは一度に変えるのではなく、試しながら徐々に移行していくことが重要です。そうすることで途中で変更することが容易で、利益が出そうになければ修正が行なえます。そのためターゲットの反応を見ながら提供する商品やサービスを定めていきましょう。
過去に施工したことのある既存顧客は、あいさつまわりやハガキでのフォローをすることで紹介を獲得できる可能性があります。紹介による顧客は直接仕事を受けられるため、元請けとして受注できる有効な手段です。
特にリフォームを行っている工務店であれば、過去のお客さまが新規顧客となるケースは十分に考えられます。
そのため既存顧客とは長期的な関係性を築き、定期的にフォローするようにしましょう。
工務店の営業について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください、
ターゲットやビジネスモデルを変更すると生産現場が混乱する可能性があるため、社内体制をしっかりと整えることが重要です。
例えば一度に取引先が増えた場合、いままで扱っていなかった商品などを管理することもあり、納期に間に合わないといった可能性も考えられます。
そのため取引数量を増やす際は確実に社内でまわせることを確認し、円滑な状態になってから本格的に受注をしましょう。

ここでは下請けの脱却に欠かせない集客方法について、以下の4つから解説していきます。
工務店の集客について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
下請けを脱却するうえでは、Webサイトの運用はまずはじめに取り組みましょう。
なぜならさまざまなターゲットに営業を行ない、見込み顧客を徐々に増やしていく過程でも、お客さまはインターネット上で自社サイトをチェックしています。
もし自社に興味を持って調べたものの何も情報を得られなければ、興味は薄れてしまうでしょう。
逆にWebサイトをとおして良い印象を持てば、そのまま問い合わせにつながりやすくなります。
このようにホームページは営業や集客の軸といえます。Webサイトさえあれば時間や場所を問わずに営業を行えるため、見込み顧客を成約につなげるためには欠かせない対策となります。
工務店のWebサイトはこちらを参考にしてください。
SNSの利用者層は工務店のメインターゲットとなる20〜30代が多く活用しており、集客を行う手段として非常に有効です。また工務店では施工事例の写真や動画はアピール材料として重要になりますが、ビジュアルで訴求できるSNSは相性が良いといえますので積極的に活用しましょう。
活用方法の例としては次のようなものがあります。
SNS単体でも認知拡大やファン獲得はできますが、Webサイトに誘導することでより詳細な情報を伝えることができ、見込み客の育成をうながせるでしょう。
工務店のSNS運用について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
Web広告は集客の即効性が高く、短期間で成果を得たい場合におすすめの方法です。
GoogleやYahoo! JAPANなど検索エンジンの検索結果に出稿する「リスティング広告」や、SNS媒体に出稿する「SNS広告」など、Web広告にはさまざまな種類があります。
どの広告においてもターゲティングを行えることが強みとなり、自社が求める顧客層に向けて広告を出稿できる仕組みです。
ただし広告掲載には費用がかかるため、継続して利用すると高額になることもあります。Webサイトへ誘導したあとのお問い合わせまでの導線作りや、SNSに登録してもらうなど「広告の先」を考えて事前に準備しておくことが必須となります。広告で集客したターゲットを離さない仕組みを整えてから、期間を定めて活用することをおすすめします。
Web広告について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
Webセミナーや展示会は、自社の認知を拡大する手段として有効です。
近年はコロナウイルスの影響もあり、オンライン上でセミナーや展示会を開催することが主流といえるでしょう。
そのためWebサイトやSNSをとおして開催の告知を行うことで、多くの見込み顧客を集められます。
またセミナーでは大人数を相手にし、その後の相談会や面談などで個人を相手にする流れによって、購買意欲の高いユーザーに絞ったアプローチも可能です。
カメラ越しの会話は距離も詰めやすいため、オンライン施策のなかでは成約率を高めやすい点も強みといえるでしょう。
本記事では、工務店が下請けであり続けることの問題点を分析し、脱却するための5つの戦略や身につけるべきスキルを紹介してきました。
下請けは売上が安定しないだけでなく、いつ仕事がなくなるかわからないといったリスクもあります。
そのため自社で集客力や技術力を身につけ、元請けとして仕事が獲得できる状態を目指しましょう。
TRASPは問い合わせにつながるホームページ制作を強みに、工務店の集客をサポートしてきた実績があります。
Web広告やSNS運用などのWebマーケティングも支援しておりますので、Webを活用した集客についてはぜひお任せください!
