ブランディング
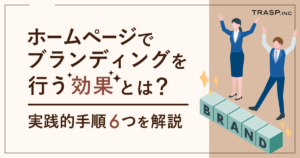
ホームページでブランディングを行う効果とは?・・・
2023.02.02
TRASPコラム
ブランディング
更新日:2023.03.21
公開日:2023.02.17
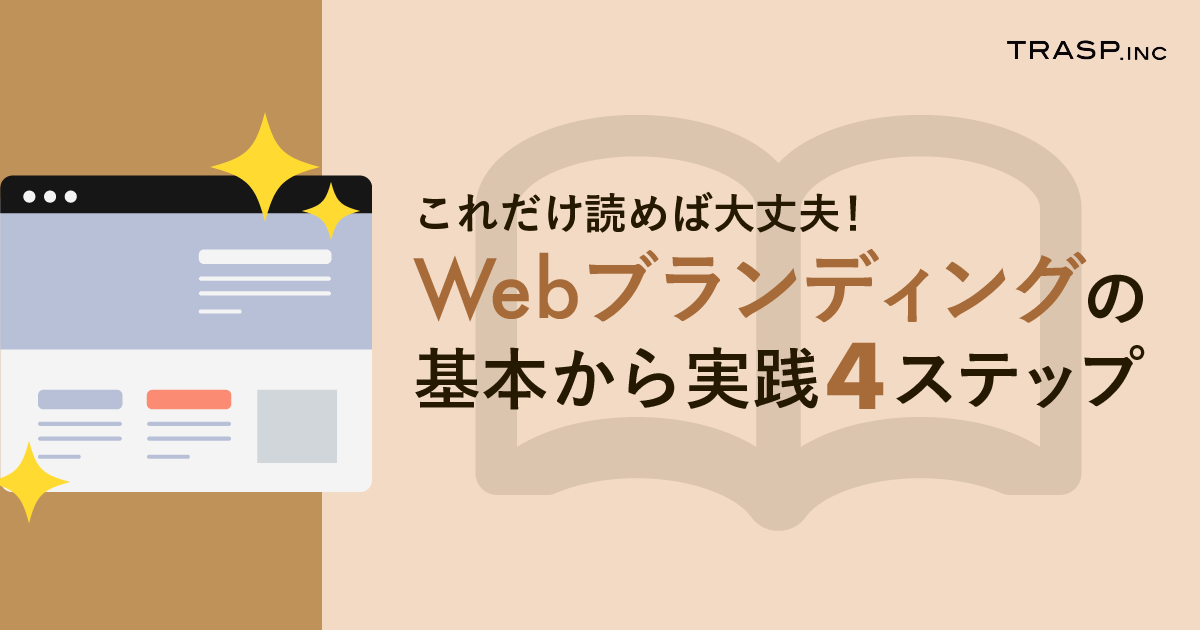
現代のように多くの企業・サービスがあふれている世の中では、かんたんに他社との差別化を図れません。そこでおすすめの方法が、ホームページを活用したWebブランディングです。
Webブランディングでは企業のイメージを打ち出すことで、最終的に顧客を「自社ファン」に育成できます。
など、Webブランディングについて詳しく知らない経営者やWeb担当者の方も多いでしょう。
そこで本記事では、Webブランディングの基本から、いますぐ実践できる具体的な手順についてまとめました。
Web集客で多くの企業を支援してきたTRASPが、Webブランディングの成功事例から「うまくいく要因」を分析し、競合と差をつけるブランディング戦略についてお教えします。
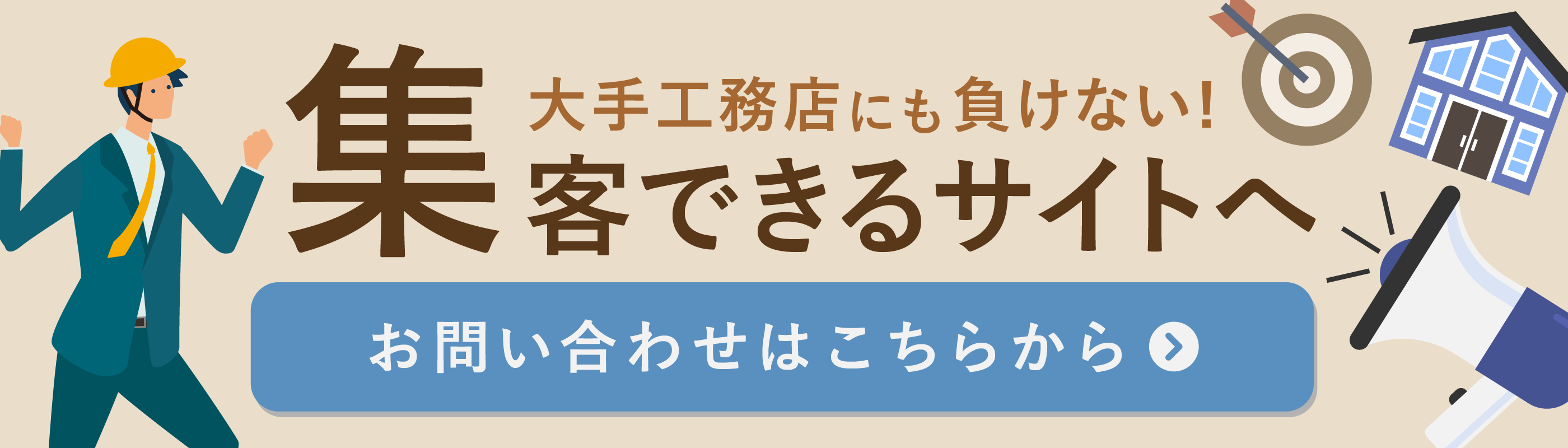
目次

Webブランディングとは、Webサイトを活用して企業やサービスのブランドを作ることです。Webサイト上で自社独自の世界観を表現することで、ユーザーへ新しいイメージを与えることや、信頼性を高めなどの「イメージづくり」が可能となります。
一般的なブランディングにおいても「イメージづくり」を行う点は共通ですが、Webブランディングでは「WebサイトをはじめとしたWeb上の施策」に特化している点が主な違いです。またブランディングと聞いて「マーケティングとは何が違うの?」と思われた方も多いはず。
両者の主な違いはこちら。
マーケティングではイメージだけに限らず、価格設定や販売経路の戦略設計など、売ることに特化している点が違いになります。そのためブランディングはイメージ戦略を重視した施策となり、マーケティング戦略の一つといえるでしょう。

つづいてWebブランディングの主な役割について、以下の3点から解説していきます。
Webブランディングをとおして自社の強みやコンセプトを表現できれば、企業の認知度を高められます。
認知度向上と聞くと「ただ企業名が有名になる」と考えてしまいますが、認知度と知名度は別物です。なぜなら認知度とは、企業名・サービス名がただ有名なのではなく、以下の観点から企業について詳しく知ってもらっている状態を指すからです。
企業名だけが先行しサービス内容について知られていなければ、お客さまを問い合わせにつなげられません。そのためWebブランディングをとおして、自社への理解を深めることが重要になります。
Webブランディングに取り組む際、発信する情報にストーリー性をもたせることで、自社ブランドに共感するユーザーを増やせます。
現代は業種をとわずに多くのモノが存在するため、ユーザーから選ばれるには「ブランドに対して良いイメージ」を持たせることが重要です。
例えば「ユーザーのこのような悩みを解決するために誕生した」「創業者のこのような想いがあって開発された」など、ストーリー性のあるWebブランディングがあると、自社ブランドへの共感力を高められます。
また共感できる企業やサービスは、自然と安心・信頼を感じやすくなるため、ユーザーが比較検討した際も選ばれやすくなるといったメリットが得られます。
Webブランディングをとおして認知度を高め自社に対する共感を集められれば、定期的に商品・サービスを購入してくれる自社ファンを増やせます。
企業の成長には売上を伸ばす必要がありますが、なかでも売上の安定化には自社ファンの獲得が必須。近年では月や年単位などの決まった期間で料金を支払う「サブスクリプションモデル」が注目されるなど、リピーター獲得は重要視されている施策の一つです。
Webブランディングでは表面的な興味に加え、ブランドに対するファン化ができます。そのためユーザーの定期的な購入、知人・友人の紹介など、自然な流れで売上が増加する仕組みを作れる点が最大の強みといえるでしょう。

ここではWebブランディングを行うメリットについて解説していきます。
1つ目のメリットは、Webブランディングによって自社ブランドのファンが増えれば、市場の価格競争を避けられることです。
仮に一つの市場内で同じサービス内容・サービス品質の商品が複数存在する場合、競合が値下げを行えば、自社も値下げを行わないと売れない状況になるケースは多いといえるでしょう。
しかし自社イメージを確立し、競合にはない付加価値を生み出せれば、他社に合わせて値下げを行う必要はありません。
とくに不景気のときこそブランディングの価値が発揮されるため、いま成長中の企業でもWebブランディングは共通して取り組むことをおすすめします。
2つ目のメリットは、経営を行うにあたって重要な「営業・採用活動」が行いやすくなることです。
自社の認知が向上すれば、顧客から商品を購入してくれることや、自社で働きたいと応募してくる求職者が増えます。そのため営業コスト・採用コストの削減ができるなど、コスト削減の面でも有効。
とくに営業時は「お客さまが自社を知っているか・知っていないか」によって、企業に対する信頼性から興味度までが大きく変化するといえるでしょう。
したがって日々の経営活動を円滑化するためにも、Webブランディングをとおした企業の認知度向上が重要になります。
3つ目のメリットは、顧客のリピート率を高めやすいことです。
一般的なブランディング施策の場合、顧客に向けたイメージ戦略や認知度向上という点では、Webブランディングと同じです。しかしWebブランディングではホームページを活用することで、ユーザーに顧客体験としての印象を与えられます。
例えばホームページをスクロールするたびに背景画像が変化する仕掛けや、ページを移動すると異なるテイストの表示形式になるなど、さまざまな方法で魅力を伝えられます。
ただ印象を強める広告とは異なり、顧客体験はユーザーの印象に残りやすい特徴があるため、最終的に自社のリピート率を高める要因となるでしょう。

Webブランディングを行う際は、まずは根本的なアイデアを出すために、以下の3つから考えていきましょう。
CI(コーポレート・アイデンティティ)
VI(ビジュアル・アイデンティティ)
BI(ブランド・アイデンティティ)
「創業からどのような過程を経てきたのか」「何を目的にいまの事業を行っているのか」など、いままでを振り返りながら将来的なビジョンを定めていくと、自社オリジナルのブランディングにつながります。
つづいて考えたアイデアをもとに、コンテンツへどのように反映させていくのかを考えましょう。
Webブランディングといっても、ホームページ、SNSなど施策内容は多種多様。なかでもWeb集客の軸として活用されるホームページは、Webブランディングにおいても欠かせない施策となります。
なぜならSNSや広告をとおして自社を知ったユーザーは、最終的に「自社名」や「サービス名」を検索し、ホームページへアクセスすることが多いからです。
ホームページ上のイメージ次第で問い合わせ率や購買率は変化するため、最初のブランディング施策ではホームページ制作から取り組むことをおすすめします。
戦略を立てた後は、実際にコンテンツを作成していきましょう。コンテンツ作成では、まず必要な項目をワイヤーフレームとして制作し、その後にユーザービリティを踏まえたうえでデザインへ反映させていくことが大切です。
またデザイン性はもちろんのこと、以下の点を考えながら作成する必要があります。
Webブランディングでは顧客体験が重要な要素となるため、求めるページへアクセスしやすいなど、ユーザー目線の操作性も重要視しましょう。
コンテンツを公開した後は「実際にどのような反応を得られているのか」「定めたイメージを浸透できているのか」など、効果検証を繰り返していきましょう。
ブランディング施策でよくある失敗例として、「自社のもつイメージとユーザーがもつイメージに乖離がある」ことが挙げられます。仮に何も検証をしなければ、間違ったイメージが広まる可能性もあるでしょう。
したがって表面的な数値だけではなく、実際に顧客の声を聞くことも重要な検証になります。
TRASPでは豊富なマーケティング実績をもとに、ユーザー目線で興味をもつホームページ制作を行っています。デザインや導線を一から設計しご提案していますので、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら

ここではWebブランディングの代表的な成功事例について解説していきます。
https://www.morinaga.co.jp/amazake/
森永甘酒は「酒粕×甘麹」の素材を強みに、「健康面で良い影響を与える甘酒」というブランディング戦略に成功した事例です。一般的に甘酒といえば、「年末年始やお祝い事のときに飲むもの」というイメージが定着化していました。
そこで森永甘酒では、ホームページ上で「酒粕×甘麹」のもつ栄養素や成分表を公開。また「体にあまく、体にやさしく」のキャッチコピー、鍋と一緒に食べられるお手軽感を与えることで、日常的な飲み物というイメージを上手に広めています。
さらにホームページでは赤と白をメインに活用しており、甘酒のカラーを視覚的にアピール。ユーザーに新たな気づきを与えている戦略は、多くの企業が参考になるポイントといえるでしょう。
https://www.redbull.com/jp-ja/energydrink
エナジードリンク市場で一躍有名になったレッドブルは、ブランディング戦略によってマーケティング力を発揮した成功事例です。
そもそもレッドブルを目にする前は、「エナジードリンク=栄養ドリンク」といったイメージが強く、大半は中高年の方が飲むドリンクでした。しかしレッドブルでは「クラブでのコンテスト開催」や「スポーツのスポンサー」を行うなど、若年層が興味をもつマーケティングを実施。
またホームページではスポーツのイベント情報やアスリートの紹介などを行っており、コンテンツとして魅力的な内容に仕上げています。このように若年層やスポーツに興味を持つ層など、いままでにはないターゲットへアプローチ点が、市場の拡大に成功した要因といえるでしょう。

最後にWebブランディングの成功に必要な要素について、以下の3点から解説していきます。
Webブランディングでは自社イメージを浸透させることが重要だが、あくまで最終的な目的は自社商品・サービスの購入を促すことです。
そのため表面的なデザインばかりにこだわるのではなく、コンテンツ内で「ユーザーに購買を促す導線」を組むことが重要になります。具体的には以下の3要素を作ることで、購買意欲を高めていきましょう。
またホームページであれば、TOPページから上記のコンテンツへアクセスできる設計が大切。そのため「初めての方はこちら。」など、ユーザーを誘導するような文言も効果的です。
Webブランディングではリピーターの獲得が重要といいましたが、そのためにはストーリー性のあるブランディング戦略が大切になります。
例えば「誕生までの秘話」や「直近でリリース予定の新商品情報」など、過去と未来がわかる内容を掲載することで、自社への興味を高められます。
とくに再訪問を促すうえでは、未来に関する情報提供が欠かせません。大規模なことでなくても「ユーザーが期待するような内容」を提供するだけで再訪問を促しやすくなるため、積極的に情報を公開していきましょう。
Webブランディングで最も重要な要素は、視覚的に興味をもたせる顧客体験です。
なぜならホームページへアクセスしてきたユーザーは、続きを読むか読まないかを「わずか3秒」で判断すると言われており、最初の視覚的アプローチ次第で成果が大きく変わるためです。
そのため自社のイメージカラーに沿ったデザイン性や商品・サービスを使用している様子の動画など、ファーストビューでインパクトを与える設計にしましょう。
自社のオリジナル性が高いほどユーザーへの印象が強くなるため、複数のファーストビューをテストすることもおすすめです。
本記事では、Webブランディングの基本から、いますぐ実践できる具体的な手順についてまとめました。
Webブランディングでは企業のコンセプトを打ち出したアイデアに加え、ホームページ内の顧客体験が重要です。そのためにはユーザー心理で考えられたホームページ設計・制作が欠かせないため、いま一度自社のホームページについて見直すことをおすすめします。
TRASPではホームページ制作を軸に、Webマーケティングを活用したブランディング戦略をご提案しています。お客さまの悩みや課題をヒアリングしたうえで、課題解決につながる戦略をご提案していますので、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら