マーケティングガイド
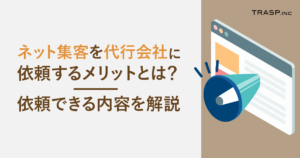
ネット集客を代行会社に依頼するメリットとは?・・・
2023.04.25
TRASPコラム
マーケティングガイド
更新日:2023.03.23
公開日:2021.11.26
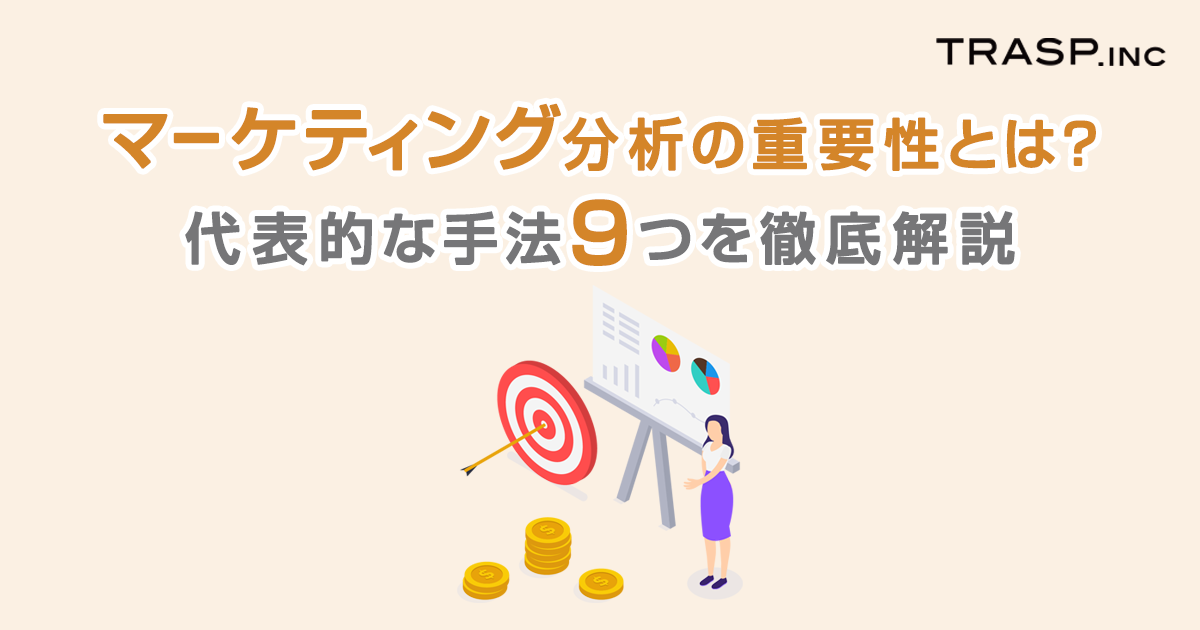
昨今のマーケティングといえば、Webサイトなどのインターネット上で実施される“デジタル・マーケティング”が主流になっていますが、そんなマーケティングに欠かせないのが、“分析”です。
ニーズが多様化している現代では、経験や勘だけに頼るマーケティングは通用しなくなっており、戦略を立てるためには、まず現状を”分析”しなければならないのです。「とはいっても、マーケティング分析は専門用語ばかりで難しい…」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、マーケティング事業を手がけているTRASPが、マーケティング分析で知っておきたい9つの代表的手法と、理解に役立つ重要用語を徹底解説!本記事を読めば、マーケティング分析の基本がわかります。

目次

マーケティング分析とは、会社が保有するデータを収集・管理・運用して、顧客一人ひとりのニーズを把握するための活動を指します。
マーケティング分析を行うことで、
ので、企業は利益の最大化を効率的に実現することができます。
マーケティング分析が重要視されるようになった背景として、次の2つの事柄があげられます。
顧客はインターネットで「知りたいものを調べられる」ようになり、同時にさまざまな種類の製品・サービスであふれた世の中になったため、顧客のニーズはどんどん多様化していきます。
つまり企業視点ではなく、顧客視点で一人ひとりのニーズに応えなければ、モノが売れない時代になったわけです。そして、顧客一人一人のニーズを把握するための方法として、さまざまなマーケティング分析のフレームワークが編み出されることになります。
時代の変化とともに、従来のマスマーケティングは、通用しなくなってしまったのです。「もっとマーケティングの歴史について詳しく知りたい!」という方はこちらの記事をご覧ください。

ここからは、マーケティング分析の手法として、よく用いられる重要フレームワーク9つをご紹介します。
まずは、「環境を分析する」ことを目的とした4つの手法から最初に見ていきましょう。
3C分析は、経営コンサルタントの大前研一氏が提案したもので、以下の3つの観点で環境を分析します。
大前研一氏は著書『The Mind of the strategist』において
「およそいかなる経営戦略の立案にあたっても、3者の主たるプレーヤーを考慮に入れなければならない。すなわち「当の企業=自社(Company)、顧客(Customer)、競合相手(Competitor)の3者である」」
と述べています。
3つの要素を検討することで、外部環境の市場・顧客・競合他社、と内部環境である自社を照らし合わせて、自社の強みと弱みを明確にすることができるのです。
Customerとは市場・顧客のことで、3C分析ではもっとも重要な部分です。ここでは、市場・顧客をマクロな視点から分析する「PEST分析」、ミクロな視点から分析する「ファイブフォース分析」の2つを使います。それぞれの方法についてはこの後、詳しく述べます。
2つの方法によって、顧客動向を精密に分析して、顧客や取引先の購買意欲や行動などを把握していきます。
Competitorとは、競合他社のことです。他社がどのような方法で市場の変化に対応しているのかは、自社の事業展開にとっても大きなヒントとなります。そのため、競合他社の視点での分析は欠かせません。
具体的には、
といった情報を調べます。
そして、
という2つの視点から分析を行いましょう。
Companyとは、自社のこと。CustomerやCompetitorの分析で外部環境を把握したら、次は「自社がどのような手を打つべきか」ということを具体的に検討していくわけですね。ここで重要なのは、「競合が市場の変化にどのように対応しているか」を自社と比較することです。
そうすれば、競合他社との差別化を図るための手がかりが見つかり、自社がどのような施策を行えばよいのかが明確になるでしょう。
またこの際、「自社の強みをどう活かすか」「自社の弱みをどう改善すればいいか」を探っていくSWOT分析(後述します)を用いることで、より意味のある分析結果が生まれます。
3CのCustomer(市場・顧客)を分析する際に、マクロの視点から調べていく方法がPEST分析でしたね。
マクロとは、企業がコントロールできない範囲にある事柄について検討することを意味します。例えば、景気変動・法律改正・人口分布・人口流動・社会的流行といった外部環境は、企業がどう頑張っても変えることのできないものですね。
しかし、世の中の動きをつかみ、客観的な視点で外部環境を把握することができれば、それらを予測できるようになり、結果的に企業の経営に活かすことが可能です。
その分析方法がPEST分析であり、PESTとは
の頭文字を表しています。
Politics(政治)
政治的状況や法律の改正などから分析を始める。法律規制の策定あるいは変更・撤廃は、事業に大きな影響を与えるからです。
Economy(経済)
経済成長率や株価、金利、消費動向などの将来における影響を予測することが大切。例えば、輸出・輸入を行う企業であれば、為替相場の変動を予測することは重要になります。
Society(社会)
社会構造やライフスタイルの変化についても分析が必要。例えば、日本で進んでいる少子高齢化社会は、高齢者向けの市場拡大・子ども向けの市場縮小を促しています。
Technology(技術)
急速に発達する技術的状況の分析も、重要です。技術開発の結果により、大きな市場が生まれる例はたくさんあり、技術の変化に敏感になることで大きなビジネスチャンスをモノにすることが可能に。
3CのCustomer(市場・顧客)をミクロに分析するのが、ファイブフォース分析でしたね。フォースとは「脅威」という意味なので、次の5つの脅威を分析することになります。
これらの外的、内的脅威を分析することで、自社を取り巻く業界構造を把握できます。
売り手の渉力による脅威
売り手が高い交渉力を持っている(市場を独占している)場合、買い手は高い価格を受け入れざるを得ないので、収益性が低くなる。
買い手の交渉力による脅威
買い手が高い交渉力を持っている(強力な購買力がある)場合には、売り手はギリギリの値引きを要求されるので、収益性が低くなる。
ファイブフォース分析は、新規参入のリサーチ方法としても有効で、既存事業から新規事業まで幅広く活用できる分析方法です。
SWOT分析は、自社の強み・弱みを知るための方法でしたね。
これら4つの要素の頭文字をとっており、プラス要因とマイナス要因をあぶり出すことで、自社の課題やリスクなどを可視化できます。
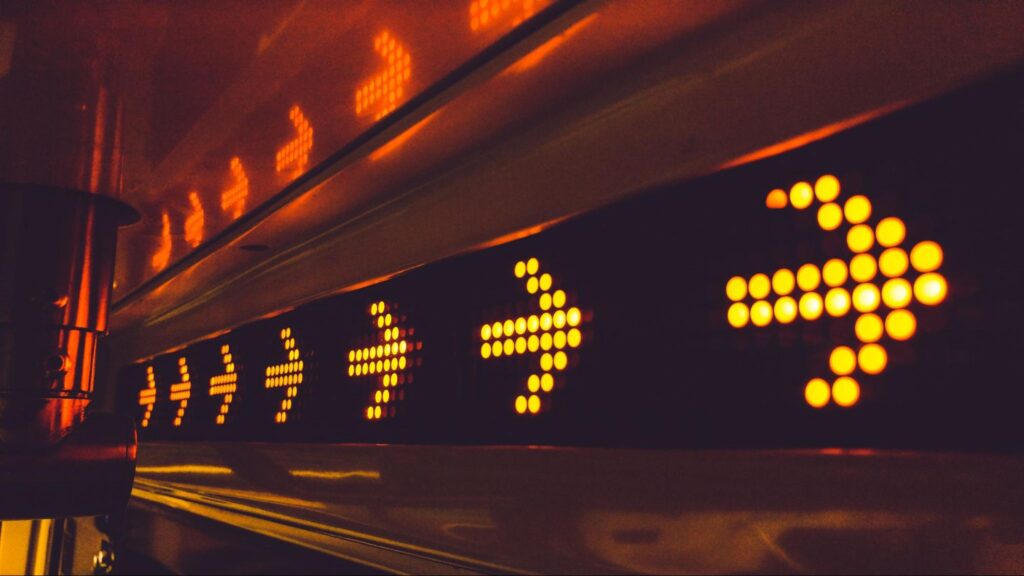
STP分析は、経営学者フィリップ・コトラーが定義したマーケティング手法で、次の3つを表しています。
3つに共通して重要なことは、ユーザーの行動を客観的に把握すること。
例えば、セグメンテーションでは、ユーザーの性別・年齢・住んでいる地域・物品の購入頻度といった特性によって市場全体を細かく分けます。
そして、ターゲティングでは細かく分けた市場の中から、どこを狙うのか決めます。最後のポジショニングでは、参入を決めた市場内における競合の商品・サービスを見て、自社の立ち位置を決めるのですね。
ポジショニングを行ううえで大切なことは、競合と比較する軸を持つこと。例えば、値段、品質、店舗数、販売チャネルなど、多くの指標の中から必要なものを選び、競合と比較しましょう。

4P分析とは、企業視点で、製品・サービスについて以下の4つの視点で考えることを指します。
Product(プロダクト:製品)
といった視点で、自社の製品やサービスについて決めていきます。
Price(プライス:価格)
適正な価格設定をするためには、競合他社の価格帯を考慮する方法と、しない方法の2つがあります。業種によって最適な方法は変わります。
Place(プレイス:流通)
商品・サービスをどうやって提供するか、流通経路を考えます。実店舗からネット通販まで多様な方法がありますが、製品のブランディングやユーザーの視点に立ち、確実に届けられる方法を探る必要があります。
Promotion(プロモーション:販売促進)
自社製品に対する認知を高めたり、製品に良いイメージを顧客に持ってもらうための方法を探ります。
4P分析(マーケティングミックス)について詳しく説明した記事がありますので、こちらをぜひご覧ください。
バリューチェーン(Value Chain)とは、事業活動で生み出される価値を、一つの流れとして捉える考え方です。つまり、「原材料の調達から、製品が顧客に届けられるまでの一連の活動をそれぞれ分析すること」と考えましょう。
製造業なら例えば、
といった工程・流れがありますね。それぞれを分析することで、どの工程で高い付加価値が生み出されているのか、またはどの工程に問題があるのかを明確に把握できます。
そしてこの分析結果を検討することにより、コスト削減を図ることができるメリットがあるほか、ターゲットとなる顧客に対してより高い価値を提供するには何をすれば良いのかも見えるようになるのです。
ファネル分析とは、簡潔に説明すると、「コンバージョン率をアップさせるための手法」のことです。コンバージョンとは、ユーザーが「商品を購入する」「サービスの申し込みをする」「資料の請求をする」といった企業にとっての成果のこと。
購買・申し込みに至るまでのユーザーの行動には、次のようなプロセスがあります。
ファネル分析では、購買行動のそれぞれのプロセスにおいて、コンバージョンに繋がった行動と、コンバージョンに至らなかった行動を分析。そして、購買行動プロセスのどこを改善するべきかを検討し、最適化することで、より高いコンバージョン率を得ていくわけですね。
RFM分析とは、顧客分析のために、顧客を次の3つの指標でグループ分けしていくマーケティング手法です。
Recency(直近いつ)>
Recencyは、顧客の購入データのうち、「購入日時」からその顧客が最後に商品を購入したのはいつかを抽出し、その時期によってグループ化します。何年も前に購入した顧客よりも、最終購入日が近い顧客のほうが「良い顧客」と考えます。
Frequency(頻度)
Frequencyは、購入頻度からグループ分けをするもので、購入頻度が高い顧客ほど「良い顧客」と考えます。この値から、新規顧客あるいは常連顧客の数がわかります。
Monetary(購入金額)
Monetaryは、購買履歴から購買金額の総額を計算して、グループ分けをするもので、金額が大きいほど「良い顧客」と考えます。
そして、RFM分析の最終目的は、各グループの性質に合わせたマーケティング施策を実行し、顧客がもたらす利益を最大化させること。グループ分けにより、それぞれの顧客のニーズに応えることができるので、施策の効果が高くなるわけですね。
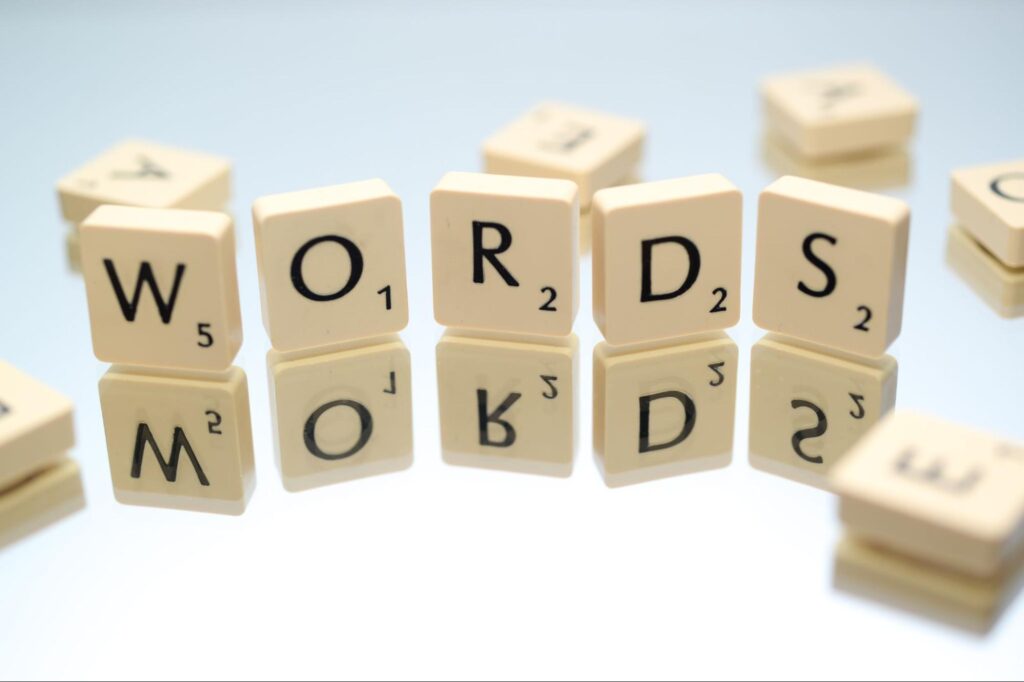
ここでは、マーケティング分析をより深く理解するのに役立つ用語を5つ紹介します。
AIDMA(アイドマ)は、購買に至るまでのユーザーの行動や考え方の変化を表したもので、次の5つのプロセスがあります。
さきほど紹介したファネル分析は、AIDMAに基づいて提唱された代表的なフレームワークで、そのほかさまざまなマーケティング分析手法にも取り入れられています。
また新聞、雑誌、ラジオ、テレビなど、マスメディアを使って不特定多数に向けて情報を発信するマスマーケティングと相性が良い考え方とされています。
AISAS(アイサス)は、時代の変化とともに通用しづらくなったAIDMAを再定義した概念で、次の5つのプロセスを指しています。
AIDMAとの最大の違いは、「顧客の積極性が加わっていること」です。IT技術の発達により、顧客自らがインターネットで情報を調べるようになったという時代の変化が、反映された概念と考えると良いでしょう。
SIPS(シップス)とは、SNSをよく利用するユーザーに特化した購買行動モデルのことで、
の頭文字をとったものです。
企業ではなくユーザーが情報拡散を担うことにより、信頼度が増して、共感が得やすくなるというSNSの特徴を反映させています。
ペルソナとは、サービスや製品を購入する架空のユーザー像・人物モデルのことです。「ターゲットユーザー」と混同される用語ですが、正しくは、ターゲットユーザーをより具体化し、一人の人物のように考えたものがペルソナなのです。
ターゲット:実在する層
30代男性、東京都在住、会社員、スポーツ好き
ペルソナ:架空の人物像
山田太郎 34歳、IT企業勤務。年収700万円、東京都内在住でマイホームを購入、妻と娘1(小6)の三人暮らし。最近の悩みは、忙しくて運動不足になりがちなこと。
このようにペルソナを設定することで、顧客のニーズをより具体的に把握できるようになります。
カスタマージャーニーとは、「顧客が購入に至るプロセス」のことです。
具体的には、顧客がどのように商品・サービスと接点を持って認知し、関心を持ち、購入意欲を喚起されて、購買や登録などに至ったか、ということになります。一連の流れを、旅に例えているわけですね。
カスタマージャーニーを作成すれば、顧客のことを深く理解し、顧客目線での発想を生み出すことができます。
マーケティングの重要な手法を9つご紹介しました。
企業が利益を出すために、どのようなことを分析すべきか、おわかりいただけたのではないでしょうか?
マーケティングの手法を実践的に活用する方法について、詳しく説明した記事もありますので、気になる方はぜひこちらもご覧ください。
TRASPは、SEO対策・コンサルティング・マーケティングに強いホームページ制作会社です。対応している業種が幅広く制作実績が豊富で、集客力の続くホームページ制作を行います。
お問い合わせはこちら