マーケティングガイド
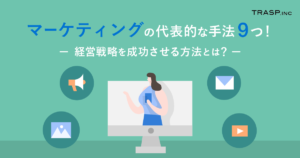
マーケティングの代表的な手法9つ!経営戦略を・・・
2021.11.12
TRASPコラム
マーケティングガイド
更新日:2023.03.23
公開日:2021.12.03
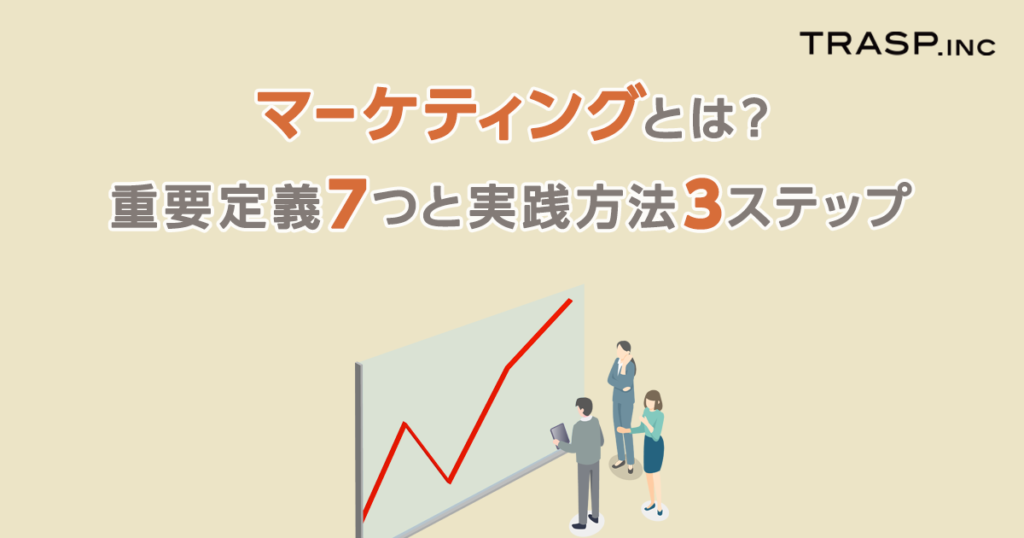
企業の経営活動に不可欠なマーケティング。よく耳にする言葉ですが、説明できる人はなかなかいません。また時代とともにマーケティングは変化するので、さまざまな解釈や定義が存在しており、よりマーケティング初心者を混乱させています。
マーケティングとは、一言で「売れる仕組みを作ること」と考えると良いでしょう。
「マーケティングの定義を知りたい」と思っている方に向けて、本記事ではマーケティングのプロであるTRASPが、過去の偉人やマーケティング協会による7つの定義を紹介し、歴史とともにどのように変化したかを解説。ぜひ最後までご覧ください。
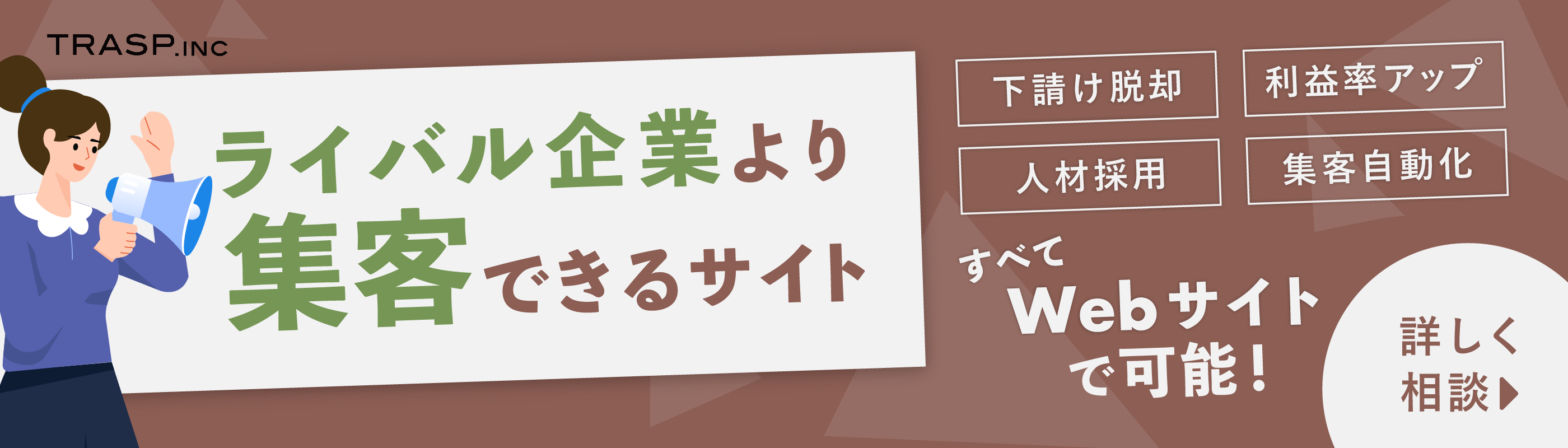
目次
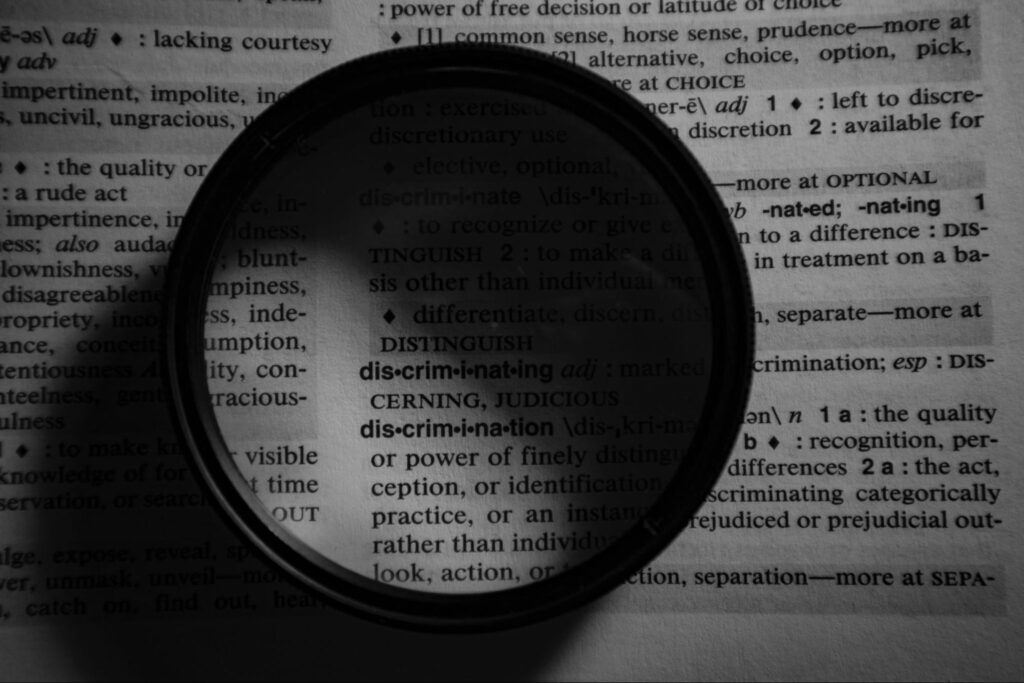
これまでに提唱されたマーケティングの重要定義は7つあります。それぞれを紹介しますので、詳しく見ていきましょう。
日本マーケティング協会は、1957年、高度経済成長期に向けて経済が急速に発展しつつある中、創設された公益社団法人です。
日本マーケティング協会が1990年に定義しており、
“マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である”
と発表しています。
要点をまとめると、
ということになります。
オペレーションズ・リサーチ(OR)とは、新しいシステムの構築・運用についての問題を、科学的な技術とコンピュータを用いて分析し、最適な解決案を見いだす「問題解決学」のことです。
日本オペレーションズ・リサーチ学会によると、
“マーケティングとは、個人や組織が製品の創造を行い、市場での交換を通じて自らのニーズや欲求を満たすために行う様々なプロセスのことである”
と定義されています。
株式会社ミツエーリンクスは、1990年というIT分野の幕開けともいえる時期から、さまざまなデジタルコンテンツを提供し、企業のマーケティングやブランディングを行ってきた会社です。
株式会社ミツエーリンクスによると、
“マーケティングとは、顧客の創造、維持を目的とする企業が、その目的を満たすような交換を顧客とのあいだに生み出すために、アイデアや財やサービスの考案から、価格設定、プロモーション、流通に至るまでを計画し実行するプロセスです。”
と定義されています。
また株式会社ミツエーリンクスは、定義に続けて、「マーケティングは販促活動ではない」ことを強調しており、また「社内の一部署(例えば、マーケティング部)だけが行う業務ではない」とも述べています。
つまり、販売や広報だけではなく、企業全体がマーケティングに取り組むべき、ということになりますね。
グロービス経営大学院は、ビジネスパーソン向けの私立大学で、3年以上の社会人経験のある人を対象に、「社会に創造と変革をもたらすビジネスリーダーの育成」を行っています。
グロービス経営大学院によると、
“マーケティングとは、顧客満足を軸に『売れる仕組み』を考える活動”
と定義されています。
最も大切なことは、「マーケティングの中心にいるのは顧客であり、顧客のニーズに応え、自然と顧客が引き付けられるような仕組みを作ること」と述べています。
アメリカマーケティング協会は、1937年に設立されて以来、30,000人以上のメンバーがマーケティング分野で活動、指導、研究しており、世界で最も大きい組織の一つです。
アメリカマーケティング協会は、時代の変化に合わせて、マーケティングの定義を最適なものに改定し続けており、最新の2007年の定義では、
“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.
マーケティングとは、顧客、依頼人、パートナー、社会全体にとって価値のある提供物を創造・伝達・配達・交換するための活動であり、一連の制度、そしてプロセスである。”
と発表しています。
ピーター・ドラッカーは、1909年に生まれたオーストリアの経営学者で、人類史上初めてマネジメントという分野を体系化した人物です。
“The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself.
マーケティングの目的はセリング(単純販売活動)を必要なくすることである”
(出典:「マネジメント」ピーター・ドラッカー)
と定義しており、「顧客を理解していれば、売り込みせずとも自然と売れるようになる」ということを強調しています。
フィリップ・コトラーは、1931年米国生まれで、「マーケティングの神様」「近代マーケティングの父」と呼ばれるマーケティング界の第一人者です。
“Marketing is about identifying and meeting human and social needs.
マーケティングとは社会活動のプロセスである。その中で個人やグループは、価値ある製品やサービスを作り出し、提供し、他社と自由に交換することによって、必要なものや欲するものを手に入れる”
(出典:「コトラーのマーケティング・マネジメント ミレニアム版」フィリップ・コトラー)
と定義しています。
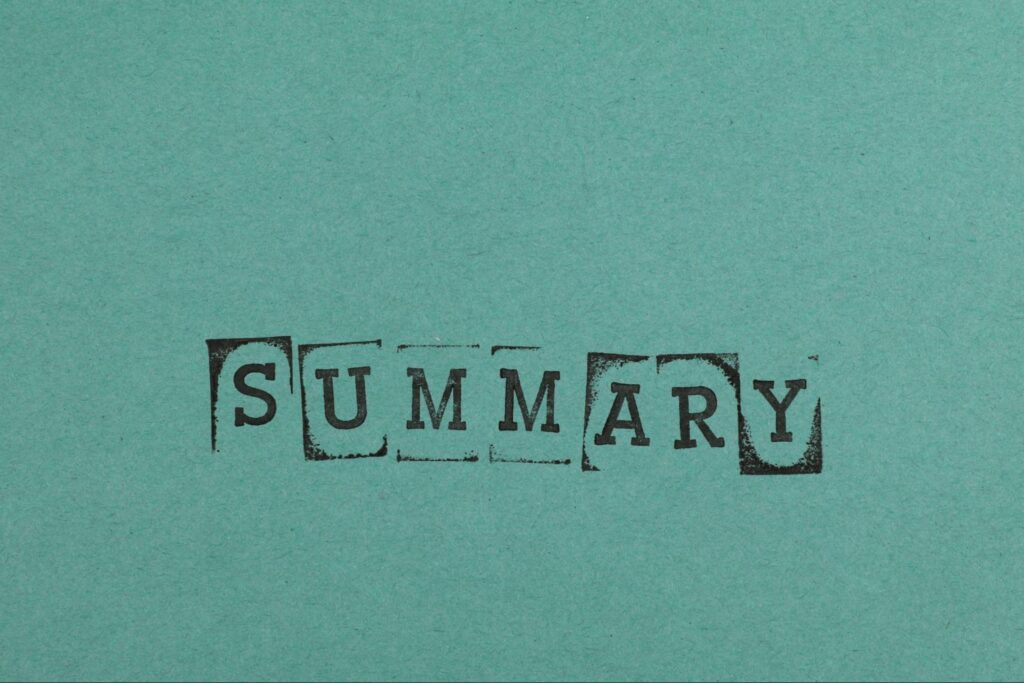
7つの重要定義をご紹介しましたが、これらに共通している本質部分を考えると、マーケティングは、”顧客との相互関係”を大切にしている概念ということがわかります。
すなわち、マーケティングとは、「売り込みをしなくても自然に売れてしまう状態を作ること」を目指すものであって、顧客に一方的に売り込む販売活動ではない、とまとめることができるでしょう。
アメリカマーケティング協会は、社会全体との関わりが大切で「モノを売るための活動だけでは良くない」ということを述べています。そのほか、経営学者フィリップ・コトラーは、「マーケティングと販売は、ほとんど正反対とも言える活動だ」とも述べています。
またコトラーは、「顧客を理解していれば、売り込みせずとも自然と売れるようになる」ということを強調しているので、マーケティングにおいて顧客の理解を深める”分析”が最重要ということになりますね。
マーケティング分析について「もっと詳しく知りたい!」という方は、こちらの記事をぜひご覧ください。
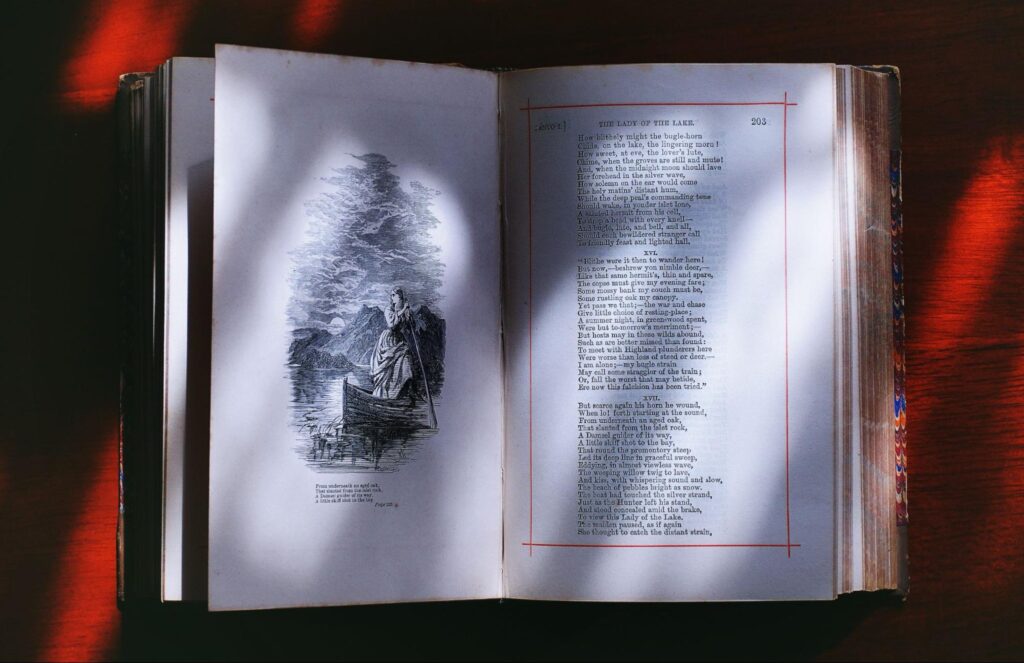
”マーケティング”という言葉についてより深く理解するために、ここではマーケティングの誕生と歴史を見ていきましょう。
「マーケティング」という言葉が最初に使われたのは、1902年、ミシガン大学の学報といわれています。この誕生からすぐに、マーケティングという言葉は社会に浸透し、3年後の1905年には、ペンシルバニア大学で「Marketing of Product」という講座が開設されています。
この頃、ゴールドラッシュや西部開拓の時代が終わり、アメリカ全土が対象となる市場が形成されはじめますが、その後、1929年〜1933年の4年間にわたって、大恐慌が発生。
大量生産・過剰生産が大恐慌の原因となっていたことがわかったため、マーケティングの必要性が問われはじめ、マーケティングの研究が盛んに行われるようになりました。
1937年には、シカゴに「アメリカマーケティング協会(AMA)」が設立され、世界のマーケティング研究の中心的機関となりました。
日本では、1955年ごろからマーケティングの研究が盛んになりました。日本生産本部(経産省管轄の財団法人)のアメリカ視察団が帰国した後、「これからはわが国もマーケティングを重視すべき」としたのがはじまりだそうです。
時代とともに、日本では次のようにマーケティングが変化しました。
1950年代は、作ったら作った分だけ売れる大量生産・大量消費の時代であったため、企業視点のマスマーケティングが中心でした。商品のプロモーション方法は、マスコミ四媒体といわれるテレビ・ラジオ・新聞・雑誌が中心でした。
1970年代になると世の中にモノがあふれるようになり、消費者がモノやサービスを選ぶ時代になったため、マーケティングも企業視点から顧客視点へ移っていきます。顧客一人ひとりのニーズに合わせたダイレクトマーケティングが中心となり、通信販売も行われる時代に。
1990年代からはインターネットが普及し始め、消費者が自ら情報を入手できるようになります。そのため、価値主導のマーケティングが盛んになり、インバウンドマーケティングという手法がとられるようになります。
マスマーケティングやインバウンドマーケティングなど代表的な手法について「もっと詳しく知りたい!」という方は、こちらの記事をぜひご覧ください。

実際にマーケティングを行う際には、次の3つの要素を順番に考えていくことになります。
そして、その際、STP分析とマーケティングミックスの2つのフレームワークを使うのが基本となります。2つの方法について、まだ知らない方はこちらの記事をぜひご覧ください。
モノやサービスを売るには、必要としている人のもとに必要なモノやサービスを提供すれば良いですね。そのため、1つ目のステップでは、STP分析の
の2つを行います。
セグメンテーションとは、市場を特定の属性を持ったユーザーで細分化することです。たとえば、年齢や性別、居住地、そして趣味といった、特定の属性に市場を細分化、グループ化していきます。よく使われる分類の仕方は次の4つです。
ジオグラフィック変数(地理的変数)
国、地域市町村、気候などで分類する
デモグラフィック変数(人口動態変数)
年齢、性別、職業、所得、学歴、ライフステージ等の客観的な基準によって市場を分類
サイコグラフィック変数(心理的変数)
ライフスタイルやパーソナリティ、志向や価値観など心理的な部分を中心にした分類
行動変数
商品に対する反応(購買状況、ベネフィット、ロイヤルテイ)による分類
注意すべき点は、やみくもに市場を細分化していてはキリがないことです。自社の強みをより活かせるセグメンテーションを優先し、客観的に分かりやすく明確に切り分けられるものを設定しましょう。
例えば、人口動態変数(デモグラフィック変数)から職業(例:会社員OL、専業主婦)、社会的心理的変数(サイコグラフィック変数)から、ライフスタイルの中のランチの方法(例:内食・弁当派、外食派)の基準を設定します。
納得がいくように市場を細分化することができたら、次に細分化された市場のどれを対象とするのかを決める「ターゲティング」を行います。
ターゲティングを行うに際して、”6R”と呼ばれるフレームワークを意識することが重要になります。6Rとは
という6つの基準を意味しています。
Realistic scale(有効な規模)
自社商品が売れる見込みのある市場規模であるかどうか。
Rate of growth(成長率)
将来的な成長性を持っている市場かどうか。
Rival(競合)
競合の数がどれくらいいるか。少ない方が当然良い。
Rank(優先順位)
ターゲットに関心を持ってもらえる物・サービスかどうか
Reach(到達可能性)
地理的に商品・サービスを届けることができるかどうか
Response(測定可能性)
どれだけ効果があったのかを測定できて、具体的に数値化できるかどうか
2ステップ目では、提供する価値を決めていきます。具体的には、
の2つを行います。
ここで述べる顧客価値とは、製品そのものの機能だけではなく、アフターサービスを受けられる・情緒的ベネフィットが得られる(楽しい気分になれる、優越感に浸れる)といったことまで含めた「広い意味での価値」を指します。
例えば、高級車は機能としては乗り物(移動手段)に過ぎませんが、高級車の価値には、洗練されたデザインや操作性といった部分のほか、「優雅な生活を満喫できる」「周りの人に自慢できる」といった情緒的なところまで含まれるでしょう。
顧客視点で価値を考えると、一つの製品をとっても、さまざまなニーズに応えられる可能性が出てきますね。
4C分析についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
ポジショニングとは、ターゲット市場での自社の立ち位置を決めることです。狙いたい市場における競合他社についてのリサーチを行い、自社が有利となる立ち位置を見つけ出すことが重要。
ポジショニングマップという二次元のマトリックス図を用いることが多く、二軸それぞれにそのサービスの価値を測る要素を置き、他社との位置関係を分析していきます。
3ステップ目では、ターゲットの手元に商品やサービスを届けるための、最適な流通方法を考えます。主に流通方法は、既存の流通業者を利用する方法と、自社で流通チャネルを整備する方法の2つあります。
既存の流通業者を利用する方法
通信販売など、多くの製品の流通方法で採用されており、コストは低めで効率的に商品・サービスを提供することができます。
自社で流通チャネルを整備する方法
コストがとてもかかりますが、自社チャネルで直接販売することで、販売活動の方向づけや管理を容易にできるほか、アフターサポートなどのサービスを的確に提供できるメリットがあります。
高級ブランド商品や高価格少量生産の住宅販売では、コストを利益で十分にまかなうことができるため、自社流通チャネルが活用されています。
またチャネル戦略を考える際は、以下の5つのポイントを検討します。
マーケティングは時代とともに変化していますが、どの時代でも根底にあるのは「顧客を正確に分析して、戦略を立てて、自然と製品・サービスが売れる仕組みを作る」ということです。
また実践するには、さまざまなマーケティングのフレームワークが必要とされるため、本記事の内容を参考に、ぜひマーケティングを経営に生かしてみてくださいね。
TRASPは、SEO対策・コンサルティング・マーケティングに強いホームページ制作会社です。対応している業種が幅広く制作実績が豊富で、集客力の続くホームページ制作を行います。
お問い合わせはこちら