オウンドメディア
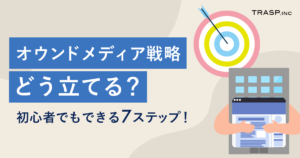
オウンドメディア戦略はどう立てる?初心者でも・・・
2023.03.01
TRASPコラム
オウンドメディア
更新日:2023.04.23
公開日:2023.03.20
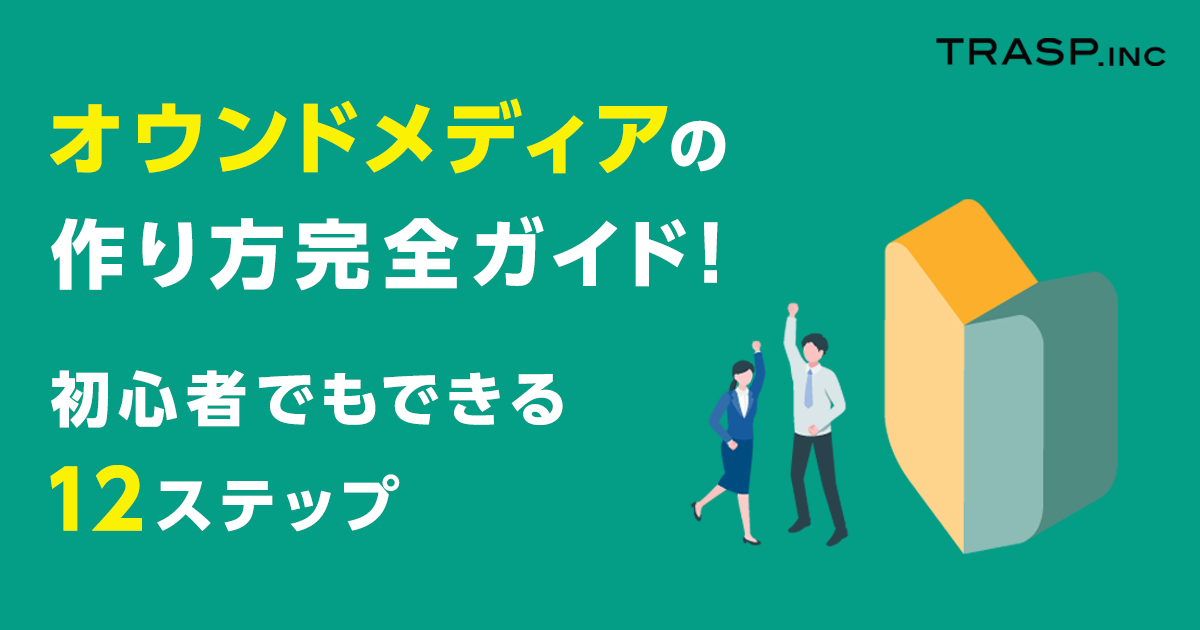
「自社が保有するメディア」を指す、オウンドメディア。近年Webマーケティング施策の一つとして、実際に活用する企業が増えています。
初めて自社でオウンドメディアを作る場合、「何から着手すれば良いか」「どのようなフローになるのか」と悩まれているご担当者さまも多いでしょう。
オウンドメディアは作り方がある程度決まっており、手順に沿って作成を進めれば失敗する確率がグッと下がります。そのため「正しい作り方」を理解すれば、立ち上げ・運用を成功へと導きやすくなるでしょう。
この記事では、オウンドメディアの作り方を完全ガイドいたします。これまで多くのサイト制作やWeb集客を手がけてきたTRASPが、初心者の方でもすぐに実践できる12ステップを詳しくまとめました。
目次

まずは、オウンドメディアを立ち上げるメリットを3つご紹介します。
ブランディングにつながる
オウンドメディアで積極的に情報発信し、多くの人に認知してもらえれば「〇〇は△△の会社」という印象を与えやすくなります。他社との差別化を図れるため、自社のブランディングをしっかり確立できるでしょう。
人材採用に有利
オウンドメディアで社員の声・社内の様子を発信すれば、“自社のリアルなイメージ”を読み手に伝えられます。その結果、自社の求人に興味を持つ求職者が増えやすくなり、採用活動にも大きく貢献するでしょう。
コンテンツを資産として残せる
オウンドメディアで発信するコンテンツは常に蓄積され続けるため、自社の“資産”となります。また一度公開したコンテンツは情報の更新・改善箇所は随時発生しますが、長期的に利用OK。「良質なコンテンツ」「有効な被リンクとの協働」「顧客ニーズを押さえた情報発信」を継続的に行えば、検索エンジンでヒットする確率が上がり、より多くの見込み客を獲得できるでしょう。
オウンドメディアの活用事例と戦略術をまとめた記事があります。
構築と運用にかかる料金相場を解説しますので、ぜひご覧ください。

前述したとおり、オウンドメディアには「正しい作り方」があります。“どのような手順を踏むのか・どのようなアクションが必要になるか”を意識し、各工程を進めることが大切です。
ここからは、オウンドメディアの作り方を段階ごとに解説します。まずは「準備・計画編」を見ていきましょう。
オウンドメディアを立ち上げる目的を明確にしましょう。なぜなら、目的があいまいだと「発信するコンテンツ内容に一貫性がない」「ネタ切れになってしまう」といった不都合が生じやすくなるため。
またオウンドメディアの目的として、主に下記の4つが挙げられます。
ここから1つor2つ程度に目的を絞り込み、オウンドメディアを運営すると良いでしょう。複数の目的を持つ場合は、優先度を設定することをおすすめします。
つづいて、ペルソナを決めていきましょう。ペルソナとは「30代男性」のようなざっくりとしたターゲット像を深く掘り下げたもので、「商品やサービスを実際に利用する顧客の架空の人物像」のことを指します。具体的な例については、下記をご覧ください。
このように名前・年齢・住所・職業・趣味など、細かい項目を設定していきます。
ペルソナを決めれば「ユーザーがどんな気持ちになれば、問い合わせ・求人応募につながるのか」「そのためにはどんなコンテンツを作れば良いか」など顧客目線を理解しやすくなります。また社内でターゲット顧客に対する共通認識を持てるため、オウンドメディアの運用をよりスムーズに進められるでしょう。
ペルソナについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
目的・ペルソナが決まったら、KPIを設定しましょう。KPIとはKey Performance Indicatorsの略で、日本語では「重要経営指標」「重要業績評価指標」と訳されることが多いです。
またオウンドメディアの指標として、主に下記のようなKPIが用いられています。
KPIを設定せずにいると「アクセスが増えたから、順調に運用できている」「アクセスが減っているから運用がうまくいかない」など、判断があいまいになりがちです。オウンドメディア運用の成果を正しく測るためにも、目的に沿ったKPIを設定しましょう。
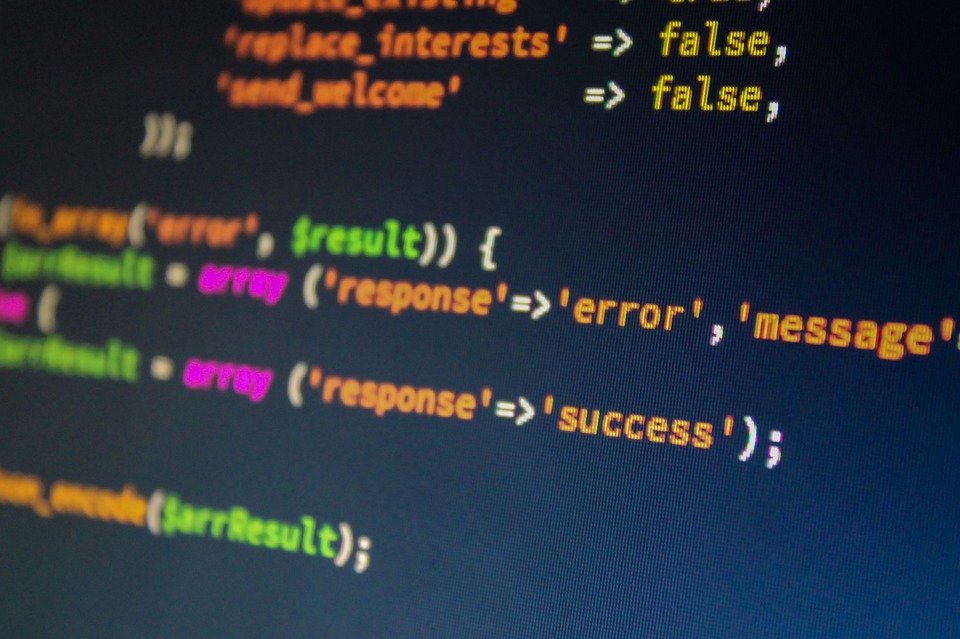
「どのような目的でオウンドメディアを立ち上げるか」「どのような層に自社を知ってもらいたいか」などを決めたら、実際に作り方を考えるフェーズへと移ります。つづいて「サイト制作編」に必要なステップについて詳しくまとめました。
オウンドメディアの構築に欠かせないのが、ドメインとサーバーです。
ドメインとは
「ドメイン」とは端的に言うと、インターネット上の住所のようなもの。ホームページを閲覧する際に、“インターネット上のどこにいるのか”を特定するために用いられます。例えば当サイト「https://trasp-inc.com/」の場合、アドレスの一部である「trasp-inc.com」がドメインに該当します。
サーバーとは
「サーバー」は一言で表すと、ホームページを保管しておく土地のような役割を持っています。取得したドメイン(住所)をサーバー(土地)に紐づけることで、そのURLにアクセスしたユーザーはサイトにアクセスできるようになります。
近年は、“機能や容量の変更がしやすい”クラウド型のサーバーが主流となっています。
またオウンドメディアを運用するなら、「独自ドメイン」がおすすめ。ドメイン名のすべてを自由に設定できるぶん、企業名・ブランド名をユーザーに認知してもらいやすくなります。
ドメイン・サーバーを用意したら、CMSを選定しましょう。CMSとはコンテンツの保存・更新などの管理が手軽にできるシステムで、具体的にはWordPress・microCMS・HubSpotなどが挙げられます。
また一般的には“無料・扱いやすい”というメリットがある、「WordPress」が主流です。さまざまなテーマが用意されており、一からサイトデザインを決める手間がかかりません。また世界的に見ても利用者が多いため、何かトラブルが生じた際でも解決策を見つけやすい点も魅力でしょう。
つづいて、サイトの構成を決めましょう。「カテゴリーをどのように分類するか」「トップページはどういうイメージにするか」「必要なコンテンツは何か」などを整理し、設計を進めていきます。
ただし見た目のこだわりを重視するあまり、情報が探しにくくなるのはNG。サイトはあくまでもユーザーのためにあります。“複数のページを見てもらえる、お問い合わせや資料請求などのコンバージョンにつながるような導線”を意識し、ユーザビリティの高い構成を目指しましょう。

オウンドメディアを構築できたら、記事作成を行っていきます。次に「記事制作編」における手順について、それぞれチェックしていきましょう。
記事を制作するにあたって、まずは対策キーワードを決めていきましょう。
なぜなら、SEO集客を中心としたオウンドメディアでは「想定読者が検索するキーワードをいかに記事に取り入れるか」により、成功が大きく左右されるため。検索結果で自社の記事が表示されなければ流入数が増えず、売上向上につながりにくくなります。
Googleのキーワードプランナー・ラッコキーワードなどのキーワードツールを活用すれば、検索需要があるキーワードを見つけやすくなります。そのなかから“検索ボリュームが多いキーワード・コンバージョン率が高いキーワード”を重視して選ぶと良いでしょう。
オウンドメディアを訪問するユーザーが、「どのようなことに悩んでいるか」「どのようなキーワードで検索するか」を先回りして考えることが大切です。
SEOキーワードの決め方について、解説した記事はこちら。
“ユーザーは何を知りたくて、そのキーワードで検索したのか”という意図を洗い出しましょう。
ユーザーによって、オウンドメディアに求める目的やニーズは変わります。「この会社のことが知りたい」「ほかの記事も読んでみよう」と一人でも多くの人に思ってもらえるよう、上記のような項目をしっかり分析しましょう。
キーワードを選定し、検索意図を洗い出してニーズを把握したら、それらにフィットした記事を執筆していきます。想定するターゲットに対して“自社にしかない魅力・価値”が伝わる情報を提供し、より接点を増やせるよう努めましょう。
またオウンドメディアの質を高めるために、古い記事をリライトする作業も行いましょう。数年前に更新された記事は古い情報が書かれていることが多く、検索エンジンの評価が低下しやすくなります。加えて更新された日時が古くなればなるほど、ユーザーからの信頼を獲得できなくなり、閲覧される機会も逃してしまうでしょう。
したがって新規記事の制作とあわせて、古い記事のリライトをすることも重要です。
SEOに強い記事の書き方について知りたい方は、こちらを参考にしてください。
オウンドメディアは、記事を書いて終わりではありません。良いオウンドメディアを作るには、分析・改善を行うことが大切です。ここでは「データ分析編」に欠かせないステップを解説していきます。
記事の制作とあわせて取り入れてほしいのが、サイト分析ツールの導入です。おすすめのツールとして、次のようなものが挙げられます。
Google アナリティクス
https://marketingplatform.google.com/intl/ja/about/analytics/
Googleが無料で提供しているWebページのアクセス解析サービスです。当サービスではサイト利用者の訪問状況や流入経路、行動パターンが分析できるため、うまく活用できればオウンドメディアの目的達成に大きく役立ちます。
Google サーチコンソール
https://search.google.com/search-console/about?hl=ja
Googleが提供する検索結果におけるWebサイトのパフォーマンス分析ツールです。サイト流入元の検索キーワードの表示回数やクリック数、サイトの掲載順位などサイト改善に必要な情報を幅広く収集できます。
GRC
Google・Yahoo!・Bingでの検索順位を把握するツールです。複数のサイト・複数の検索語をチェックできるため、多くの企業やサイトが利用しています。
このような分析ツールを利用すれば「記事のどこが読まれているか」「クリックされているか」を確認できるため、その都度必要な改善施策を見つけやすくなります。収集したデータから分析し、いまのオウンドメディアに不足しているものを洗い出しましょう。
おすすめのアクセス解析ツールを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
サイト分析ツールを導入した後は、PV数・滞在時間・直帰率・コンバージョン率などのデータを確認しましょう。ただ良い記事を投稿しただけでは、十分な結果は得られません。
“投稿した記事により、どのような成果が出ているか”を定量的なデータで振り返りましょう。
また、さきほど紹介した「Googleアナリティクス」「Googleサーチコンソール」を活用すれば、下記のような数値を計測できます。
ゼロから立ち上げるオウンドメディアの作り方マニュアル(medifund)
上記の項目はオウンドメディアを立ち上げてから毎月、あるいは毎週ペースで測定することをおすすめします。しかし立ち上げ直後は自然検索による流入は見込めないため、数値分析はある程度期間運用を行ってから始めると良いでしょう。
必要なデータを確認して課題が見つかったら、定期的に改善施策を行っていきましょう。具体的な改善施策の例として、下記のようなものがあります。
例えば狙ったキーワードがうまく上位表示されていた場合、Googleから高く評価されているテーマである確率が高いです。そのため近いテーマでキーワードを横展開すれば、次の記事も上位表示される可能性があります。
対して検索結果で上位表示されているのにあまりクリックされていない場合、それは記事タイトルが魅力的ではないと考えられます。記事タイトルを調整するだけで、集客数が伸びることもあるでしょう。
このように改善施策と一言でいっても幅広く、多くの手法や工程が存在します。「自社がいま取るべきアクションは何か」を常に意識し、多くのユーザーに支持されるオウンドメディアをつくりあげましょう。
当社では数多くの企業の市場分析やアクセス解析を手がけてきました。実際の改善事例を含め、詳細を下記ページで詳しく説明しています。ぜひご覧ください。
TRASPのアクセス解析

これまでに説明したように、オウンドメディアを実際に運用し、成長を促すためには「自社の課題に沿った戦略を立案すること」「質の高いコンテンツを継続して制作すること」「正しい効果測定を行うこと」などを実践する必要があります。
専門的な知見・ノウハウが必須となるため、「Webのスキルに自信がない」「オウンドメディアの運用を成功させたい」と考える方は、ホームページ制作会社への依頼を検討すると良いでしょう。
当社は中小企業のオウンドメディア構築・運用代行サービスを承っています。自社コラムのオウンドメディアにおいてコンテンツ運用施策を実施。「1年間でPV数が595%増」「さらにCV数を11倍UP」などの実績を保有しています。
また戦略設計やコンテンツ制作だけでなく、結果検証までを一貫して行っています。オウンドメディア運用に関する業務をTRASPにおまかせいただくことで、社内業務の工数削減やコスト削減が実現します。
TRASPの強み
この記事では、オウンドメディアの作り方を詳しくまとめました。初心者でもできる12ステップをご紹介しましたが、いかがでしたか?
前述した通りオウンドメディアを作るには、下記のように専門的な知見・ノウハウが欠かせません。
そのため「Webのスキルに自信がない」「オウンドメディアの運用を成功させたい」と考える方は、ホームページ制作会社への依頼を検討すると良いでしょう。
TRASPでは0から自社コラムを成長させた経験をもとに、オウンドメディアの制作・運用支援を行っています。お客さまに合わせた設計から丁寧にサポートしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら