SEO
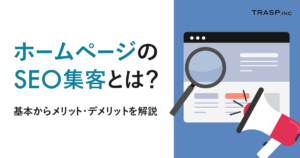
ホームページのSEO集客とは?基本からメリッ・・・
2023.04.14
TRASPコラム
SEO
更新日:2023.03.30
公開日:2021.02.16
インターネット上の記事はインターネットへ公開できるサービス、そしてパソコンがあれば誰でも執筆可能です。ただし読まれるブログ記事を書きたい場合はスキルが必要なので、簡単に執筆するわけにはいきません。
企業でもブログ記事を集客へ活用する機運が高まっており、読まれる記事をブログにアップロードして集客ができるように体制を構築するのは重要になっています。SEOにおいては文才がないとよい記事が書けないわけではなく、ある程度のコツを押さえれば初心者でもスムーズに読まれる記事を執筆できるようになるのがポイントです。
今回は読まれるブログ記事の書き方を探している方へ向けて、実際にWebライターとして活躍している筆者の経験も交えながらブログ記事の書き方をレクチャーしていきます。

目次

昔のマーケティング手法は、電話で見込み客へ営業を行うといったプッシュ式の手法が一般的でした。インターネットが普及し始めてから、状況は変化しています。
まずインターネットから手軽に情報を集められるようになったことで、自発的に情報を収集して商品やサービスの選定に活用するユーザーが増加しました。そして情報が増える中で、企業がユーザーのことを考えずにむやみに影響を行うプッシュ型の手法は鳴りを潜めました。
変わって主流になったのが、ユーザーが自分から流入してくれるのを待つプル型のマーケティング手法です。検索エンジンで自分の悩みを検索するユーザーは多く、検索エンジン上にブログ記事をアップロードして集客を狙う手法は有効になっています。
また一度上げたブログ記事は陳腐にならない限り、長期間指定されたキーワードで上位表示されるのもポイントです。いわば24時間365日働いてくれるセールスマンを、ブログをオウンドメディアとして利用することで用意できるのはメリットになります。
さらにブログを活用したマーケティングは最安で無料から始められます。また「レンタルサーバーを借りてWordPressをインストールして独自のブログを構築する」といった手法も、さほど費用は発生しません。ブログを活用したマーケティングは事業規模に関係なく、あらゆる業種が活用できるマーケティング手法です。
ちなみに現在では、「Twitter」といったSNSで情報を検索するユーザーも増加しています。そこでSNSにもブログの最新情報をアップロードして、ブログにもSNSリンクを貼りながら相互流入を狙う手法も増加しているのもポイントです。
ブログ記事を用意する場合は、検索エンジンに限らずさまざまなチャネルを意識しながら執筆を行っていきましょう。

ここからは初心者にも分かりやすいように、かみ砕きながらブログ記事の書き方を解説していきます。
まずは記事のテーマを決定します。
ブログでは独自の知見からユーザーのニーズがある情報を提供することが求められます。つまり自社が提供している商品やサービスに関するテーマの記事を選定するのが重要です。
たとえば自社がレシピ紹介サイトを提供しているのに、パソコンを使ったプログラミング方法に関するノウハウを教えるブログを解説するのはおかしいです。「レシピ紹介サイトを運用している企業のはずなのに、なぜプログラミングのレクチャーを行っているのか」とユーザーに捉えられて、混乱を引き起こしてしまう可能性があります。またブランド力醸成の点でも、自社の業種に合ったブログ記事をアップロードしないと関係構築は厳しいです。
専門性をブログに持たせる上でも、記事のテーマ決定は重要になります。
記事のテーマが決定したら、次は必要なキーワードの選定を行っていきます。記事のテーマから徐々に膨らませていき複数のキーワードを選んでいくのがポイントです。
記事を書く際のキーワードは、複数単語で構成されているものにしましょう。
キーワードには
といった種類があります。この内ビッグワードとミドルワードは大企業が運用しているコンテンツなどが上位を独占しており、中小規模の企業が立ち上げたばかりのブログ記事がいきなり上位を狙うのは厳しいです。
最初は3単語以上で構成されるようなスモールワードを選ぶと、競合が少ない分安心して質の高いブログ記事を書いて上位表示を狙えます。
たとえばレシピ分野で言うと「人気 レシピ」というミドルワードはすでに対策され切っているので上位表示は難しいです。しかし「たけのこ 時短 レシピ」とすればタケノコを使ったすぐできるレシピを探しているユーザーへ記事を表示しやすくなります。
スモールワードで上位表示を安定して狙えるようになると、「ドメインパワー」が付いていくのでブログコンテンツ全体が上位へ表示されやすくなるのもポイントです。ドメインパワーがついて自信がついてきた段階で、ミドルワードやビッグワードの対策にも取り組んでみてください。
キーワードが決定したら、次は想定読者を決めていきます。
想定読者によって内容は変わってきます。たとえば同じ「たけのこ 時短 レシピ」というキーワードでも、女性がターゲットであれば作りやすさや他レシピとの相性などを求められる可能性があるでしょう。また男性がターゲットの場合は食べ応えなどを重視される可能性があります。
このように同じキーワードでも想定読者によって内容が変わるかもしれないので、事前のリサーチでどんな読者へ情報を提供するのかをしっかり決めておく必要があります。
といった手法でターゲットユーザーを決定可能です。
またターゲットユーザーを考える際は「ペルソナ」の考えも重要になってきます。ペルソナの概要については後ほど説明していきます。
想定読者を特定した後は、記事執筆の元になる構成を作っていきます。構成の基本は「PREP法」になります。詳しくは後で説明するので最後まで読んでみてください。
ブログの基本構成でよく使われるのは、
などです。
「たけのこ 時短 レシピ」であれば、「2分でできる!簡単なたけのこレシピのおすすめを3つご紹介します」というタイトルを付けて想定読者に合わせた見出しを付ける方法が考えられます。
構成においてはh1タグに該当するタイトルの後に、
というように見出しが続いていきます。
階層を深くし過ぎると返って構成が分かりにくい記事になるので、h2~h4の間で構成を作っていくのがおすすめです。
ちなみにh2の数は3個以上とルールを決めているメディアも多いです。見出しの数に正解はありませんが、記事にある程度ボリュームを持たせたい場合はh2の数を3つ以上になるように調整してみてください。
h3やh4は文章の展開に合わせて適宜つけていくイメージになります。執筆途中に内容を変更する場合もあるので、柔軟に対応できるようにしておきましょう。
最後に実際に本文を執筆していきます。
前準備がすべて完了していたら、執筆はスムーズに進むはずです。途中で筆が止まってしまう場面が多い場合は、まだ内容を頭で考えて整理できていない状態に陥っています。そのまま無理に執筆してもよい記事は完成しないので、前のステップに戻って頭を整理しておきましょう。
また冒頭においては、
といった内容を入れ込むと読まれやすい記事になります。ターゲットユーザーと関係ないユーザーを間違って集客してしまう危険も防げるのがメリットです。
「一気に執筆するスキルがない」という方は、何を説明するのか内容を前もって箇条書きで各見出しに追加すると効果的になります。箇条書きの内容を膨らませて自然な文章にするだけで、読まれる記事ができあがります。
記事を執筆する際は、読まれやすくするためのさまざまなテクニックが必要です。詳しくは次の章で説明していくのでチェックしてみてください。

ここでは初心者が陥りがちな、ブログ記事の間違った書き方をご紹介していきます。
ブログ記事で成果を出すためには、ターゲットユーザーを意識する必要があります。しかし初心者の場合、どんなユーザーにも読まれるような記事をイメージして執筆を行ってしまう場合もあります。
ターゲットが絞れていない記事は内容があいまいになり、どんなユーザーにも刺さらなくなる記事になってしまうのがデメリットです。記事を読んだ方が自分事と捉えられないような記事はアップロードしてはいけません。
有名な四字熟語に「起承転結」があります。
の4つの点を意識して文章を執筆する方法として小・中学校で教わる概念です。
しかし「起承転結でブログを書けば見てもらえる記事になる」というのは間違いです。インターネットユーザーは「なるべく早めに結論を知り、興味があれば読み進める」といったスタンツを取ります。起承転結で記事を書いてしまうと最後まで何が言いたいのか分からないため、ユーザーが読み進めるのをやめて離脱してしまう可能性があり危険です。
小説をアップロードしてストーリーで興味を持たせたい場合は、構成に関して起承転結を取り入れてもよいと思います。ただしユーザーのためになるSEO記事を執筆する際、起承転結を意識するのはNGだと覚えておきましょう。
SEOに強い記事を執筆する際は、
などを考えて構成を練った後に執筆を開始する必要があります。焦ってとりあえず記事を執筆しようと思ってしまうと、内容が一貫しない内容の薄い記事が完成してしまう危険があります。
「記事を書きながら見出しといった構成を決めている」という方は今すぐやめましょう。記事の内容がぶれる可能性が高まりますし、効率よく執筆ができず途中が行き詰ってしまう危険があるからです。
たとえばエンジニアとして働いている方は、ついつい「システムをローンチして様子を見たい」といった表現を使ってしまうことがあります。「ローンチ」という言葉はサービスを売り出し始める際などに使われる言葉ですが、関連の業界にいない方には意味がまったく伝わりません。
ブログ記事に「新しいサービスがローンチされました」という表現を使ってしまうと、読み手が理解できず混乱を招くきっかけになります。意味が分からないと早々に離脱されて競合へ流れてしまう可能性もあるので注意しましょう。
冗長とは要するに、「長ったらしい」という意味です。たとえば「ブログ初心者はSEO、検索エンジン最適化のことですが、を意識せずに書く場合も多いと思いますが、それはいけないことです。」というのは冗長な文章になります。システム分野ではシステムストップを防ぐため冗長性が必要になる場合も多いのですが、ブログの執筆分野では冗長な表現は好まれません。
1つの文章に伝えたい内容が複数ある状態はユーザーの混乱を招きます。すぐに内容が伝わらないと専門用語を多用した際と同じく離脱が発生する危険が高まるので注意しましょう。
単調な書き方とは、たとえば
といった文章が該当します。
インターネットユーザーは素早く目的の情報を探せることに重点を置いています。つまり単調な書き方だとリズム感が悪くなって読みにくくなるだけでなく、ユーザーが欲しい情報をすんなりと頭に入れられなくなり離脱の原因になってしまうのがポイントです。
冗長な表現と合わせて、ブログの執筆時には単調な表現をしていないか確認する必要があります。
ブログ記事においてトンマナ(トーン&マナー、書き方に一貫性を持たせること)は重要です。トンマナはユーザー側に「この記事は真面目なテイストだ」というように印象を左右する重要な要素になっています。
しかし「このブログはおすすめ。なぜおすすめなのか解説させていただきます。」という表現は「です、ます」がないパターンと謙譲語が混在しており、トンマナが統一されていません。表現上の理由で強調するためにわざと混在させるパターンもあるかもしれないですが、SEO記事では一般的にトンマナをそろえないとブランド力を付ける上でも不利になるので注意しましょう。
ブログ初心者だと「小説などと同じように、ブログも上から下まできれいに読まれる」と思っている場合があります。しかし最後まできれいに閲覧してもらえると考えて「こそあど言葉」を多用したり、前の文章を読んでいないと分からない内容を注釈なしで記載するといった書き方をしてしまうと危険です。
ブログの読み手は時間がない状況で記事を読んでいる場合があります。上から下まで読まないと必要な情報が入手できないと時間が掛かり、すぐに目的に情報を入手できません。読み手の限られた時間で答えを提示しないと、ファンとして獲得を行うのは難しいでしょう。
マーケティングメールはタイトルがつまらないと誰も開封してくれません。他のメールに埋もれて読まれないままごみ箱に入れられてしまう可能性もあります。
ブログ記事も同じです。タイトルが「ブログ記事の書き方」といった平凡な内容だと、何を説明してくれるのかイメージが思い浮かばず検索エンジン上で興味を持ってもらえない可能性が高まります。
また記事内の見出しについても注意です。見出しにキーワードが入っていないと内容が分かりづらくなり、理解に時間が掛かってしまう可能性もあります。SEO的にもキーワードは見出しに入れておいたほうがよいです。
ブログ運営において発生しがちな問題において、「ディスクリプションの使い回し」があります。
ディスクリプションはブログ記事本文ではなく、検索エンジン上に掲載される文章の概要を示すテキストです。タイトルタグといっしょに検索エンジン上でブログ内容を説明するのに使われます。
しかしブログ運営の手間を省こうとして、複数の記事でディスクリプションを使い回す方もいらっしゃいます。しかしディスクリプションを使い回すと記事ごとの意味が検索エンジン上で伝わりにくくなり、クリックされても内容が違うのですぐ離脱するといった現象が発生してしまうのがネックです。
焦っていると記事を執筆した後、すぐに情報をアップロードしたくなります。しかしブログ記事でチェックを行わないのは厳禁です。
キーボードでタイピングをしていると、意識しない内に誤字・脱字が発生します。マーケティングで有名な大手メディアでも頻繁に誤字・脱字が発生しているので注意が必要です。
また文脈に違和感がないかもチェックする必要があります。間違っていないという「バイアス(思い込み)」はブログ記事に悪影響を与えてしまいます。

ここからは失敗しない、ブログ記事の書き方のコツをご紹介していきます。
ターゲットユーザーがずれないようにするには、「ペルソナ」構築を行いましょう。
ペルソナとはマーケティング分野において、「仮想的に作り出したユーザー」を指しています。たとえば化粧品であれば、「30代で子持ち、時短でメイクができる製品を探している」といったペルソナを作ってターゲティングを行っていきます。ペルソナは商品やサービスを広告やSNSなどで売り出す際も有効ですが、ブログ記事では指定のユーザーへ刺さる内容をぶれずに書きたいときに活用可能です。
記事ごとにペルソナは異なるので、事の内容に合わせてペルソナを使い回さないように注意しましょう。
ブログを使ってSEOライティングを行う際は、起承転結ではなく「PREP」を意識しましょう。
PREPとは
といったように結論や要点でサンドイッチのように文章を挟んでいく書き方です。
PREP法で記事を執筆すると、読み手は冒頭で結論や要点を理解して、読み進めるべきかそうでないか瞬時に判断できます。また説得力を持たせて文章の内容を広げていくためにも必要な筆記法です。
ブログ記事においてはリサーチが重要です。場合によっては執筆開始後より前の段階に時間を掛けて、執筆を進めていく必要があります。
などを考えながら文章前の準備を進めることで、文章の質は格段に上がります。
そして情報収集の上で構成を作ってから記事を執筆することで、執筆中に行き詰まる危険を防ぎながら効率よく執筆を進められるようになるのもメリットです。
特に初心者向けの記事の場合、専門用語の多用は危険です。少し大げさな表現になりますが、小学生でも読める文章を意識して執筆を行っていくのが重要になります。
ここでいう小学生が読める文章とは、「難しい言葉を使わずにかみ砕いて説明を行っている文章」を指します。詳しい意味は分からなくても、素人が読んだ場合でも何となく内容が分かる文章です。
専門用語を変換して分かりやすく説明できる場合は、分かりやすい説明を優先しましょう。またどうしても専門用語を使わないと説明できない部分は、注釈を入れて意味を説明してみてください。ちなみにカタカナ語も専門用語と同じように理解を邪魔する危険があるので注意しましょう。
ただし読み手がテーマに関してある程度知識を持っている場合は、注釈を入れなくても構いません。ペルソナに合わせて書き方を変えてみてください。
表現が冗長にならないようにするには、「一文一意」を意識することがポイントです。一文一意とは「1文章で1つの意味を伝える」という意味になります。「この本は面白い」といった文章構成は、基本的な一文一意の事例です。
1文に複数の意味が入っていると、ユーザーは頭の中で内容を整理するのが大変になります。しかし一文一意で説明を行うと、1つ1つ内容を区切りながら読み手が文章の意味を理解できるようになるのがポイントです。
並列表現で説明を行うといった場合は一文一意でなくてもよい場合があります。状況によって書き方を判断してみてください。
また冗長な文章は、読点を複数つなげて無理やり内容を伝えようとします。読点(、)が3個以上入ってしまうような文章は危険と思ってください。1~2個程度で読点が済むように工夫を行いながら執筆するのが重要です。
また「しかし」といった接続詞を多用する行為も冗長な文章を作ってしまう原因になるので危険です。適切に区切りを入れながらリズムのよい文章を執筆していくのがコツになります。
リズムのある文章を執筆するためには、単調な書き方を防ぐのも重要です。
といった工夫で、文章の読みやすさは格段に上がります。
読んでいて見た目に窮屈のない文章を作れているかがポイントです。
ブログを書く際は、キャラ付けとして文調をを統一してトンマナをそろえてみてください。
実世界においても、キャラがぶれていると他の方に違和感を持たれてしまいます。ブログ記事執筆でも状況は同じです。「です、ます口調が基本であればだ、である口調は使わない」といったように、あらかじめどういったトンマナでブログ記事を執筆するかルールを決めてからブログの運用を始めましょう。
ちなみに企業向けのブログ記事では「です、ます」口調が利用される傾向が多いです。ただしメディアによっては「だ、である」や軽い口調が使われる場合もあるので、自社がどのターゲットユーザーへ訴求したいかも考えながらトンマナを構成していきましょう。
ブログ記事を執筆する際は、飛ばし読みを考えた構成にするのもポイントです。
といった工夫でメリハリがつくようになり、飛ばし読みされても意味が伝わるブログを構築することができます。
短時間でも分かりやすいためになる文章とユーザーに捉えられれば、時間があるときもそうでないときも積極的にユーザーがファンとして文章を閲覧してくれる可能性が高まります。
検索エンジンでブログ記事に興味を持ってもらえるよう、タイトルの付け方はキャッチーになるように工夫する必要があります。
といった工夫でキャッチーになりやすくなります。ただし記号を使い過ぎたり「初心者はこれだけで大丈夫」といったフレーズを入れ過ぎると釣りタイトルと捉えられ、期待度が下がってしまう点には注意しましょう。
また見出しにキーワードを入れてみるのもポイントです。見出しにキーワードがあったほうが自然とどんな内容が文章に執筆してあるのかわかりやすくなりますし、SEO対策としても有効になります。
前半だけで意味が伝わるようタイトルや見出しの左側にキーワードを入れ込んでみるのもポイントです。ただし意味が不自然になるケースも多いので、必ず準拠すべきルールというわけではありません。
多少面倒でも、ディスクリプションを使い回さずに記事ごとに用意するのも重要です。ディスクリプションを記事ごとに用意することで検索ユーザーとの内容ミスマッチが減らせますし、クローラーも文章の意味を理解しやすくなります。
「ディスクリプションをいちいち用意して書き込むのが面倒」という場合は、WordPressといったサービスの機能を使いましょう。ディスクリプションを記載する欄に内容を執筆すれば、すぐ記事へ内容が反映されるようになっているので便利です。
人間は執筆が終わって間もないタイミングでは自分のミスに気づけない傾向にあります。ですからお茶を飲むといった行動で一息入れて冷静になった後、内容を確認してみると効果的です。
誤字・脱字が発生していたり文脈がおかしいと思ったら、その場ですぐ訂正しましょう。訂正したら訂正内容が正しいか、内容をもう一度よく見返してみてください。

今回はブログ記事の書き方を筆者の経験も基にして解説してきました。
読まれるブログ記事を書くためには、事前のテーマやキーワード、ターゲットユーザーの選定が重要です。そして構成を練って読まれるタイトルや見出しなどを付け、スムーズに読める工夫を文章中に盛り込んでいけば可読性が上がり集客パフォーマンスも向上するでしょう。