SNS運用
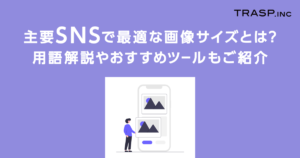
主要SNSで最適な画像サイズとは?用語解説や・・・
2021.11.29
TRASPコラム
SNS運用
更新日:2023.05.15
公開日:2022.01.25
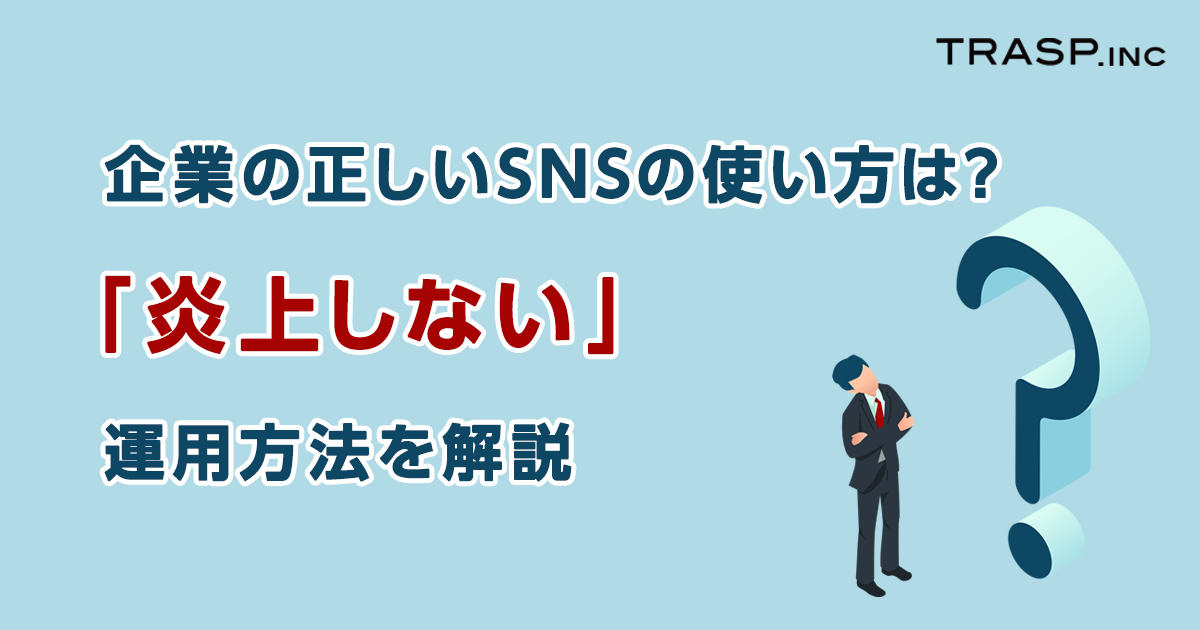
情報拡散力が高く、数多くのユーザーが利用するSNSは“販促ツール”として非常に優れています。
マーケティングの一環として、SNSを取り入れる企業も増えてきました。
しかし、そのようななかで
「企業でのSNS運用を検討しているが、間違った使い方を知って回避したい」
「炎上しない運用方法があれば教えてほしい」
と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、これまでに数多くのSNS運用実績を持つTRASPが、間違った使い方や炎上する使い方、事例を詳しくまとめました。
これを読めば、炎上を防いで回避できる正しい運用方法がわかります。
正しく使うことで得られるメリットも紹介しますので、SNS運用を検討している方はぜひご一読ください。
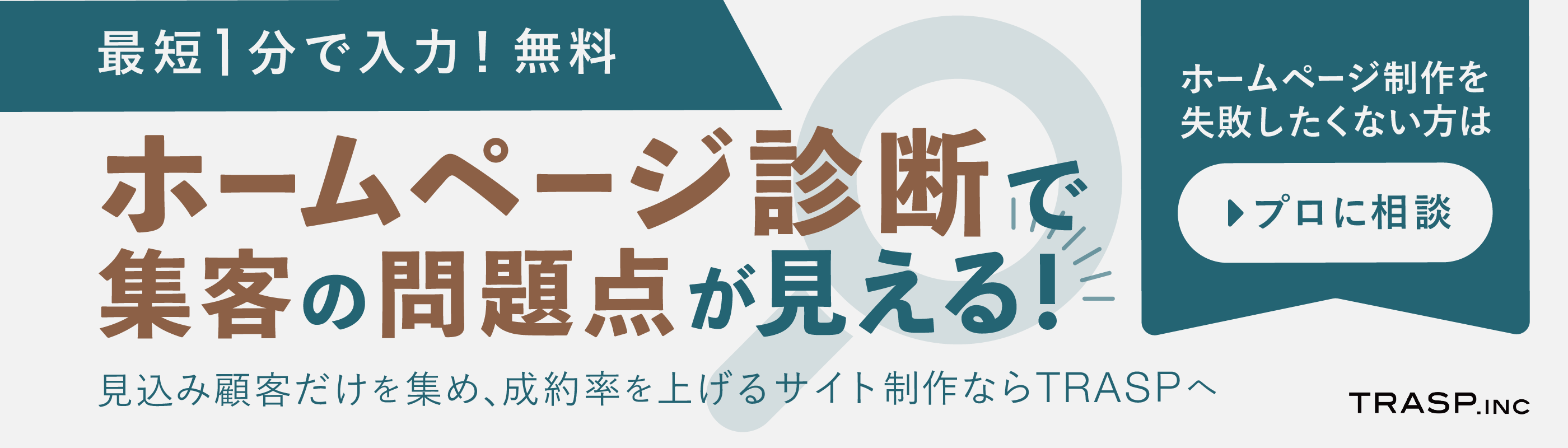
目次

SNSとは“ソーシャルネットワーキング(Social Networking Service)”の略。
オンライン化が進む影響でコミュニティケーションツールとして定着し、現在も多くの人が利用しています。
ホームページとSNSの違いは以下のとおり。
ホームページ
SNS
このように、ホームページとSNSは相互補完関係にあたります。
そのため、これらの違いを理解したうえで、マーケティングに活用すると良いでしょう。
集客や購買などの成果につなげるためには、どちらか一方だけではなく、それぞれ運用し併用するのをおすすめします。
企業がSNS運用をするメリットを、こちらの記事で詳しくまとめています。
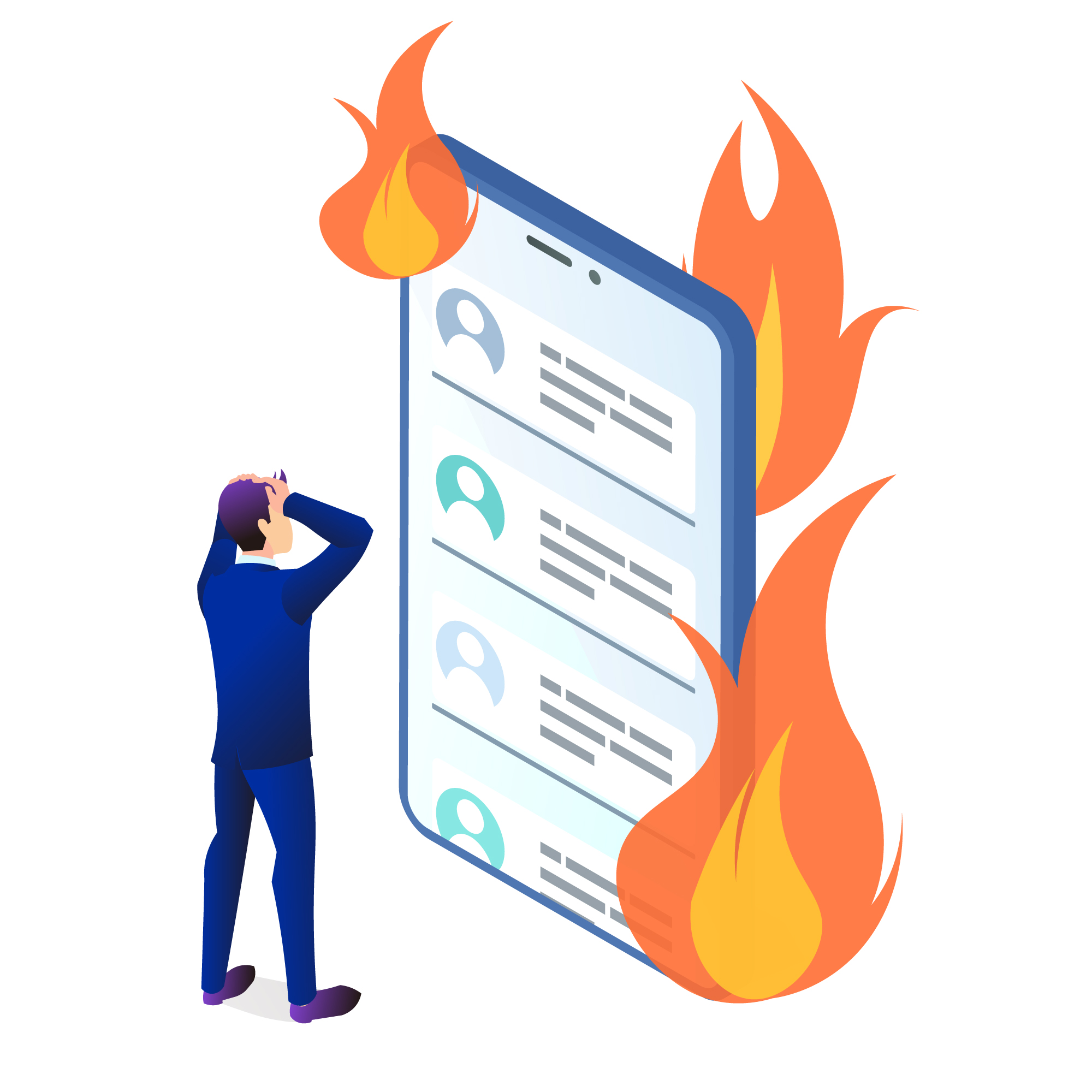
企業にとってのSNSでのリスクとは、次の2つのパターンがあります。それぞれを詳しく見ていきましょう。
SNSマーケティング上のリスクとして、以下のようなものが挙げられます。
企業のSNSアカウントにて投稿した内容が「読んだ人を不快な気分にさせた」として炎上するケースが多くあります。
衣料品メーカー:Twitterでの炎上事例
「タイツの日」と称される日程に合わせて、タイツを着用した女性のイラストをハッシュタグ付きで募集。
投稿された一部のイラストに、性的描写を連想させる内容があった。
その結果「企業が発信する広告としては不適切である」「誰に対して宣伝をしているのか」という声が、多くのユーザーから寄せられる。その後、企業は公式に謝罪を発表した。
このように「女性を性的に消費しているのではないか」と批判された例をはじめ、キャンペーンを紹介する際に掲載したコメントが「性犯罪を想起させる」と猛反発にあった例など、これまでにさまざまな炎上が起きています。
担当者が“ユーモアを交えたネタ”として投稿したとしても、その意図が消費者に伝わらなければ意味はありません。
マイナスイメージを持たれてしまえば、企業の信頼度は下がってしまいます。
そのため、SNSで投稿する際には「読んでいて誰かを傷つけないか」「倫理・モラルに反していないか」といった点を意識し、慎重に情報発信をしていきましょう。
ステルスマーケティング(stealth marketing)とは、“消費者に宣伝広告であることを隠して、気付かれないようにPR活動を行うこと”です。
ケースなどが該当します。
エンターテインメント企業:Twitterでの炎上事例
公開に先立ってある映画を視聴してもらったクリエイター7名に対し、感想を表現した漫画をSNSにて投稿してもらうという企画を実施。
企画自体には何の問題もなかったものの、クリエイターが投稿する際にPR表記していなかったことで、ステマ騒動に発展した。依頼側・請負側のコミュニケーション不足により、依頼から実際に投稿が行われるまでの間で「PR表記が必要である」という情報を共有できていなかったことが原因。後日、企業側は騒動に対して、公式サイト上で謝罪文を公開した。
ステルスマーケティングが発覚した際に生じる企業のリスクは大きく、ブランドイメージを損ねてしまう可能性が高いです。
そのため、企業はステマの意味や対象となる行為を正しく理解しましょう。
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、“過大な景品・不当な表示を排除し、消費者の利益を守るために定められた法律”です。金銭面の保護だけではなく、消費者自身が良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ることを目的としています。
この景品表示法などに違反したことで、問題となるケースも後を絶ちません。
サプリメント企業:Instagramでの炎上事例
サプリメントは医薬品ではないため、本来は「〇〇を解決する」という表記はNG。
しかし、「乾燥知らずのうるおい肌へ」という表現が使われており、薬事法違反に該当していた。そのほかにも、薬事法違反・景品表示法違反に触れる可能性の高い投稿が多く、炎上する事態に。最終的に企業は公式に謝罪。
コスメやサプリメントなど、健康に影響を与える商品は薬事法の対象となるため注意しましょう。
また、SNSへの投稿には景品表示法が適用されるため、法律に違反していないかをしっかりと確認してください。
このように、SNSは気軽に情報発信・共有ができるからこそ、トラブルとは常に隣り合わせになります。
そのため、
を検討すると良いでしょう。
社員が会社名を出して発信することで、その投稿が炎上した際に企業にまで飛び火してしまいます。
飲食業:Twitterでの炎上事例
アルバイトAが食材をごみ箱に捨てた後、再びまな板に置く様子をアルバイトBが携帯電話で撮影した。その後、Bの友人であるCにより、該当動画が投稿し拡散され、企業への批判が殺到。
企業は謝罪に加え、アルバイト3名に対する退職処分と刑事、民事での法的措置の準備に入ったことを発表した。最終的にAとBは退職処分、さらにBとCは「偽計業務妨害」、Aは「偽計業務妨害ほう助」の容疑で書類送検される事件に。
上記の事例以外にも、
というケースも。
また、個人が「不当解雇された」「上司にこう言われた」など会社の悪口をSNSに書き込むことで企業のイメージダウンにつながり、炎上につながった事例も数多く報告されています。
そのため、個人がSNSを利用する際においても、社員に対する教育や管理を行うことが大切です。
対処法としては、「SNSの勉強会・セミナー受講」などが有効でしょう。
自社に合う方法を取り入れて、ぜひ社員の倫理教育を実践してみてくださいね。
SNS運用時の注意点をさらに知りたい方はこちらも参考にしてください。

続いて、マーケティングにおけるSNSの正しい使い方5選を紹介していきます。
SNSによって特性は異なりますので、事前にリサーチしておくと良いでしょう。
自社の目的やターゲット、コンセプトに合う媒体を選択することが大切です。
また、ツールごとにアプローチを変えることを意識してください。
例えば
といった特徴があります。
運用するすべてのSNSに同じ内容を発信しても、同じ反応が得られるわけではありません。
そのため、媒体によってプロモーション方法を変えていくことで、効率的に集客率UPを狙えるでしょう。
ユーザーと企業の心理的な距離が近いSNSにおいては、ユーザー目線に立ったうえで情報発信することが重要です。
なぜなら、顔が見えないSNSだからこそ、丁寧に接することでファン獲得につながる可能性が高くなるため。
投稿する際に
など、相手の気持ちに寄り添う姿勢を忘れないようにしましょう。
SNSの専門知識を持った運用担当者を採用しましょう。
誰にでも手軽に使え、気軽に投稿できると思われるSNSですが、企業のSNS運用においては専門の知見が必要となります。
運用担当者の業務として、以下のようなものが挙げられます。
SNSの設定
投稿する内容の検討
投稿するコンテンツの作成やチェック
消費者や利用者とのコミュニケーション(コメント返信、メッセージ対応など)
自社内における各部署との打ち合わせ
データ分析及び運用改善
このように、SNS運用といってもさまざまなアクションが必要です。
戦略的に自社のSNSを活用していくためにも、専任の担当者を決めておきましょう。
各SNSに合ったガイドラインを策定することをおすすめします。
共有しておけば引継ぎの際や、複数人でSNSを運用する場合に役立っていくためです。
例えば、次のような項目を決めておくと良いでしょう。
投稿頻度や投稿内容
トンマナ
キャンペーンなどに必要な予算
制作物(画像・動画など)を依頼する方法
SNSは長期的に運用して、成果につながるケースがほとんど。
できる限りリスクを軽減していくために、ガイドラインの策定をしっかりと行いましょう。
SNSを運用していくうえでは、いつ炎上や乗っ取りが起きるかわかりません。そのため、トラブル発生時に迅速な対応をするためにも、企業のSNSは放置せず常に監視することをおすすめします。
しかし、通常の業務をこなしながら、休日や夜間もSNSをチェックするのは大変ですよね。
そこで、監視に特化した外部サービスを3つ紹介していきます。
https://search.yahoo.co.jp/realtime
Yahoo!リアルタイム検索は、トップページの検索バーの上にあるリアルタイムボタンをクリックして、そのまま利用できます。検索したいキーワードを入力すると「そのキーワードがどの程度リアルタイムで検索されているか」「ポジティブな反応orネガティブな反応のどちらが多いか」といった内容まで調査可能です。
また、Twitterに投稿されたツイート(つぶやき)をYahoo!検索の「リアルタイム検索」で検索できます。過去には、FacebookやInstgramの投稿も確認できましたが、現在は対応していません。システムの特性上、検索できるのは30日以内となっています。それ以上はさかのぼれないため、注意してください。
https://www.google.co.jp/alerts
グーグルアラートは“調査したいキーワードを登録しておけば、それに関連する情報がインターネット上で掲載された際に通知してくれる”という機能です。通知頻度は変更可能で、方法はGmailかRSSフィードのいずれかになります。
炎上のキッカケを即座に見つけたい場合は、「会社自体に関するキーワード」「代表者や役員に関するキーワード」「商品・サービスに関するキーワード」をあらかじめ設定しておくと良いでしょう。
また、何かしらの批判的な記事が投稿された際には、自社サイトやSNSがリンク設定されるケースがほとんどです。そういった記事を拾うために、自社サイトとSNSのURLも検索キーワードとして設定すれば、トラブル発生時に迅速に対応できます。
https://eltes-solution.jp/service/riskmonitoring/
リスクモニタリングサービス(株式会社エルテス)は、AIと目視を組み合わせてリスク判別を実施しており、24時間365日SNS投稿の監視サービスを提供しています。投稿した内容に企業情報やお客様情報が含まれていないかを確認し、リスクの火種を素早く検知。リスクの投稿検知後は、初期対応のサポートをすぐに実施します。幅広いサポートを実施しているため、安心して運用を任せられるでしょう。
上記のような利便性が高いサービスを取り入れ、効率的に企業のSNSを運用していくと良いでしょう。

SNSを正しく使うことで得られるメリットとして、以下の2つが挙げられます。
自社のSNSアカウントを運用する際に、ぜひ参考にしてください!
企業がSNSを正しく使えば、自社のブランディングを強化できます。なぜなら、SNSで発信する世界観を統一していけば、ユーザーに「〇〇(商品・サービス)=この会社」といった印象を与えられるためです。そのような認識が拡大して、イメージを定着させていけば信頼度向上を目指せます。
自社の商品・サービスの認知拡大も狙えます。なぜなら、各SNSには「いいね!」「シェア」などの情報拡散機能が搭載されているためです。
「この情報を誰かに教えたい」と思ったユーザーが、その時点で情報拡散を行います。そうすれば、まだその企業を知らない人に対して最新情報をリーチできる可能性が高くなるでしょう。そして、最終的に自社商品・サービスの名前を知ってもらうキッカケとして活用できます。
したがって、潜在層を含む多くの人へ向けて商品・サービスの認知拡大に役立つと言えるでしょう。
当社ではホームページ制作だけではなく、マーケティングやSNS運用においても数多くの実績を保有しています。「SNSから見込み顧客を獲得」「企業ブランドの構築」「ターゲットを絞った広告配信」の3軸を強みに、お客さまの状況やご要望に応じて最適なプランニングを提案いたします。
SNS運用はこちら
この記事では、企業の正しいSNSの使い方や炎上しない運用方法を解説しました。企業がSNSを運用するにあたって、さまざまなリスクが伴います。そのため、トラブルを回避するポイントを押さえて運用に臨むことが大切です。一方で、SNSにはリスクを上回る数多くのメリットも存在します。さきほど紹介した正しい使い方を意識してマーケティングに活かせば、自社の集客率向上も狙えるでしょう。
TRASPは、これまでに数多くの業種の集客支援に携わってきました。SEO対策・コンサルティング・マーケティングも強く、幅広い分野で手厚くサポート!SNS運用に関してもさまざまなノウハウ・知識を保有しているため、お客さまに最適なプランをご提案できます。無料相談も行っていますので、まずはお気軽にお問合せください。
