ブランディング
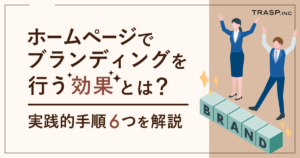
ホームページでブランディングを行う効果とは?・・・
2023.02.02
TRASPコラム
ブランディング
更新日:2023.04.23
公開日:2023.03.20
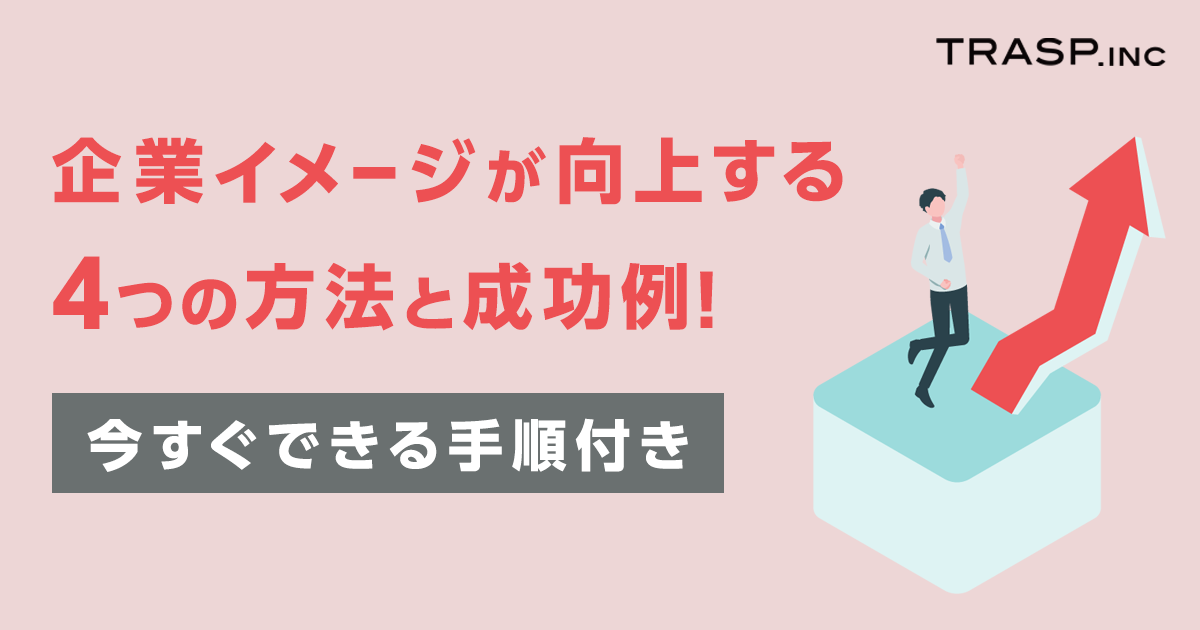
近年ではインターネットやSNSが急速に普及し、多くの情報がすぐに拡散・共有されるようになりました。企業イメージが業績に与える影響は年々大きくなっているなかで、このようなお悩みを持つご担当者さまも多いでしょう。
「イメージを向上させたい」
「何からすれば良いかわからない」
企業イメージを向上させるためには、会社そのものや従業員の魅力を高めることが重要です。そのためにも“必要な方法・手順”を知り、自社に合うものを選択すると良いでしょう。
この記事では、企業イメージが向上する4つの方法を徹底解説!幅広い業界のブランディング施策を行ってきたTRASPが、いますぐできる手順や成功事例も詳しくご紹介します。
目次

「そもそも企業イメージとは?」という疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
企業イメージとは顧客・取引先・株主・従業員などが、その企業に対して抱く全体的な印象や共通認識のこと。この企業イメージは商品やサービスの品質・従業員の対応・SNSの評判・広告の内容をはじめ、その企業が関わるさまざまな要素から影響を受けています。
例えば「質が高い」「環境にやさしい」商品を提供する企業であれば、消費者は商品に加え、企業全体に対しても安心感や信頼感を持つでしょう。
一方でニュース・SNSを通じて企業・社員の不祥事が報じられれば、その企業にとって大きなイメージダウンに。その結果、顧客が他社に流れたり、商品を買ってもらえなくなったりして売上が激減することになります。
したがって「信用できる」「スタイリッシュである」「人気が高い」「高級感がある」など、顧客が持つ企業イメージは、企業の個性であり、同時に資産であるといっても過言ではないでしょう。
結論
企業が収益を上げるためには、“自社ならではの魅力”をより多くの人に理解してもらい、企業イメージの向上を図ることが大切といえます。

つづいて、企業イメージを向上させる具体的なメリットを3つご紹介します。
他社との差別化を図れる
売上、利益の向上
優秀な人材を確保しやすくなる

ここからは企業イメージを向上させる方法4つをご紹介します。方法ごとにブランディングの対象や得られる効果が変わるため、自社の目的に応じて使い分けると良いでしょう。
アウターブランディングとは、一般のお客さまや取引先など社外に向けたブランディング活動のことです。
代表的な手法
企業イメージを幅広く浸透させるためには、視覚や聴覚を活用したアプローチを行うことが重要です。特にロゴやキャッチコピーは、「どのような企業なのか」というイメージが一目で伝わる内容にすることをおすすめします。
例えばアウターブランディングの成功例として、Apple社のiPhoneが挙げられます。実際にAppleのロゴを見ると「デザインが美しく、洗練されたイメージ」「アプリが充実している」という印象を受ける方も多いのではないでしょうか。
それらの印象により「iPhoneが欲しい」と思う人が増え、いまでは世界的に多くのファンを抱えるプロダクトとして成長を遂げています。
このように消費者に対してプラスのイメージを与えられれば、その商品・サービスを使うこと自体に価値が生まれ、自社のブランドの認知度が大きく高まるでしょう。
インナーブランディングとは、社内に向けたブランディング活動のことです。その名前のとおり、企業の「内側」である自社の従業員を対象にブランディングを行うこと。
インナーブランディングの成功例:スターバックス
福利厚生を充実させることで安心して働ける環境作りをするなど、従業員を大切にする姿勢や主体性を尊重し、エンゲージメントを高め、企業・従業員の間において目的と価値観を共有することに成功しました。
マニュアルをなくし「心をこめる」「歓迎する」などの指針のみを掲げ、「どのような対応をするか」という具体的な行動については従業員一人ひとりへ自由に委ねることで、従業員の仕事に対する誇りにつながっているとのこと。
このようにインナーブランディングによって、従業員が働くことへのモチベーションが上がれば、商品やサービスの品質が磨かれていきます。最終的には企業の利益に還元されるため、社外だけでなく社内に向けてもイメージの向上を図りましょう。
ストーリーブランディングは、企業や商品・サービスが持つストーリーを幅広く発信するブランディング活動を指します。具体的にはこのような情報を発信すると良いでしょう。
上記のように「自社や商品がどのような物語を経て存在しているのか」「その商品には誰の、どのような思いが込められているか」など背景にある物語を知ってもらい、企業に対する顧客の愛着を深められるようにします。
もしサービスや商品の内容が他社と似ていたとしても、それが成立するまでのストーリーは、自社独自のものです。そのため、自社やその商品を競合他社から差別化したい場合は、ストーリーブランディングは有効な手法といえるでしょう。
採用ブランディングとは、採用全般におけるブランディング活動のことです。
主なアピールポイント
近年は“福利厚生が充実しているか”を基準にして、就職先を探す人が圧倒的に多いです。特に福利厚生を重点的に見直し、求職者の関心を引ける機会を増やせるよう努めましょう。
ホームページでブランディングを行う効果、実践的手順6つを詳しくまとめています。
幅広い業種のホームページをブランディングしてきた経験や実績が豊富なTRASPでは、ブランド戦略の擦り合わせや目的のヒアリングをしっかりと行い、集客の強化に効果を発揮するブランディングを行います。
TRASPのホームページ制作

つづいて、企業イメージを向上させる手順5ステップを解説します。
まずは自社や商品・サービスブランドが「どのようなイメージを持たれているか」を調査しましょう。
自社のポジショニングに加え、市場で“どのような立ち位置を目指すのか”を明確にすれば、ブランディングの方向性を定めやすくなります。消費者を対象に行う消費者調査・商品の市場規模や競合商品などの調査をはじめ、実際に製品をテスト販売し、モニターからの反応を測定する実地調査などを行うと良いでしょう。
次に、自社のブランドアイデンティティを明確にしていきます。ブランドアイデンティティとは、消費者に抱いてほしいブランドイメージのこと。下記のような項目を深く掘り下げ、幅広い消費者に受け入れられるものを打ち出していきます。
ブランドアイデンティティが「ユーザーの気持ちを無視したもの」「企業側が一方的に押し付けるもの」になってしまうのはNG。反感を買うことにつながり、SNSなどで炎上も引き起こす可能性があります。
したがってユーザーに寄り添う姿勢を重視し、企業・社員・ユーザーがともにゴールを目指せるようなものを設定しましょう。
ブランドアイデンティティは、長期的なブランド戦略の指針となる大切なコンセプトです。そのため簡単に捨ててユーザーの信頼を裏切らないよう、一貫した姿勢を通しましょう。自社の強みをよく把握し、あらゆる角度から検討して慎重に決めることをおすすめします。
ブランドアイデンティティを定めたら、ターゲットを設定しましょう。
すべての消費者に対し、均一にブランドイメージを向上させることは不可能です。ターゲットとするユーザー層を具体的に決めれば「どのような情報を発信すべきなのか」「魅力を感じてもらえるデザインは何か」など、自社が取るべき戦略をより把握できます。
そのためには、具体的にはユーザーの年齢層・ライフスタイル・価値観…などを細かくイメージすると良いでしょう。精度の高いターゲット設定をすれば、ユーザーの心に刺さる施策を見出せるぶん、長期的な顧客をつかみやすくなります。ブランド戦略の成功を大きく左右するため、こちらも入念に進めていきましょう。
ターゲットをよりさらにユーザー像を細かくしたものを、「ペルソナ」と呼びます。このペルソナ設定に関する情報をまとめた記事があるため、ぜひご覧ください。
つづいて1~3の流れで抽出した課題を洗い出し、適切な戦略を実行しましょう。必要な戦略については「製品ブランディング」か「企業ブランディング」によって、大きく異なります。代表的なものを下記にピックアップしたので、ぜひご覧ください。
製品ブランディング
企業ブランディング
あわせてブランディング戦略を実施するための、訴求方法も決めましょう。例えばメディアへの広告展開(マスメディア、屋外広告、Webほか)・広報活動・SNSを活用したアピール・イベントやプロモーションなど、さまざまな施策が考えられます。
また、ブランドの訴求方法を決める際には「ブランドのイメージやターゲットに合った媒体やツールを選ぶこと」「適切なトーン&マナーで表現すること」が大切。多くの消費者に“独自の価値”を存分に伝えられるよう、自社の現状や方向性に合った戦略・訴求方法を見つけましょう。
ブランディング戦略がスタートしたら、PDCAを繰り返し行いましょう。
ブランド評価の定点観測を実施し、戦略がワークしているかを検証していきます。具体的には消費者調査・市場調査に加え、PR活動やWebサイトなどのオウンドメディアを通じて効果測定するのもおすすめ。また企業ブランディングの場合は、従業員満足度・従業員ロイヤリティなどを図る社内でのアンケートを行うのも効果的です。
随時改善策を考案・実行し、企業イメージの更なる向上を目指しましょう。
TRASPではブランディングを加味したホームページ制作やマーケティング施策を実施しています。多くのお客さまからブランディングを通した問い合わせ数や契約数増加の報告をいただいているため、安定した売上増加の手段としてぜひご活用ください。
お問い合わせはこちら
最後に企業イメージの向上に成功した事例3選をご紹介します。「どのような取り組みをしたのか」「成功要因は何だったのか」など詳しく見ていきましょう。
1つ目の事例は「今治タオル」です。“高品質なタオル”として人気を誇る同商品ですが、かつては輸入タオルに圧倒され、ブランドとして危機的状況に陥っていました。
そこで「今治タオル」は個別のブランドではなく、産地としてのマスターブランドの確立を目指すことに。“愛媛県の今治をタオルの産地”としてブランド化するため、さまざまな戦略を実行してきました。具体的には、下記の取り組みが挙げられます。
さらに品質の高さを強調する白いタオルを強く訴求することで、「白い無地のタオル=今治タオル」というブランドイメージの確立に成功。順調に知名度が上がり、いまでは世界各地で多くの人から愛用される商品となりました。
2つ目の事例は「マツダ」です。以前は「マツダ地獄」といわれる状況もあった同社ですが、既存の顧客にフォーカスした製品開発を行い、再びブランド価値を回復させました。
マツダ地獄とは
1990年代にマツダは、販売数を増加させるために店舗ごとで取扱ブランドを分ける「多チャネル化戦略」を実施。結果的に当戦略は成功せず、在庫処理のために値引きをしなければならない事態となりました。
また新車の値段が安くなったことで、下取り価格も下落。そのため顧客は「マツダに下取ってもらうしかない」「次の自動車もマツダを購入しなければならない」というループに陥ります。これによりブランド価値が大きく低下した出来事を「マツダ地獄」といいます。
そして同社は、この「マツダ地獄」から脱却するため、顧客視点の企業戦略へと大胆な方向転換を図ります。主役を「車」ではなく、「顧客の生活や価値観」として“Be a Driver”という新たなコンセプトを設定。
「自社の製品を愛してくれる人のために最高の製品を提供する」という考えのもと、ユーザーが何を求めるかを徹底してリサーチし、シェアよりも顧客を大切にする姿勢を長年貫いてきました。
その結果「車にこだわるならマツダ」というブランドイメージが定着し、世間の評価を大きく変えることに成功。ITmediaビジネスの記事によると、2022年5月時点での営業利益は前年比の11倍と、いまでは非常に需要が高まっていることがわかります。
ブランディングにおいて、“自社が闘うポジションを明確化すること”の重要性がわかる事例でしょう。
https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage
3つ目の事例は「ルイ・ヴィトン」です。
ルイ・ヴィトンといえば、「L」「V」を組みわせたモノグラム柄を思い出す方は多いでしょう。この柄を見るだけで、誰もが自然と「ルイ・ヴィトンの商品である」とイメージできるほど、知名度を獲得することに成功しました。
また生産量をあえて限定することで、商品価値をより高められるよう工夫しています。「あえて露出を制限すること」「希少性を生み出し持っていること」で、ステータスと感じるブランドイメージを築き上げました。
この記事では、企業イメージが向上する4つの方法と成功例を詳しくまとめました。今すぐできる5ステップの手順も解説しましたが、いかがでしたか?
企業イメージを向上させれば、「他社との差別化を図れる」「売上・利益の向上」などのメリットがあります。また、ブランディングにもさまざまな方法が存在します。「どれを選ぶか」によって得られる効果も変わるため、特性を理解することが大切です。
紹介した5ステップや成功事例を参考に、自社に合う取り組みを実施すると良いでしょう。
TRASPは中小から大規模な会社のお客さままで、多くのホームページ制作実績があります。集客特化型など、ご要望に合わせた提案も可能です。無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら