SEO
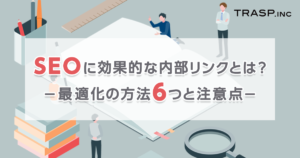
SEOに効果的な内部リンクとは?最適化の方法・・・
2022.01.06
TRASPコラム
SEO
更新日:2023.03.22
公開日:2022.02.23
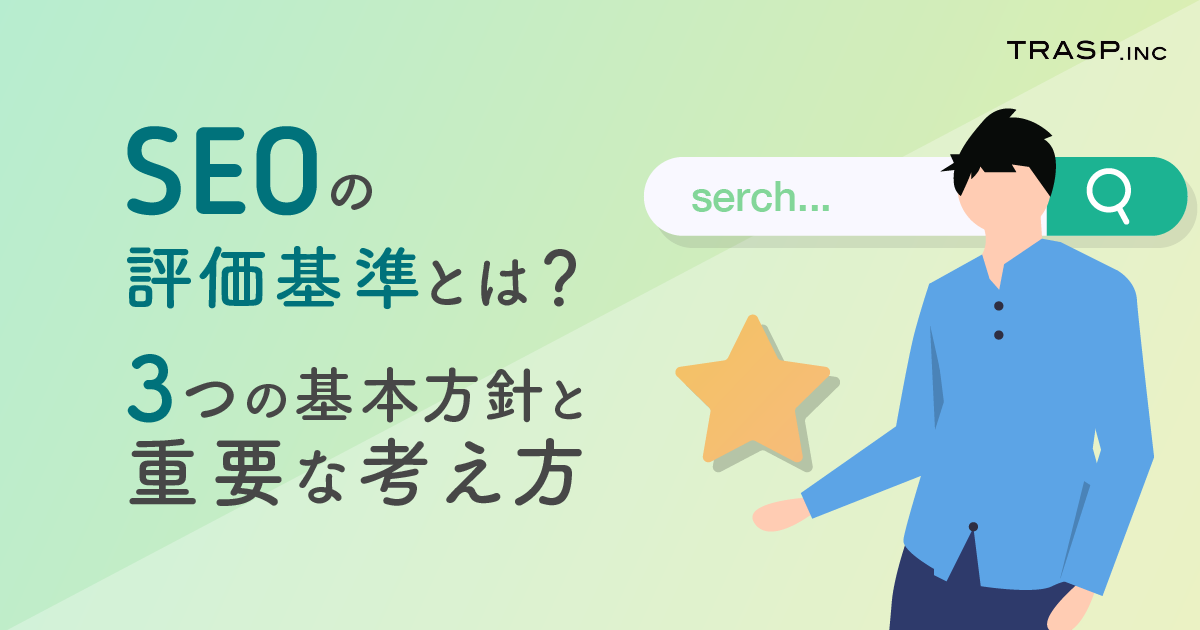
SEO対策に取り組むなかで、「SEOの評価基準を知って、効果的な対策をしたい…」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。SEOでは明確な評価基準が公表されていないものの、本質的な考え方やSEO評価の基本方針は学べます。
そこで本記事ではSEOの評価基準について、3つの基本方針と重要な考え方を解説していきます。
基本から専門的なSEOまで幅広い知識をもつTRASPが、評価基準に関する注意点や評価を高める方法についても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください!

目次
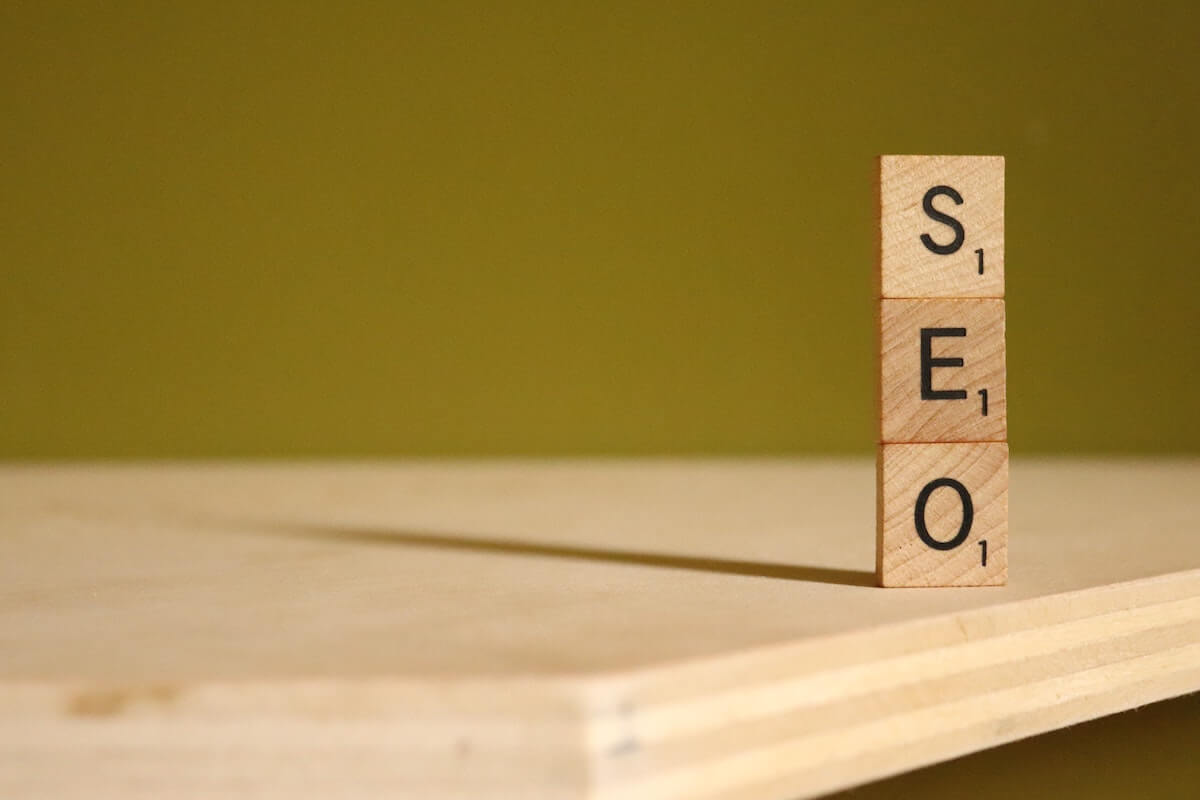
SEOとは「Search Engine Optimization」の略で、検索エンジン最適化を意味します。
ユーザーがGoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジン上で検索をした際に、結果画面で自社サイトを上位表示させることが目的です。
検索結果の順位は、検索エンジンのアルゴリズムがインターネット上のWebサイトを評価し、ランキング形式で表示する仕組みです。したがってSEOの評価とは、検索アルゴリズムが判断する複数の要素から成り立ちます。
「そもそもSEO対策ってなに?」という方は、まずこちらの記事からご覧ください。
WebサイトのSEO評価は、検索エンジンのアルゴリズムによって決定する仕組みです。
現在の日本ではGoogleとYahoo! JAPANが主な検索エンジンとしてほとんどのシェアを占めていますが、Yahoo! JAPANはGoogleの検索エンジンを採用しているため、SEOの評価を得るには、Googleに向けた対策を行うと考えて良いでしょう。
またGoogleでは「ユーザーの利便性を第一に考える」という考えのもと、価値のあるWebサイトを上位に表示する方針をとっています。
明確な評価基準は非公表となり、上位表示するWebサイトに偏りがないよう公平な状態です。
したがってSEOの評価基準を知るためには、Googleの方針や考えから推測することが重要といえるでしょう。
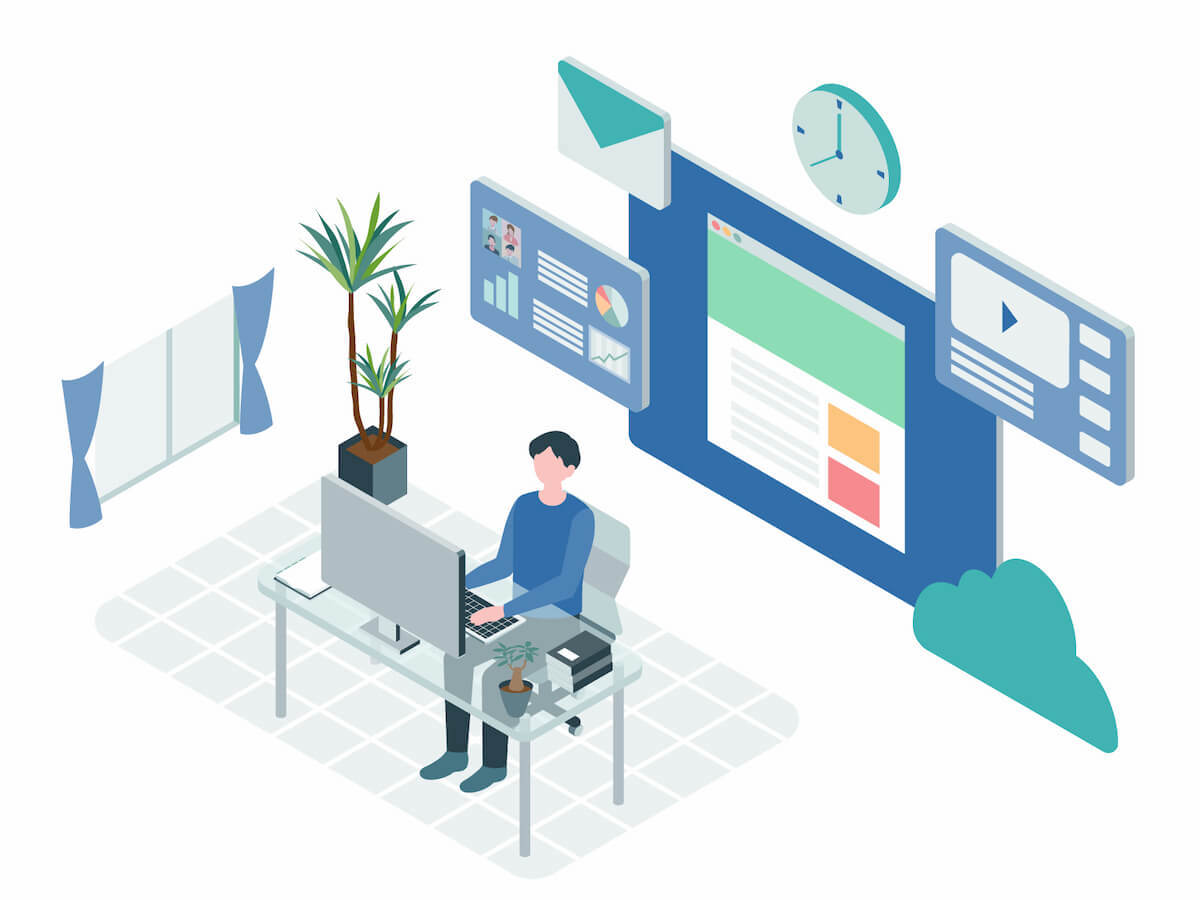
SEOの評価基準を知るためには、まずは評価が決まるまでの流れから確認しましょう。
評価が決まる流れは以下のとおりです。
各々、解説していきます。
まずはクローラーがインターネット上のWebサイトを巡回し、各Webサイトの情報収集を行う「クローリング」からはじまります。
クローラーとは
Webサイトの情報を集めるためのロボット。検索エンジンごとに異なり、Googleでは「Googlebot」である。
クローラーが集める情報はこちら。
コンテンツを新しく公開した場合、クローラーに巡回されるまでは検索エンジンに認知されていない状態となります。
そのため検索結果に表示されるためには、クローラーの巡回を促し、はやくに情報を伝えることが重要です。
次にクローラーが集めた情報を検索エンジンのデータベースに登録する「インデキシング」が行われます。
集めた情報は、まずリンクやページ解析を容易にするための「インデクサ」と呼ばれる中間処理を行います。
そしてHTML要素や情報データに分解し、最終的にはインデックスへ格納される仕組みです。
またSEO用語では、データベースに登録することを「インデックス」といいます。
基本的にクローリングされた情報はインデックスされますが、noindexタグなどを活用することで、インデックスの拒否も可能です。ただしインデックスされなければ検索結果に表示されないため、特別な理由がない限りはインデックスされましょう。
インデックス後は検索アルゴリズムが定めた評価基準に沿い、ユーザーが入力した検索キーワードとの関連性などからランキング付けをします。そして検索結果の画面にて、Webサイトがランキング順に表示される仕組みです。
検索順位はユーザーのニーズを満たすWebサイトが上位に表示されるため、コンテンツ内容からWebサイト情報まで、さまざまな要素から判断されます。
したがって検索エンジンから評価を高めるSEO対策も重要ですが、検索上位化に最も必要な要素は、ユーザーのニーズを満たす有益な情報といえるでしょう。
SEOの検索順位をあげる方法については、以下の記事を参考にしてください。

GoogleではSEOの明確な評価基準を公表していないものの、目安として活用できる資料や情報は存在します。
「Google 品質評価ガイドライン」も参考資料の一つとなり、検索結果の品質に関するマニュアルです。
「General Guidelines」は英語版しか提供されていないため、ここでは内容からSEOの評価基準と基本方針について要約して解説していきます。
Needs Metはユーザーの需要に合った適切な内容を、スムーズに提供できるかを判断する指標です。
Google 品質評価ガイドラインのなかで最も重要視されている項目となり、SEOで良い評価を得るためには欠かせない要素となります。
評価基準については、以下の5段階です。
またNeeds Metで高評価を得るには、以下のポイントを押さえましょう。
Page Qualityは発信する情報の質が高く、信頼できるのかを判断する指標です。
どんなに需要に沿った内容であっても、信頼性のない情報では質が高いといえません。
そのためNeeds Metのつぎに重要とされている項目になります。
評価基準については、以下の5段階です。
またPage Qualityで高評価を得るために重要とされている考え方が、以下の2つになります。
詳しくは、後述の「SEOの評価基準となる考え方4つ」で解説していきます。
ユーザービリティはWebサイトの見やすさや操作のしやすさなど、使いやすさについて判断する指標です。
仮に信頼性があり需要に沿った情報でも、肝心なWebサイトが使いづらければ、ユーザーはストレスを感じるでしょう。そのため快適に操作できるよう、Webサイトの質を高めることも重要です。
押さえておくべき評価項目はこちら。
またGoogleでは2021年の6月に検索順位を決める新しい要素として、コアウェブバイタルを導入しています。
コアウェブバイタルはWebサイトをとおして得られる経験(UX)を判断する指標となり、Google Search Consoleから確認可能です。
コアウェブバイタルについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

SEOの評価基準を考える際は、GoogleがどのようなWebサイトやコンテンツを求めているのか、企業理念や考え方から学ぶ必要があります。
なかでも重要な考え方が以下の4つです。
各々、解説していきます。
E-A-Tは「Google 品質評価ガイドライン」に記載されている評価基準の一つです。
以下の3要素から成り立ち、Webサイトの専門性について解説しています。
Expertise(専門性)
専門的な分野やジャンルに特化したWebサイトのほうがコンテンツの質が高いと判断され、SEOでは高く評価されやすい。
Authoritativeness(権威性)
情報の発信者が、他の人からみて優れていると判断されているのか。被リンクを多く獲得しているWebサイトほど、権威性が高いと判断されやすい。
Trustworthiness(信頼性)
情報の発信者が、信頼性のある人物なのか。Webサイトの管理者情報や紹介記事が掲載されていると、信頼性があると判断されやすい。
現在のSEOでは「コンテンツの質」が重視されているため、E-A-Tをふまえたうえでコンテンツ制作することが重要です。
YMYLは(Your Money Your Life)の略となり、健康やお金など、人々の生活に大きく影響するジャンルのことです。
内容次第では人の人生や命にかかわるジャンルとなるため、Googleではコンテンツの質だけでなく信頼性や権威性などを重視し、厳しい評価基準を定めています。
YMYLに該当するジャンルはこちら。
またYMYLで押さえておくべきポイントは以下になります。
検索上位化が難しい領域のため、ほかのジャンル以上に品質の高さを重視しましょう。
「Googleが掲げる10の事実」はGoogleの企業理念をあらわしたものとなり、SEOの基本的な考えを理解するうえで欠かせない要素です。
全10項目がありますが、ここでは抜粋して紹介していきます。
ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる
Googleが掲げる10の事実のなかで最も重要とされる考えです。ユーザーの利便性を第一に考え、価値のある情報や体験を提供することが大切とされています。
ウェブ上の民主主義は機能する
Googleでは被リンク数を「投票数」と捉え、SEOの評価基準として考えています。そのため外部のサイトから評価を得ることが重要です。
悪事を働かなくてもお金は稼げる
本当に価値のある情報やコンテンツはユーザーに求められると考えています。そのためリンクの売買など、不正な行為はやめましょう。
被リンクの概要や、やってはいけない被リンクなどを解説した記事もあります。
Googleのペナルティとなりやすい重複コンテンツについて解説した記事もあります。
モバイルファーストインデックスは、SEOの評価基準がモバイル版のWebページを軸にする仕組みのことです。
従来まではPC版のWebページを軸に、コンテンツ内容やサイト構造を判断して評価を決めていました。
しかし近年ではPCよりスマートフォンやタブレットの利用率が上回ったことで、Googleも活用されることが多いモバイル版のWebページを主軸としています。
したがって今後Webサイトを運営するうえでは、モバイル対応が必須の条件となり、サイト構造やレイアウトなどもモバイル版に最適化することが重要です。

前述ではSEOの評価基準として検索品質評価ガイドラインやE-A-Tを紹介してきましたが、あくまで評価基準の一つにしかすぎない点には注意をしましょう。
仮に検索品質評価ガイドラインをすべて満たしているからといっても、かならず検索上位に表示されるとは限りません。逆に満たせていないからといって、Googleのペナルティを受けることもないでしょう。
そのためSEOの評価基準や基本方針はあくまで「ヒント」として捉え、ユーザーの立場からニーズや検索意図を考えることが重要です。
またGoogleではSEOの評価はすべて検索アルゴリズムで決定しています。
したがってSEOについてより知識を深めるためには、アルゴリズムに関する理解も大切にしましょう。
Googleのアルゴリズムについては、以下の記事をご覧ください。

SEOの評価を高めるためには、検索エンジンから評価されるWebサイトやページについて知り、SEO対策を実施する必要があります。
ただしSEO対策ではやみくもに実施するのではなく、内部対策と外部対策に分け、しっかりと網羅することが重要です。
とはいっても高く評価されるSEO対策では、WebマーケティングやHTML関連などの専門的な知識も必須となります。
一から学んでいくこともできますが、長期的な取り組みや最新の情報収集など、成功までの道のりは簡単ではありません。
そのため「自分で学び続けることはつらい…」と感じている方は、SEO対策のプロであるTRASPにお任せください。
基本から専門的なSEO対策まで、質の高いサポートをご提供いたします。
SEO対策はこちら
SEOの内部対策と外部対策についてまとめた記事がありますので、合わせてご覧ください。
本記事ではSEOの評価基準について、3つの基本方針と重要な考え方を解説してきました。
SEOの評価基準として考えるべき要素は、小手先のテクニックではなく「ユーザーの利便性を第一に考えること」です。Googleの企業理念にもあるように、本質的な部分を捉えれば結果は後からついてくるため、まずはコンテンツの質に重点を置いて取り組みましょう。
TRASPはSEOの内部・外部対策、そしてコンテンツマーケティングと幅広い施策に対応しています。
お客さまごとに足りない要素を分析したうえで取り組むため、SEOで効果の出ない理由がわからないという方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
