制作ガイド

プロが選んだフリー素材サイト12選!無料で商・・・
2020.06.25
TRASPコラム
制作ガイド
公開日:2023.07.11

「ホームページ制作でトラブルが起きたらどうしよう」「どのようなトラブルがあるのか知りたい」とお悩みではありませんか?
この記事では、「知らないとやばい!」トラブル事例をランキング形式で紹介します。ホームページ制作業界を熟知したTRASPが、事例数や危険度などをもとに順位をつけたので、参考にしてみてください。
また、トラブルにならないための対策や、問題が起きたときの対処法も丁寧に解説します。この記事を読めば、制作をスムーズに進める方法や優良業者に依頼するためのポイントがわかりますよ。
専門用語もなるべく使わずに説明するので、知識がない方も安心して読んでみてください。
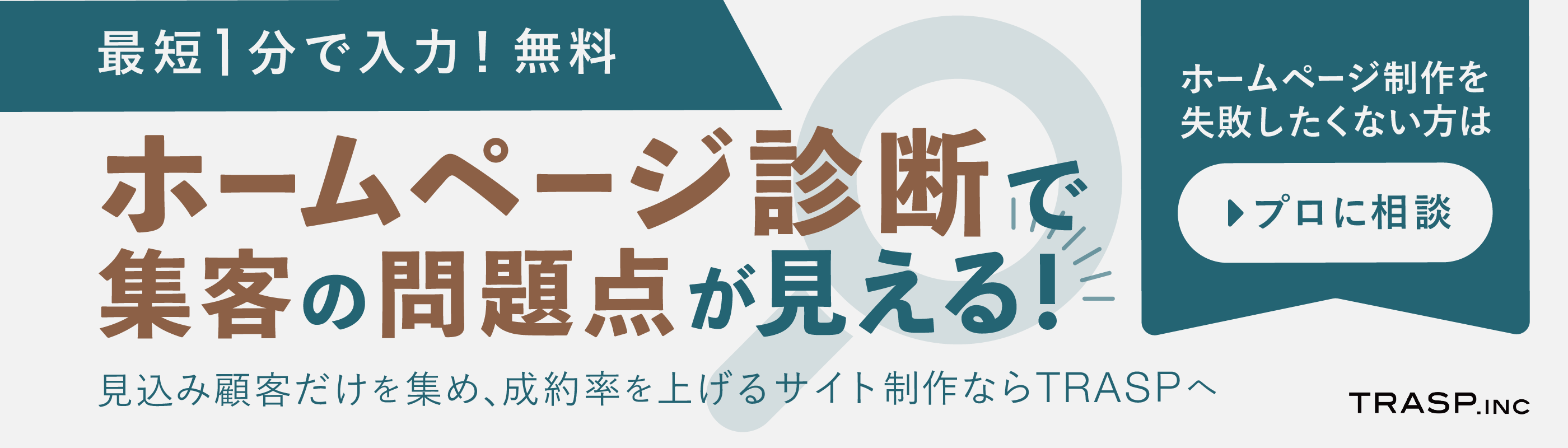
目次

なぜホームページ制作会社とのトラブルは起きてしまうのでしょうか。
実はトラブルには、「悪質な詐欺に遭うケース」と「クライアント側に原因があるケース」の2通りがあるのです。
残念ながら、悪意を持って顧客を騙そうとする制作会社も存在します。たとえば、お金を払ったあとに音信不通になったり、明らかに要望と異なるホームページを納品されたりする事例が多いです。
悪徳業者に騙されないためには、この記事で紹介するトラブル事例から、悪質な手口を知ることが大切です。記事の後半では、悪徳業者を選ばないためのポイントも紹介するので、参考にしてみてください。
優良業者であっても、クライアント側(あなた)の問題がトラブルにつながることがあります。
たとえば、「ホームページなんて簡単に作れるでしょ」「少し修正するだけなら当日に終わるよね」といった勘違いをしているケースです。知識が不足していることで、不可能な要望をしてしまうクライアントは少なくありません。
また、契約書を見ていない、あるいは説明を聞いていないことによって生じる認識のズレが、トラブルにつながることもあります。
このように制作会社とのトラブルは、ちょっとした確認不足やすれ違いによって生じることが多いです。そのためトラブルを避けるためには、ホームページ制作に関する基礎知識を学ぶことが大切になります。

ここからは、ホームページ制作業界を熟知したTRASPが見聞きしたトラブルを、ランキング形式で紹介します。1~5位は、知っておかないとやばいことになるかもしれません。今のうちに把握しておきましょう。
最も多いのは、お金に関するトラブルです。トラブルの実情を知るために、まずはホームページ制作の費用についてみていきましょう。かかる費用としては主に2つ。
初期費用
ホームページの構築・公開にかかる料金
運用費用
公開後のサポートにかかる料金
たとえば初期費用が格安、あるいは無料の場合、コストを削減できると思うかもしれません。しかし実際には「初期費用0円で月額5万」だとすれば1年間で60万円、2年間で120万円にものぼり、総額は相場以上になるケースも多いです。初期費用の安さだけで依頼しないようにしましょう。
また、契約後の追加請求によって、予算以上のコストがかかったというトラブルもあります。これは、契約前に依頼範囲を明確にしておかなかったことが原因です。
見積もりの際には、以下のように、プラン内の作業とプラン外(追加料金)の作業を明らかにしてもらいましょう。
期待していた仕上がりにならなかったというトラブルも少なくありません。
基本的には、1~3回ほどの修正対応をしてもらえますが、悪質な業者だと一度も修正してくれないことがあります。そのため依頼の際には、納品時の修正の上限回数を確認しておきましょう。
また、クライアント側に問題があって、品質が下がることもあります。打ち合わせで何も要望を伝えなかったり、何度も意見が変わったりすると、制作会社が本来の実力を発揮できません。下記のような要望を制作会社に伝え、協力してホームページを作っていきましょう。
制作したホームページの著作権や所有権に関するトラブルも多いです。制作会社に権利があると、依頼先を変えたいと思っても権利を譲渡してくれないことがあります。最悪の場合、解約時にホームページを削除されてしまうことも。そのため、契約の前に著作権と所有権について確認しておきましょう。
基本的には、クライアント側に権利を渡してくれます。万が一、制作会社側が持つ場合は、解約後や満了後のホームページの取り扱いについて相談しておくことが大切です。また、イラストやアニメーションを制作会社に作成してもらう場合は、そのコンテンツに対する権利も確認しておきましょう。
中途解約できない年単位の契約には注意しましょう。解約できないと、ホームページが不要になった際や、対応に不満を覚えた際にも依頼先を変更できません。なかには、解約できると伝えられていても、実際には違約金が高額で解約できないケースもあります。そのため見積もりの際には、契約期間や解約方法などを確認することが大切です。
特にリース契約には注意が必要です。
リース契約のリスク
ホームページ制作におけるリース契約は、中小企業庁からも注意喚起されています。リース契約を提案してくる制作会社には、依頼してはいけません。
ホームページは、一度公開して終わりではありません。効率的に集客するためには、コンテンツを増やしていく・定期的に更新をするなどの運用が必要です。そのため多くの制作会社では、下記のようなサポートを提供しています。
しかし、まったくサポートしてくれなかったり、一つひとつの作業に高額な費用を請求したりする悪徳な業者もいます。契約時に、運用のサポートの内容や料金を確認しておきましょう。
公開後のサポートが充実している制作会社をお探しなら、TRASPにご相談ください。毎月5記事〜依頼可能な「コラム運用サービス」をはじめ、さまざまなアフターフォローを提供中です。自社コラムのPV数を1年で595%アップさせたノウハウをもとに、集客力アップをお手伝いいたします。
お客さまの業務内容やゴールに合わせてお見積もりいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら

ここからは、ホームページ制作のトラブルランキング6位~10位を紹介します。小さなリスクでも重なれば大きなトラブルに発展するため、極力避けられるように、把握しておきましょう。
ホームページを構築するシステム面は、デザインなどとは違って目に見えないので、知識のない方では問題に気付きにくいです。そのためここでは、システムの品質を疑うべき、制作会社の特徴を紹介します。
まず、ホームページを作るソフトウェアであるCMSについて、何も説明してくれない業者は不親切です。
CMSの使い方がわかれば自社でちょっとした修正や新着情報などを更新できるものの、CMSの情報を共有してくれないと制作会社にまかせっきりになります。
なかにはマイナーなCMSを用いたり、ログイン情報を教えなかったりして、その制作会社にしか頼れないように仕向ける悪質な会社も。契約の前に、どのCMSを使用するのか、クライアント側でも更新できるかなどを確認しておきましょう。
その他、システム面において、下記のようなトラブルにも注意が必要です。
「ホームページを作ったのに集客できない」「絶対に成果が出ると言われたのに…」という悩みも多いです。
結論から言うと、ホームページ運用に「絶対」や「必ず」はありません。なぜなら、検索エンジンの検索結果に表示される順位は、コントロールできないからです。そのため、「絶対成果を出します!」とアピールしてくる会社には、依頼してはいけません。
検索してもホームページが出てこない
コラム記事などは、公開直後だったり、検索上位の競合が大手企業だったりすると、検索しても表示されないことがあります。
そのためまずは、会社名などの固有名詞で検索してみましょう。トップページなどが検索結果に表示される場合は、きちんとインターネット上に登録されています。1ページも表示されない場合は制作に問題がある可能性が高いので、一度担当者に相談してみましょう。
また、スキルのある優良業者であっても、成果が出ないこともあります。その際は、どうして成果が出ないのか、別の戦略はないのかなどを担当者に相談してみましょう。
きちんとした分析をもとに具体的なプランを提示してくれる制作会社は、継続して依頼しても良いでしょう。一方で「わからない」「難しい」としか回答がない場合は、依頼先を変えてみましょう。
人手不足の会社では、納期が過ぎても納品されないケースがあります。きちんと理由を説明してくれれば多少は安心できますが、悪徳業者は連絡なしに遅れることも。そのような会社は放置するといつまでも納品してくれないので、どのくらい遅れるのかを確認してみましょう。
また、納期の大幅な遅れのように、制作会社側に明らかな落ち度がある場合は、契約解除できることがあります。契約の際には、納期が遅れる際の対応や、問題があった際の契約解除について聞いてみましょう。
ただし制作中に「デザインはこれでいいか?」「打ち出すサービス内容に間違いはないか?」といった確認が制作会社から来ることがあり、クライアントの回答の遅れによって、納期が遅れてしまうこともあります。制作会社から質問などの連絡が来た際には、なるべく早く返信しましょう。
担当者との相性が悪かったり、返信が遅かったりして悩んでいる方も多いです。十分な人手のいる優良業者であれば、担当者変更に応じてくれるでしょう。しかし人手不足の会社では、担当者を変更できないことも多いです。担当者の対応が悪い、かつ変更できない場合は、依頼先を変えましょう。
また、「訪問営業でなかなか帰ってくれなかった」「見積もり時の対応が不親切だった」といった不信感のある会社は、おそらく契約後の対応も悪いです。制作プランが魅力的に見えても、依頼しないようにしましょう。
契約する際には、まさか制作会社が倒産するとは思わないでしょう。しかしホームページ制作に限らず、契約後に倒産するトラブルは日々起きています。たとえば、全額先払いの契約を結んでお金を払ったのに、納品前に倒産してしまうことがあります。
経営状況をすべて把握するのは難しいものの、人手が足りずにバタバタしている印象がある会社や、支払いを急かされる会社には警戒しましょう。
また、サーバーやドメインを制作会社が管理している場合は、倒産と同時にホームページを利用できなくなることがあります。万が一に備えて、ログイン情報を共有してもらったり、経営悪化の際の対応について確認しておいたりすると安心です。

結論からいうと、ホームページ制作でトラブルが起こった際には、第三者に相談しましょう。知識のない方が一人で悩んでいると、悪徳な制作会社はその不安に付け込んできます。さらなる被害につながるので、専門家への相談がおすすめです。
お金や契約に関するトラブルは、弁護士の得意分野です。制作会社の顧問弁護士からアプローチがあった場合や、裁判になる場合でもスムーズに対応してもらえます。
とはいえ、どの弁護士に依頼すれば良いのかわからない方も多いでしょう。そのような方は、日本弁護士連合会が運営する「ひまわりほっとダイヤル」の利用がおすすめです。中小企業向けの法律相談を受け付けており、目的に合った弁護士と面談できます。
いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いという方は、都道府県や市区町村の消費者センターへの相談がおすすめです。トラブルの解決に向けて、専門の相談員が公正な立場でアドバイスしてくれます。まずは消費者ホットライン「188」に電話し、消費生活相談窓口を紹介してもらいましょう。
ただし、弁護士のように解決まで担ってくれるわけではありません。裁判などの法的な手続きが生じる場合は、弁護士への相談が必要です。
ホームページのプロである制作会社に、相談してみるのも一つの手です。今依頼している制作会社の問題点などをプロの視点で指摘してくれる可能性があります。
ただし制作会社の解決方法は、新しいホームページを作る、あるいは運用を引き継ぐことがメインです。弁護士のように法的な問題などを解決できるわけではありません。

最後に、ホームページ制作でトラブルにならないための4つのポイントを解説します。トラブルのリスクは、ちょっとした工夫で避けられるので、ぜひ実行してみてください。
サーバーやドメインを制作会社が管理していると、依頼先を変える際に揉めてしまうかもしれません。そのリスクを避けるためには、サーバーとドメインを自ら契約するのも一つの手です。インターネットには、サーバーなどの契約方法を解説する記事が多数投稿されているので、専門的な知識がなくても契約できます。
サーバーとドメインの契約を制作会社にまかせる場合は、ログイン情報は共有してもらえるか、所有権はどちらが持つのかなどを確認しておきましょう。
契約書をきちんと見ていなかったことによるトラブルも多いです。少しの手間を惜しんだことで、将来的に何倍もの手間がかかることもあるので、しっかり確認しておきましょう。
契約時にチェックするポイント
きちんと見られているか不安な場合は、第三者にリーガルチェックしてもらいましょう。
依頼時は見積もりを比較してじっくり検討したのに、依頼後は制作会社に丸投げになってしまう方も多いです。まかせっきりになると、制作会社もどのように進めていけば良いのかわからなくなってしまいます。
そのため、制作会社から打ち合わせや施策の案内があった際には、積極的にコミュニケーションを取りましょう。もちろん、あなたから「ここが気になる」という指摘をしたり、アイデアを出したりするのも有効です。
ホームページは作ることがゴールではありません。コストに見合った成果を出せるように、制作会社と協力していきましょう。
知らないとやばいホームページ制作におけるトラブル事例と、悪徳業者を避けるためのポイントを紹介しました。
ホームページ制作でのトラブルは、詐欺のように制作会社に悪意があるケースだけではありません。クライアント側の知識不足などによる認識のズレが、トラブルにつながることもあります。
そのため制作会社に丸投げするのではなく、自らも学びながらホームページを成長させていくことが大切です。それでも問題が起きてしまった場合は、弁護士などの第三者に相談しましょう。
安心してまかせられる会社をお探しの方は、企画から運用まで一貫対応できるTRASPにご相談ください。積極的にお客さまの声に耳を傾け、トラブル防止に努めます。
お問い合わせはこちら