ブランディング
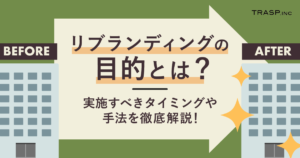
リブランディングの目的とは?実施すべきタイミ・・・
2023.03.08
TRASPコラム
ブランディング
更新日:2023.04.09
公開日:2023.03.14
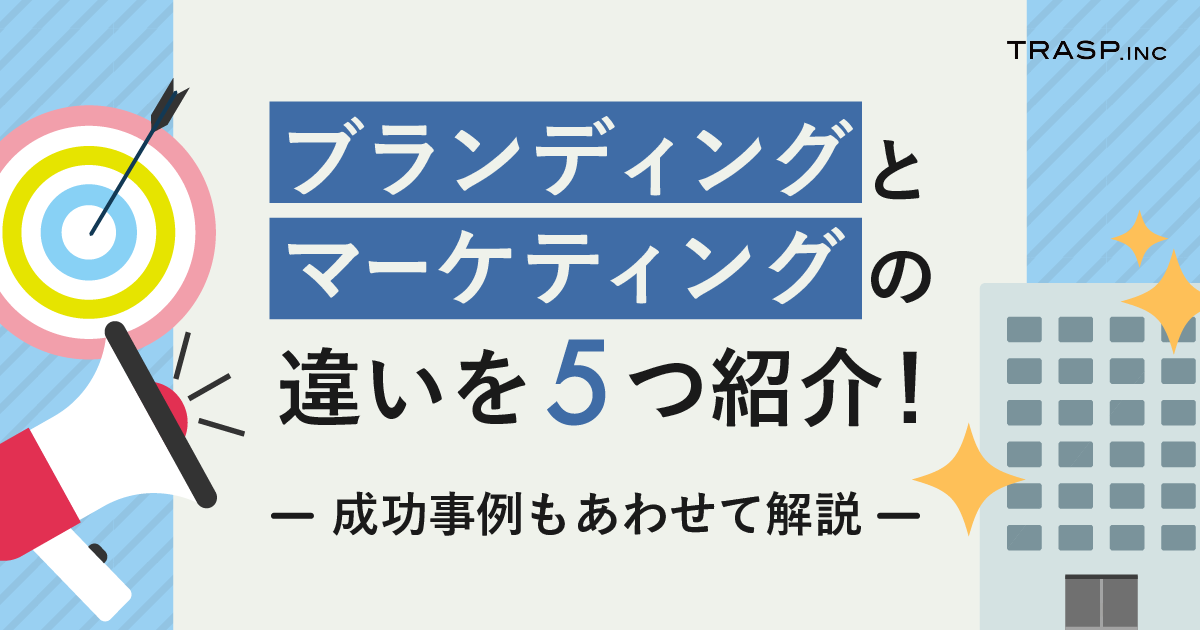
自社のWeb集客を実践するなかで、
「ブランディングやマーケティングに興味があるが、何から手を付けて良いの?」
「そもそも両者の違いや関係性がわからない」
このように悩まれているご担当者さまもいらっしゃるでしょう。
「マーケティング」「ブランディング」は使う人によって定義が異なり、混同されることが非常に多いです。自社のブランド戦略・マーケティング施策をスムーズに進めるためにも、まずは両者の目的や役割をしっかり押さえると良いでしょう。
この記事ではブランディングとマーケティングの違い5つを徹底解説!これまでさまざまな企業のマーケティングを支援してきたTRASPが、成功事例もあわせて解説します。
目次

ブランディングとマーケティングは別ものですが、合わせて行うことで相乗効果を発揮します。まずは両者の定義について、詳しく見ていきましょう。
ブランディングとは言葉通り、“ブランド”を築き上げるためのさまざまな活動のこと。企業や商品・サービスの価値を高め、消費者に認知させることを目的としています。
例えば「リンゴマークのロゴ=アップル社の製品」のように、会社名や商品名を見聞きしたら、頭のなかで特定のイメージ・ブランド価値が想起されるのではないでしょうか。
このように「〇〇といえばこの会社」という風に、社名や商品・サービス名を聞いた時に、消費者がパッとイメージを確立させる行為がブランディングに該当します。
マーケティングとは商品・サービスが売れる仕組みづくりのことで、“あくまでも商品を売ること”を目的としています。具体的には、下記のような手順を踏むことが多いです。
また、広告宣伝・市場調査や顧客分析・SNSでのコミュニケーション・オンラインコンテンツ提供といった、幅広い活動もマーケティングに含まれます。
したがって、両者は単体でも行えます。なので「ブランディングは必要ない」と思っている方もいるかもしれません。
しかし「リンゴマーク=アップル」という土台があれば、広告を打てばすぐに「アップル製品だ!」と認識してもらえるなど、合わせて行うことで相乗効果が生まれます。
そのためマーケティングと並行し、ブランディングを行うことをおすすめします。
マーケティングの重要定義7つと実践方法3ステップを紹介します。こちらもぜひご覧ください。

さきほど“ブランディングとマーケティングは別ものである”とお伝えしました。しかし「具体的には何が違うの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
そこでこの項目では、ブランディングとマーケティングの5つの違いをご紹介します。
1つ目の違いは、狙いです。
ブランディングの狙いは「自社のブランド価値を向上させること」。自社や商品・サービスのブランド価値を上げ、好意的な印象を持つファンを増やすことを目指しています。
ブランディングで施策を考える際は「どうすれば消費者に選ばれ、愛されるブランドになれるだろうか?」という思考のもと、立案を進めていきます。
対して、マーケティングの狙いは「売上やシェアを拡大させること」で、自社のブランド価値の向上に重きを置いていません。
「どうすれば商品・サービスを利用してくれる人が増えるか」を軸とし、企業や商品・サービスの価値をより多くの人に届けることを目指しています。
マーケティングで施策を考える際は「より販売実績を伸ばすには、どのような仕組みが必要か」という思考で、意思決定を行っていきます。
2つ目の違いは、指針です。
ブランディングの指針は、「Why(なぜやるのか?)」。
「なぜこのブランドが存在すべきなのか」「なぜブランド価値を顧客に提供するのか」といった、存在意義を深く追及します。その結果、ブランドのストーリーやビジョン、アイデンティティといったものを確立できるでしょう。
一方でマーケティングの指針は、「How(どうやるのか?)」。
合わせて行う場合、ブランディングの指針である“Why”に伴い、「ターゲットに向けて、ブランドストーリーやビジョンをどう届けるのか」という、手法を模索するのがマーケティングです。また、主にテレビや新聞などのマス広告、Web広告などの多彩な施策が候補として含まれる点も特徴。さまざまな広告手段からターゲットに合わせ、適切なチャネルを選択することが重要です。
3つ目の違いは、ターゲット・ターゲット心理です。
ブランディングのターゲットは「ファンになってくれる人」で、マーケティングのターゲットは「購入してくれる人」となります。
マーケティングでは商品・サービスの価格を他社よりも安く設定し、購入を促進させることも考えられます。しかしブランディングでは、価格に関係なく買ってもらえるような消費者に情報を届けなければなりません。
そのためブランディングのターゲットは「好き」or「嫌い」、マーケティングのターゲットは「必要」or「不要」で購入を判断できるよう、設定を進める必要があります。
4つ目の違いは、手段です。
前述したように、ブランディングは“消費者との良好な関係づくり”を目指しています。そのための手段としてファン心理を育成し、自社のブランドイメージを構築していくのです。
一方でマーケティングは、商品理解を促進させることが手段です。「どのような商品なのか」「購入することで得られるメリットは何か」を消費者に訴求し、狙いである購買行動の喚起を行っていきます。
5つ目の違いは、期間です。
両者の取り組みにおける期間は大きく異なり、一般的に「ブランディングは長期的な施策」「マーケティングは短期的な施策」となります。
マーケティングの狙いである「購買行動を促し、売上やシェアを拡大させること」自体は、短期的にも生じる確率が高いです。
しかしブランディングの狙いである「自社の想起イメージを浸透させ、ブランド価値を向上させること」は、すぐに実現するものではありません。長い時間をかけて、顧客の頭のなかに知覚されるよう活動を続けることが大切です。
TRASPでは豊富なマーケティング実績をもとに、ユーザー目線で興味をもつホームページ制作を行っています。デザインや導線を一から設計しご提案していますので、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
自社のブランド戦略を軌道に乗せるには、実際にブランディングに成功した事例を学ぶと良いでしょう。つづいて、ブランディングで参考にしたい成功事例をご紹介します。
https://www.hoshinoresorts.com/
星野リゾートは日本屈指の総合リゾート企業で、開業して100年以上の歴史を持ちます。
同社はもともと温泉旅館の運営をしていましたが、1995年に現社名に変更。同時に「お客様にサービスを聞くのではなく、自分のこだわりをサービスにしていく。」をブランドアイデンティティとして掲げるようになりました。
当時のホテル業界に浸透していた“すべてをお客さまに合わせること=サービス”という概念を破り、独自のポジションを確立していきます。
また同社は下記5つのサブブランドを用意し、さまざまな顧客のニーズに応えています。
これらのサブブランドを作った理由として、「各施設のブランドが明確になるぶん、顧客が自分にマッチするものを選択できること」「グループ全体でのリピーター率UPに期待できること」が挙げられます。
「さまざまなところに宿泊してみたい」という顧客のニーズを汲み取り、全国で星野リゾートを楽しめるような戦略が練られている点に注目です。
アメリカに本社を置くIBMは、公的機関・企業にパソコン関連機器やサービスを提供しています。同社は、2017年に「コグニティブコンピューティング」をキーワードとし、自社製品やサービスを新たに定義しました。
「コグニティブコンピューティング」とは、“コンピューターが人間のように自ら理解・推論・学習するシステム”のこと。構造化データ・非構造化データの両方を取り扱うことで、あふれる情報のなかで人間がよりすぐれた判断ができるようになります。
その結果、「人間の力では処理が難しいビックデータの解析」「これまで人間の判断が必要だった業務を代行し、作業時間を削減する」といったことが可能に。人がよりクリエイティブに、かつ革新的なアイデアを生み出す仕事に集中できる環境づくりを行います。
そして、この新たな定義により、同社がプッシュしている人工知能「Watson」の知名度が向上しました。“IBMが提供するソリューション”として各方面から支持され、大きく売上を伸ばしています。
既存のITシステムと差別化を図り、自社のブランディングに成功した事例です。
次に、マーケティングで参考にしたい成功事例を見ていきましょう。
大手家電メーカーのシャープ株式会社は、SNSマーケティングで大きく成功しました。2023年2月時点でフォロワーは83万人を超えており、絶大な人気を集めています。
同社のTwitterの公式アカウントは、「シャープさん」という愛称で親しまれています。さらに「きょうの晩ごはん教えて」「他のメーカーの方が良い」など、良い意味で大企業らしくないフランクな印象の投稿が特徴的。遊び心あふれる個性・適度なゆるさを感じさせる発信内容が、ユーザーの興味をグッと掻き立てます。
また自社サイトの抽選ページがアクセス過多でパンクし、苦情が殺到した際には「このアカウントも502 Bad Gateway出したい」とツイート。あと一歩で炎上という危機を回避し、和やかな雰囲気に変えたことでも知られています。
ユーザーに楽しんでもらうことを主軸とした情報発信により、自社の知名度向上・ファンの獲得につながった事例です。
競争が激しい飲食業界で、揺るぎないポジションを確立しているのがスターバックス。ドリンクは1杯600円前後と決して安くないものの、根強いファンが多く存在しています。
同社はCMや広告を一切出さず、実際に店舗に足を運んだ利用者の「店舗体験」をベースにマーケティング戦略を練っています。
上記のように従来のカフェとは一線を画した、心地の良い空間づくりを徹底。「スターバックスでしか味わえないひととき」というブランドアイデンティティを確立しました。
競争しがちな「価格」ではなく、「お客様が満足できる高いホスピタリティ」を提供価値としたことで、大きな成功を収めています。
こちらの記事では、企業のマーケティング成功事例12選を詳しくまとめています。

さきほど“ブランディングとマーケティングは合わせて行うことで相乗効果が生まれる”とお伝えしましたが、やはり両者は連動させると良いでしょう。
なぜなら、ブランディングとマーケティングに違いはあるものの、完全には切り離せるものではないため。お互いに必要不可欠な存在といっても、大げさではありません。
極端な例を出すと、ブランディングがなくても商売自体はできます。「ニーズがあるものをつくる」「正しい相手に、適切無価格で」「適切なチャネルを用いて、ただ売れば良い」、それでよければマーケティングを行うだけでもOKです。
しかしそれだけでは企業価値を高められず、消費者から求められる存在にはなれません。
そのためブランディングにより、“ブランド全体の価値を高める”ことが必須なのです。「長期的な顧客がつく」「付加価値があがる」「ファンが増える」といった効果に期待できるため、より企業としての成長も望めます。
したがって、商品や自社のフェーズに応じて「ブランディングが必要なのか」「マーケティングが必要なのか」を見極め、相互を連動させていくことをおすすめします。
幅広い業種のホームページをブランディングしてきた経験や実績が豊富なTRASPでは、ブランド戦略の擦り合わせや目的のヒアリングをしっかりと行い、集客の強化に効果を発揮するブランディングを行います。
TRASPの強み

ここまでブランディングとマーケティングの定義や違い、成功事例などを紹介しました。両者が持つ目的や役割は異なりますが、いずれも“企業の経営には欠かせないものである”とおわかりいただけたのではないでしょうか。
ブランディングやマーケティング自体は、自社のみで進めることもできます。しかし“多くの人の心を惹きつける戦略を実行するため”には、専門的な知識やノウハウを駆使することが欠かせません。
そのため「自社のブランドをより育みたい」「確実に利益向上を図りたい」と考える方は、ホームページ制作会社への依頼がおすすめです。
当社はこれまでに「広告を使わずにサイトアクセスが10倍以上に伸びた」「自社コラム運用でアクセス数を1年で10倍UPを実現した」など、多くの実績を保有しています。また幅広い業務のWeb集客に携わった経験から、企業に合った戦略を見出し、ベストなプランニングをご提案いたします。
「自社に合うブランディング・マーケティングの戦略を知りたい」と悩まれている方は、ぜひ一度お話を聞かせていただけませんか?
この記事では、ブランディングとマーケティングの違い5つをご紹介しました。成功事例もあわせて解説しましたが、いかがでしたか?
ブランディングとマーケティングは「狙い」「指針」といった点は異なりますが、密接に関係しています。また両者は合わせて行うことで相乗効果を得られるため、集客効果を最大限に引き出すには連動させることが大切です。
紹介した事例を参考に、自社に合う施策をぜひ実行してみてくださいね。
TRASPではホームページ制作を軸に、Webマーケティングを活用したブランディング戦略をご提案しています。お客さまの悩みや課題をヒアリングしたうえで、課題解決につながる戦略をご提案していますので、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら